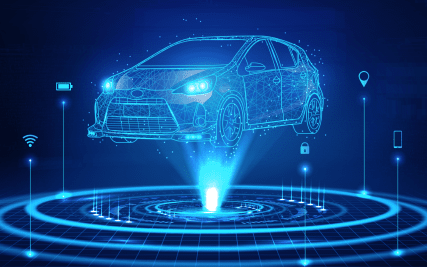Secure First, Then Ride
自動運転を超え、
モビリティサービスまで
人とインフラとモビリティをつなぐ
自動運転を超え、
モビリティサービスまで
人とインフラとモビリティをつなぐ
自動運転を超え、
モビリティサービスまで
人とインフラと
モビリティをつなぐ
アウトクリプトはより安全なコネクテッド技術で
モビリティを革新します
アウトクリプトはより安全なコネクテッド技術で
モビリティを革新します
自動運転を超え、
モビリティサービスまで
人とインフラとモビリティをつなぐ
自動運転を超え、
モビリティサービスまで
人とインフラと
モビリティをつなぐ
アウトクリプトはより安全なコネクテッド技術で
モビリティを革新します
アウトクリプトはより安全なコネクテッド技術で
モビリティを革新します
アウトクリプト株式会社(AUTOCRYPT Co., Ltd.)は、世界唯一無二の自動車セキュリ ティEnd to Endソリューションを提供する「自動運転サイバーセキュリティ企業」です。
自動運転技術の高度化に伴い、自動車のサイバーセキュリティ対応への要求も益々高くなっています。
私たちは、人とクルマとインフラをより安全につなぎ、スマートモビリティ社会の実現に取り組んでいます。
より安全な自動運転の実現に欠かせないV2X。
AutoCryptはV2Xに参加する全てのコンポーネントに対しセキュリティソリューションを提供します。
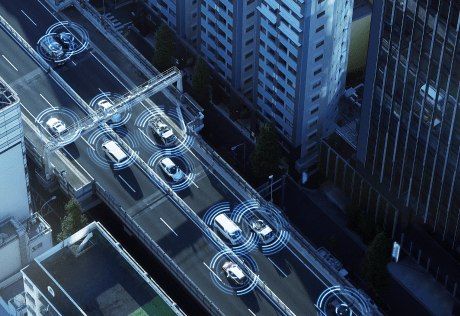

自動車通信セキュリティに必要とされるファイアウォールおよび侵入検知システムの機能とECUの安全な通信確立に必要なセキュリティ・モジュールを提供します。
車載システムの開発に最も必要である脆弱性検知からセキュリティ対策の有効性検証まで確認できるテスティングプラットフォームを提供します。システム連携を支援しているため、外部機関との情報共有が容易になります。

車両運行を管理し最適化するフリートマネジメントシステム(FMS)及び交通弱者向けバウチャータクシーとオンデマンド型乗合交通(DRT)サービス、マルチモーダルサービスなどを提供します。

2020年6月、自動車へのサイバー攻撃対策を義務付ける「WP29」が採択されました。これにより、国土交通省は道路運送車両法の改正を行い、2022年7月以降、自動車メーカー及びTier1サプライヤにはWP29への準拠が求められます。
アウトクリプトは、WP29に完全対応するサイバーセキュリティコンサルティングを提供します。