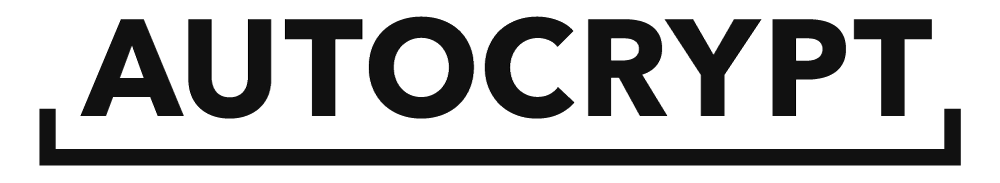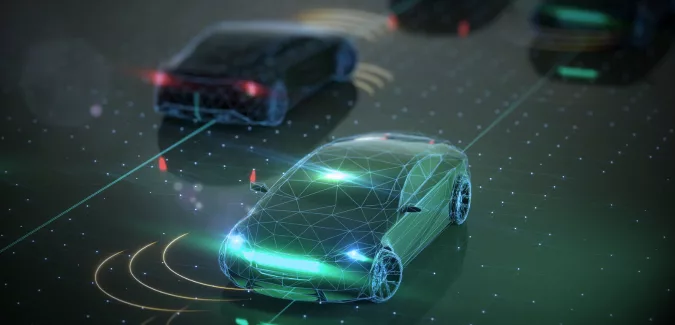SOVDгҒЁгҒҜпјҹSDVжҷӮд»ЈгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘж–°гҒ—гҒ„иЁәж–ӯиҰҸж ј

иҖҗйҮҸеӯҗиЁҲз®—ж©ҹжҡ—еҸ·пјҲPQCпјүгҒЁгҒҜпјҹиҮӘеӢ•и»ҠгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘж–°гҒ—гҒ„жҡ—еҸ·ж–№ејҸ
2025е№ҙ10жңҲ31ж—Ҙ
гӮўгӮҰгғҲгӮҜгғӘгғ—гғҲ, CES 2026гҒ«еҮәеұ•вҖҰ AIжҷӮд»ЈгҒ®ж¬Ўдё–д»Ји»ҠијүгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈжҠҖиЎ“гӮ’е…¬й–Ӣ
2025е№ҙ11жңҲ28ж—Ҙ
иҝ‘е№ҙгҖҒиҮӘеӢ•и»ҠжҘӯз•ҢгҒ§гҒҜгҖҢгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўе®ҡзҫ©и»ҠдёЎпјҲSoftware-Defined VehicleпјҡSDVпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’иҖігҒ«гҒҷгӮӢж©ҹдјҡгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮз°ЎеҚҳгҒ«иЁҖгҒҶгҒЁгҖҒSDVгҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®гҖҢж©ҹжў°гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гӮҜгғ«гғһгҖҚгҒӢгӮүгҖҒгҖҢгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гӮҜгғ«гғһгҖҚгҒёгҒЁеӨ§гҒҚгҒҸгӮ·гғ•гғҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸжөҒгӮҢгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯеҝғгҒ«гҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒй«ҳгҒ„еҮҰзҗҶиғҪеҠӣгҒЁиЁҲз®—иғҪеҠӣгӮ’еӮҷгҒҲгҒҹй«ҳжҖ§иғҪгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝпјҲHPCпјҡHigh Performance ComputerпјүгҒ§гҒҷгҖӮгӮҜгғ«гғһгҒ®дёӯгҒ«гҖҒгҒҫгӮӢгҒ§гғҮгғјгӮҝгӮ»гғігӮҝгғјгҒ®гӮөгғјгғҗгғјгҒҢијүгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®HPCгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒ“гҒқгҖҒгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўе®ҡзҫ©и»ҠдёЎпјҲSDVпјүгҒҜе‘ЁеӣІгҒ®зҠ¶жіҒгӮ’гғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒиҮӘгӮүеҲӨж–ӯгҒ—гҒҰеӢ•гҒҸй«ҳгҒ„иҮӘеҫӢжҖ§гӮ„гҖҒгӮҜгғ©гӮҰгғүгӮ„д»–гҒ®и»ҠдёЎгғ»гӮӨгғігғ•гғ©гҒЁгҒӨгҒӘгҒҢгӮӢй«ҳгҒ„зӣёдә’жҺҘз¶ҡжҖ§гӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҒ§гҖҒгҖҢи»ҠдёЎиЁәж–ӯгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҰізӮ№гҒӢгӮүиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘгғ‘гғ©гғҖгӮӨгғ гӮ·гғ•гғҲгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иЁәж–ӯеҹәжә–гҒҜгҖҒдё»гҒ«гӮ»гғігӮөгғјгӮ„гӮўгӮҜгғҒгғҘгӮЁгғјгӮҝгғјгҖҒгҒқгҒ®й…Қз·ҡгҖҒECUй–“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгғҗгӮ№гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®ж•…йҡңгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢгҒ“гҒ®гӮ»гғігӮөгғјгҒ®еҖӨгҒҢгҒҠгҒӢгҒ—гҒ„гҖҚгҖҢгҒ“гҒ®ECUгҒЁгҒ®йҖҡдҝЎгҒҢйҖ”еҲҮгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҖҒгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгӮ„й…Қз·ҡгғ¬гғҷгғ«гҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«гӮ’жӨңеҮәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёӯеҝғгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒHPCгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰй§ҶеӢ•гҒ•гӮҢгӮӢSDVгҒ§гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜдёҚеҚҒеҲҶгҒЁгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢгҒ©гҒ“гҒӢгҒ®йғЁе“ҒгҒҢеЈҠгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҖҚгӮ’иҰӢгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒHPCдёҠгҒ§еӢ•дҪңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиӨҮйӣ‘гҒӘгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®еӢ•дҪңзҠ¶жіҒгӮ’и©ізҙ°гҒ«еҲҶжһҗгҒ—гҖҒз•°еёёгӮ„дёҚе…·еҗҲгӮ’зҡ„зўәгҒ«иЁәж–ӯгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒSDVжҷӮд»ЈгҒ®иЁәж–ӯгҒҜгҖҒеҫ“жқҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўдёӯеҝғгҒ®гҖҢеЈҠгӮҢгҒҹйғЁе“ҒжҺўгҒ—гҖҚгҒӢгӮүгҖҒгҖҢгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒЁгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўгӮ’дёҖдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰжҚүгҒҲгҖҒгҒқгҒ®гғ©гӮӨгғ•гӮөгӮӨгӮҜгғ«е…ЁдҪ“гӮ’з®ЎзҗҶгғ»жӨңиЁјгҒҷгӮӢиЁәж–ӯгҖҚгҒёгҒЁеҪ№еүІгҒҢжӢЎеӨ§гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹж–°гҒ—гҒ„иҰҒжұӮгҒҢгҖҒеҫ“жқҘгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢж–°гҒҹгҒӘиЁәж–ӯеҹәжә–гӮ„иЁәж–ӯгғ•гғ¬гғјгғ гғҜгғјгӮҜгӮ’е®ҡзҫ©гҒҷгӮӢеӢ•гҒҚгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®д»ЈиЎЁдҫӢгҒ®дёҖгҒӨгҒҢжң¬зЁҝгҒ§еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮӢSOVDпјҲService Oriented Vehicle DiagnosticsпјүгҒ§гҒҷгҖӮ
SOVDгҒЁгҒҜдҪ•гҒӢ
еҫ“жқҘгҒ®и»ҠдёЎиЁәж–ӯгҒҜгҖҒи»ҠијүECUпјҲйӣ»еӯҗеҲ¶еҫЎгғҰгғӢгғғгғҲпјүгҒ”гҒЁгҒ«еҖӢеҲҘгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҹиЁәж–ӯгғ—гғӯгғҲгӮігғ«пјҲдё»гҒ«UDSпјҡUnified Diagnostic ServicesпјүгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзҸҫеңЁгӮӮгҒ“гҒ®гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒҜеәғгҒҸеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиҝ‘е№ҙгҒ®SDVеҢ–гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰи»ҠдёЎгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒҢиӨҮйӣ‘еҢ–гҒ—гҖҒHPCгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҒЁгҒҷгӮӢи»ҠијүгӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгҒ®еҪ№еүІгҒҢжӢЎеӨ§гҒҷгӮӢдёӯгҒ§гҖҒECUеҚҳдҪҚгҒ§гҒ®иЁәж–ӯгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜе°ҶжқҘгҒ®иҰҒжұӮгӮ’еҚҒеҲҶгҒ«жәҖгҒҹгҒ—гҒҚгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶиӘІйЎҢгҒҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®иӘІйЎҢгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжҘӯз•ҢжЁҷжә–гҒ®ж•ҙеӮҷгӮ’иЎҢгҒҶеӣЈдҪ“гҒ§гҒӮгӮӢASAMпјҲAssociation for Standardisation of Automation and Measuring SystemsпјүгҒҢSOVDгҒ®жЁҷжә–еҢ–гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгӮ’з«ӢгҒЎдёҠгҒ’гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮASAMгҒҜгҖҒи»ҠдёЎгҒ®иЁәж–ӯгғ»и©ҰйЁ“гғ»жӨңиЁјгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжЁҷжә–зҡ„гҒӘд»•ж§ҳгӮ’зӯ–е®ҡгҒ—гҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒ«жҷ®еҸҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиҮӘеӢ•и»ҠгғЎгғјгӮ«гғјгӮ„гӮөгғ—гғ©гӮӨгғӨгғјй–“гҒ®иЈҪе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®дә’жҸӣжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгҒӨгҒӨгҖҒиЁәж–ӯгҒ®й«ҳеәҰеҢ–гҒЁеҠ№зҺҮеҢ–гӮ’дҝғйҖІгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеӣЈдҪ“гҒ§гҒҷгҖӮSOVDпјҲService Oriented Vehicle DiagnosticsпјүгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҗҚгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠи»ҠдёЎиЁәж–ӯгӮ’гҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰжҚүгҒҲзӣҙгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®жЁҷжә–гҒ§гҒҷгҖӮеҫ“жқҘгҒ®иЁәж–ӯгҒ§гҒҜгҖҒиЁәж–ӯгғҶгӮ№гӮҝгғјгҒЁеҗ„ECUгҒҢзӣҙжҺҘеҜҫи©ұгҒ—гҖҒUDSпјҲISO 14229пјүгҒӘгҒ©гҒ®гғ—гғӯгғҲгӮігғ«гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰECUеҚҳдҪҚгҒ§DTCгӮ’иӘӯгҒҝеҮәгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒиЁҲжё¬еҖӨгӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгӮ’жӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰSOVDгҒҜгҖҒи»ҠдёЎеҶ…гҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢиЁәж–ӯж©ҹиғҪгӮ„зҠ¶ж…Ӣжғ…е ұгӮ’гҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№зҫӨгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰжҠҪиұЎеҢ–гҒ—гҖҒгҒқгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰе·Ҙе ҙгҒ®иЁәж–ӯж©ҹеҷЁгҖҒгӮҜгғ©гӮҰгғүдёҠгҒ®гғҗгғғгӮҜгӮЁгғігғүгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҒHPCдёҠгҒ§еӢ•дҪңгҒҷгӮӢи»ҠеҶ…гӮўгғ—гғӘгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгӮҜгғ©гӮӨгӮўгғігғҲгҒҢе…ұйҖҡгҒ®гӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғјгӮ№гҒЁгғҮгғјгӮҝгғўгғҮгғ«гҒ§гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮиЁҖгҒ„жҸӣгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒи»ҠдёЎе…ЁдҪ“гӮ’гҖҢиЁәж–ӯгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҖҚгҒЁиҰӢгҒӘгҒ—гҖҒгҒқгҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгӮ’зөұдёҖгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®APIд»•ж§ҳгҒҢSOVDгҒ§гҒҷгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒASAMгҒ§зӯ–е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹSOVDгҒ®еҶ…е®№гҒҜгҖҒзҸҫеңЁISO 17978гӮ·гғӘгғјгӮәгҒЁгҒ—гҒҰеӣҪйҡӣжЁҷжә–еҢ–гӮӮйҖІгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®дёҖйғЁгҒҜгҖҢISO/DIS 17978-3гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰAPIд»•ж§ҳгҒҢгғүгғ©гғ•гғҲе…¬й–ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒңSOVDгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒӢ
SOVDгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж №жң¬зҡ„гҒӘзҗҶз”ұгҒҜгҖҒгҖҢSDVгҒЁгҒ„гҒҶгӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҖҚгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢHPCдёӯеҝғгғ»гӮҫгғјгғіеһӢгӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгҒёгҒ®гӮ·гғ•гғҲгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҫ“жқҘгҒҜгҖҒиЁәж–ӯгғҶгӮ№гӮҝгғјгҒҢUDSгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰECUгҒ”гҒЁгҒ«зӣҙжҺҘгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҷгӮӢж§ӢжҲҗгҒҢеүҚжҸҗгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮзҸҫеңЁгӮӮгҒ“гҒ®ж–№ејҸгҒҜеәғгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гӮұгғјгӮ№гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰе•ҸйЎҢгҒӘгҒҸж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒHPCгҒҢгғҸгғ–гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰж©ҹиғҪгӮ’йӣҶзҙ„гҒ—гҖҒEthernetгғҷгғјгӮ№гҒ®гғҗгғғгӮҜгғңгғјгғідёҠгҒ§гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢеӨҡж•°еӢ•дҪңгҒҷгӮӢж§ӢжҲҗгҒ«з§»иЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸдёӯгҒ§гҖҒгҖҢECUеҚҳдҪҚгҒ®иЁәж–ӯгҖҚгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҹгӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгҒ гҒ‘гҒ§д»ҠеҫҢгӮӮгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ е…ЁдҪ“гҒ®зҠ¶ж…ӢжҠҠжҸЎгӮ„гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгғ©гӮӨгғ•гӮөгӮӨгӮҜгғ«з®ЎзҗҶгҒ«еҜҫеҝңгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒйҒӢз”ЁжҖ§гӮ„гӮ№гӮұгғјгғ©гғ“гғӘгғҶгӮЈгҒ®йқўгҒӢгӮүжҮёеҝөгҒҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ©гҒ®и»ҠдёЎгҒ«гҖҒгҒ©гҒ®HPCж§ӢжҲҗгҒЁгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгғҗгғјгӮёгғ§гғігҒҢијүгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒ©гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҫқеӯҳй–ўдҝӮгҒ§еӢ•дҪңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҒӘгҒ©гҒ®жғ…е ұгӮ’гҖҒиҝ‘жҺҘиЁәж–ӯгғ»йҒ йҡ”иЁәж–ӯгғ»и»ҠеҶ…иЁәж–ӯгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгӮүгҒ§гӮӮдёҖиІ«гҒ—гҒҹеҪўгҒ§жүұгҒҲгӮӢжһ зө„гҒҝгҒҢд»ҠеҫҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢзҸҫеңЁгҒ®е•ҸйЎҢж„ҸиӯҳгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒгӮЁгӮігӮ·гӮ№гғҶгғ е…ЁдҪ“гҒ®еҠ№зҺҮжҖ§гҒ§гҒҷгҖӮзҸҫзҠ¶гҒ§гҒҜгҖҒOEMгҒ”гҒЁгҒ«иЁәж–ӯгӮўгӮҜгӮ»гӮ№ж–№ејҸгӮ„гғҗгғғгӮҜгӮЁгғігғүйҖЈжҗәгҒ®д»•зө„гҒҝгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҖҒиЁәж–ӯгғ„гғјгғ«гғҷгғігғҖгғјгӮ„гӮөгғ—гғ©гӮӨгғӨгғјгҒҜOEMгҒ”гҒЁгҒ«еҲҘгҖ…гҒ®гӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғјгӮ№гҒёеҖӢеҲҘеҜҫеҝңгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮSDVеҢ–гҒ«дјҙгҒ„гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўжӣҙж–°гҒ®й »еәҰгӮ„ж©ҹиғҪиҝҪеҠ гҒ®гғҡгғјгӮ№гҒҢдёҠгҒҢгӮҢгҒ°дёҠгҒҢгӮӢгҒ»гҒ©гҖҒгҒ“гҒ®гҖҢOEMгҒ”гҒЁгҒ®гҒ°гӮүгҒӨгҒҚгҖҚгҒҜгҒқгҒ®гҒҫгҒҫй–Ӣзҷәгғ»йҒӢз”ЁгӮігӮ№гғҲгӮ„гғӘгғӘгғјгӮ№гӮ№гғ”гғјгғүгҒ®гғӘгӮ№гӮҜиҰҒеӣ гҒЁгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮSOVDгҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзҠ¶жіҒгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒи»ҠдёЎиЁәж–ӯгӮ„гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўжӣҙж–°гҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еӨ–йғЁгӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғјгӮ№гӮ’гӮөгғјгғ“гӮ№жҢҮеҗ‘гҒ§е…ұйҖҡеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮи»ҠдёЎеҶ…йғЁгҒ§гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈпјҲAUTOSARгғҷгғјгӮ№гҒӢзӢ¬иҮӘOSгҒӢгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮҫгғјгғіж§ӢжҲҗгҒӢпјүгӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҒӢгҒҜеҗ„зӨҫгҒ®иЈҒйҮҸгҒ«е§”гҒӯгҒӨгҒӨгҖҒHPCгӮ„гӮІгғјгғҲгӮҰгӮ§гӮӨгҒ«SOVDгӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғјгӮ№гӮ’е®ҹиЈ…гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе·Ҙе ҙгҒ®гғҶгӮ№гӮҝгғјгҖҒгғ•гғӘгғјгғҲз®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҒгӮҜгғ©гӮҰгғүгӮўгғ—гғӘгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҖҒи»ҠеҶ…гӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиӨҮж•°гҒ®гӮҜгғ©гӮӨгӮўгғігғҲгҒҢеҗҢгҒҳгғ«гғјгғ«гҒ§и»ҠдёЎгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢSOVDгҒ®зӣ®зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒSDVжҷӮд»ЈгҒ«жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢй«ҳй »еәҰгҒ®гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўжӣҙж–°гӮ„й«ҳеәҰгҒӘйҒ йҡ”гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’гҖҒгӮҲгӮҠгӮ№гӮұгғјгғ©гғ–гғ«гҒӢгҒӨжҢҒз¶ҡеҸҜиғҪгҒӘеҪўгҒ§ж”ҜгҒҲгӮӢеҹәзӣӨгҒ«гҒӘгӮҠеҫ—гӮӢиЁәж–ӯиҰҸж јгҖҒгҒқгӮҢгҒҢSOVDгҒ«жңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҪ№еүІгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
еҫ“жқҘгҒ®иЁәж–ӯж–№ејҸгҒЁSOVDгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„
гҒ“гҒ“гҒҫгҒ§иҰӢгҒҰгҒҚгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒSOVDгҒҜгҖҢгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸж–°гҒ—гҒ„иЁәж–ӯгҖҚгӮ’гӮјгғӯгҒӢгӮүзҷәжҳҺгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚж—ўеӯҳгҒ®иЁәж–ӯеҹәзӣӨгӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«гӮөгғјгғ“гӮ№жҢҮеҗ‘гҒ®е…ұйҖҡгӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғјгӮ№гӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҷәжғігҒ«иҝ‘гҒ„жЁҷжә–гҒ§гҒҷгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒеҫ“жқҘгҒ®иЁәж–ӯж–№ејҸгҒЁжҜ”гҒ№гӮӢгҒЁгҖҒеүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгӮ„гҖҒгҒ©гҒ“гӮ’иЁәж–ӯгҒ®еҚҳдҪҚгҒЁгҒҝгҒӘгҒҷгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒ«гҒҜгҖҒжҳҺзўәгҒӘйҒ•гҒ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҫ“жқҘгҒ®иЁәж–ӯж–№ејҸгҒҜгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҖҢECUеҚҳдҪҚгҒ®иЁәж–ӯгҖҚгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеӨҡгҒҸгҒ®ECUгҒҢCANгғҗгӮ№дёҠгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиЁәж–ӯгғҶгӮ№гӮҝгғјгҒҜUDSгҒӘгҒ©гҒ®гғ—гғӯгғҲгӮігғ«гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰеҖӢгҖ…гҒ®ECUгҒ«зӣҙжҺҘгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮDTCгҒ®иӘӯгҒҝеҮәгҒ—гӮ„гғ©гӮӨгғ–гғҮгғјгӮҝгҒ®еҸ–еҫ—гҖҒгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўжӣёгҒҚжҸӣгҒҲгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж“ҚдҪңгҒҜгҖҒгғҶгӮ№гӮҝгғјгҒЁгӮҝгғјгӮІгғғгғҲECUгҒЁгҒ®й–“гҒ®гӮ„гӮҠеҸ–гӮҠгҒЁгҒ—гҒҰе®ҢзөҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒҜгӮ·гғігғ—гғ«гҒ§еҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒд»Ҡж—ҘгҒ§гӮӮе№…еәғгҒҸеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиЁәж–ӯгҒ®иҰ–зӮ№гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮгҖҢгҒ©гҒ®ECUгҒ«гҒ©гӮ“гҒӘж•…йҡңгӮігғјгғүгҒҢеҮәгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҚгҖҢгҒ©гҒ®йҖҡдҝЎгғ©гӮӨгғігҒ«з•°еёёгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮігғігғқгғјгғҚгғігғҲгғ¬гғҷгғ«гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰSOVDж–№ејҸгҒ§гҒҜгҖҒиЁәж–ӯгҒ®еҚҳдҪҚгҒҢECUгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒи»ҠдёЎгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ дёҠгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„гғӘгӮҪгғјгӮ№гҒёгҒЁеј•гҒҚдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮHPCгӮ„гӮҫгғјгғіECUгҒҢйӣҶзҙ„гҒ—гҒҹжғ…е ұгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«гҖҒгҖҢгҒ“гҒ®и»ҠдёЎгҒ«гҒҜгҒ©гҒ®ж©ҹиғҪзҫӨгғ»гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгғҗгғјгӮёгғ§гғігҒҢијүгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒд»ҠгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶзҠ¶ж…ӢгҒ§еӢ•дҪңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҰ–зӮ№гҒ§иЁәж–ӯгғӘгӮҪгғјгӮ№гӮ’гғўгғҮгғ«еҢ–гҒ—гҖҒгҒқгҒ®гғӘгӮҪгғјгӮ№гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиҝ‘жҺҘиЁәж–ӯгғ»йҒ йҡ”иЁәж–ӯгғ»и»ҠеҶ…иЁәж–ӯгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгӮүгӮӮеҗҢгҒҳSOVDгӮӨгғігӮҝгғјгғ•гӮ§гғјгӮ№гҒ§гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒSOVDгҒ§гҒҜECUгҒ®еҗ‘гҒ“гҒҶеҒҙгҒ«гҒӮгӮӢвҖңж©ҹиғҪгғ»гӮөгғјгғ“гӮ№вҖқгӮ’иЁәж–ӯгҒ®е…ҘеҸЈгҒЁгҒ—гҒҰжүұгҒҶгҒ“гҒЁгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒECUй–“гҒ®и©ізҙ°гҒӘгӮ„гӮҠеҸ–гӮҠгӮ„ж—ўеӯҳгҒ®UDSгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒгҒқгҒ®иғҢеҫҢгҒ§гғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ еҒҙгҒҢеҗёеҸҺгҒҷгӮӢгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜгҖҒгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гғ‘гӮ№гҒ®дёҖиІ«жҖ§гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҫ“жқҘж–№ејҸгҒ§гҒҜгҖҒе·Ҙе ҙгҒ§гҒ®иҝ‘жҺҘиЁәж–ӯгҒЁгҖҒгғҶгғ¬гғһгғҶгӮЈгӮҜгӮ№зөҢз”ұгҒ®йҒ йҡ”иЁәж–ӯгҖҒи»ҠеҶ…гҒ§гҒ®иҮӘе·ұиЁәж–ӯгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢеҲҘгҖ…гҒ®д»•зө„гҒҝгҒЁгҒ—гҒҰе®ҹиЈ…гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮеҗҢгҒҳжғ…е ұгҒ«еҲ°йҒ”гҒҷгӮӢгҒ«гӮӮгҖҒзөҢи·ҜгҒ”гҒЁгҒ«еҲҘгҒ®APIгӮ„гғҮгғјгӮҝеҪўејҸгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҖҒOEMгҒ”гҒЁгҒ®е·®гӮӮеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮҠгҒҢгҒЎгҒ§гҒҷгҖӮSOVDгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгӮ’гҖҢз•°гҒӘгӮӢзөҢи·ҜгҒӢгӮүгҖҒеҗҢгҒҳиЁәж–ӯгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҪўгҒ«жҸғгҒҲгӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮе·Ҙе ҙгҒ®гғҶгӮ№гӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮҢгҖҒгғ•гғӘгғјгғҲз®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒӮгӮҢгҖҒи»ҠеҶ…гӮЁгғјгӮёгӮ§гғігғҲгҒ§гҒӮгӮҢгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜеҗҢгҒҳSOVDгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№е®ҡзҫ©гҒ«гӮӮгҒЁгҒҘгҒ„гҒҰиЁәж–ӯгғӘгӮҪгғјгӮ№гҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе§ҝгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒҢгҖҒеҫ“жқҘж–№ејҸгҒЁгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒSOVDгҒҜж—ўеӯҳгҒ®UDS/DoIPгғҷгғјгӮ№гҒ®иЁәж–ӯгӮ’еҗҰе®ҡгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢECUдёӯеҝғгҒ®иЁәж–ӯгҖҚгҒӢгӮүгҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№пјҸгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ дёӯеҝғгҒ®иЁәж–ӯгҖҚгҒёиҰ–зӮ№гӮ’жӢЎејөгҒ—гҖҒгӮўгӮҜгӮ»гӮ№зөҢи·ҜгӮ’зөұдёҖгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жһ зө„гҒҝгҒЁгҒ—гҒҰдҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮзҸҫжҷӮзӮ№гҒ§SOVDгҒҢжҘӯз•Ңе…ЁдҪ“гҒ«е®Ңе…ЁгҒ«жҷ®еҸҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒHPCгӮ„гӮҫгғјгғігӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҹж¬Ўдё–д»Ји»ҠдёЎгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒҶгҒҲгҒ§гҖҒеҫ“жқҘж–№ејҸгҒЁгҒ®гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹж§ӢйҖ зҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒд»ҠеҫҢгҒ®иЁәж–ӯиЁӯиЁҲгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢйҡӣгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘеүҚжҸҗгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
SOVDгӮ’гҒ©гҒҶдҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гӮӢгҒ№гҒҚгҒӢ
д»ҠеҫҢгӮӮгҖҒи»ҠдёЎеҒҙгҒ®E/EгӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгҖҒгӮҜгғ©гӮҰгғүгӮ„гғҗгғғгӮҜгӮЁгғігғүгҒ®ж§ӢжҲҗгҖҒгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈиҰҒ件гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜиҰҸеҲ¶еӢ•еҗ‘гҒӘгҒ©гҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒж–°гҒ—гҒ„жЁҷжә–гӮ„гғ•гғ¬гғјгғ гғҜгғјгӮҜгҖҒгғҷгғігғҖгғјзӢ¬иҮӘгҒ®гӮҪгғӘгғҘгғјгӮ·гғ§гғігҒҢж¬ЎгҖ…гҒЁзҷ»е ҙгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдәҲжғігҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§йҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгҖҢгҒ©гҒ®жҠҖиЎ“гҒҢгғҲгғ¬гғігғүгҒӢгҖҚгӮ’иҝҪгҒ„гҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮҲгӮҠгӮӮгҖҒиҮӘзӨҫгҒ®и»ҠдёЎгӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№жҲҰз•ҘгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒ®дёӯгҒ§гҖҒSOVDгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжЁҷжә–гӮ’гҒ©гҒҶдҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гӮӢгҒӢгӮ’еҶ·йқҷгҒ«ж•ҙзҗҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮSOVDгҒҜгҖҒгҒқгӮҢиҮӘдҪ“гҒҢзӣ®зҡ„гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒSDVжҷӮд»ЈгҒ®иЁәж–ӯгӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒҶгҒҲгҒ§гҒ®гҖҢе…ұйҖҡиЁҖиӘһгҖҚгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮжң¬иЁҳдәӢгӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҖҒиҮӘзӨҫгҒ®иЈҪе“ҒгӮ„гғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒЁгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йҖЈжҗәгҒ—еҫ—гӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгҒ©гҒ®гғ¬гӮӨгғӨгғјгҒ§жҙ»з”ЁгҒҷгҒ№гҒҚгҒӢгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢе…ҘгӮҠеҸЈгҒЁгҒ—гҒҰSOVDгӮ’жҚүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ