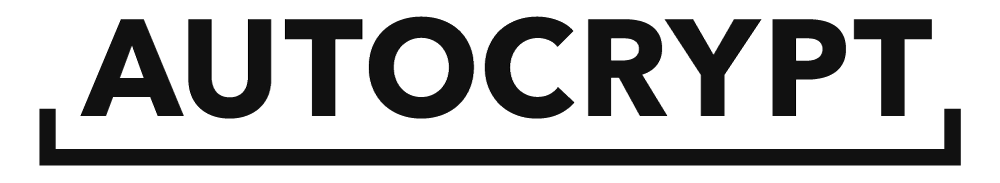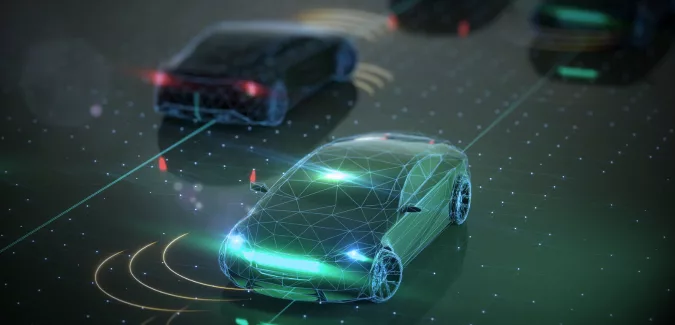śó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼ʄɼ„ɨ„Éô„Éę4ŚģüŤ®ľ„Ā®śäÄŤ°ďŚčēŚźĎ„Āĺ„Ā®„āĀ | 2025ŚĻīÁČą

„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éą„ÄĀ„āĮ„É©„ā¶„ÉČŚüļÁõ§„ĀģŤá™ŚčēŤĽäŚźĎ„ĀĎ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥„ĀĆAWS„Éē„ā°„É≥„Éá„Éľ„ā∑„Éß„Éä„Éę„ÉÜ„āĮ„Éč„āę„Éę„ɨ„Éď„É•„ÉľŚĮ©śüĽ„āíťÄöťĀé
2025ŚĻī8śúą20śó•![[JP] ŚģüŤ®ľ„Āč„āČŚģüŤ£Ö„Āł„ÄĀśó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēťĀčŤĽĘ „ā§„É°„Éľ„āł](https://www.autocrypt.jp/wp-content/uploads/2025/09/JP-ŚģüŤ®ľ„Āč„āČŚģüŤ£Ö„Āł„ÄĀśó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼Ę-„ā§„É°„Éľ„āł-80x80.webp)
„Äź„ɨ„ÉĚ„Éľ„Éą„ÄĎŚģüŤ®ľ„Āč„āČŚģüŤ£Ö„Āł„ÄĀśó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼Ę
2025ŚĻī9śúą26śó•
Ťá™ŚčēťĀ荼ʄĀģśú™śĚ•„ĀĆ„Ā§„ĀĄ„Āęśó•śú¨„ĀģŤ∑Įšłä„ĀßÁŹĺŚģü„Āģ„āā„Āģ„Ā®„Ā™„āä„Ā§„Ā§„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā2025ŚĻī„ĀĮ„ɨ„Éô„Éę4„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼ʄɟ„āĻ„ĀĆ„Āô„Āß„ĀęŚÖ¨ťĀď„āíŤĶį„āäŚßč„āĀ„ÄĀśĶ∑Ś§Ė„Āč„āČ„ĀĮŚÖąťÄ≤ÁöĄ„Ā™„É≠„Éú„āŅ„āĮ„ā∑„Éľ„ĀĆ„ÉÜ„āĻ„ÉąŤĶįŤ°Ć„āíťĖčŚßč„Āô„āč„Ā™„Ā©„ÄĀŚ§ö„ĀŹ„Āģšļļ„ĀĆ„ÄĆśú™śĚ•„ĀģšĻó„āäÁČ©„Äć„āíŤāĆ„ĀßśĄü„Āė„āČ„āĆ„āč„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„Ā£„ĀüŤ®ėŚŅĶ„Āô„ĀĻ„ĀćŚĻī„Āß„Āô„Äā„Āď„ĀģśÄ•ťÄü„Ā™Ś§ČŚĆĖ„ĀĮ„ÄĀŚćė„Ā™„āčśäÄŤ°ď„ĀģťÄ≤ś≠©„Ā†„ĀĎ„Āę„āą„Ā£„Ā¶„āā„Āü„āČ„Āē„āĆ„Āü„āŹ„ĀĎ„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äāśó•śú¨śĒŅŚļú„ĀĆ„Āď„āĆ„āíŚõĹŚģ∂śą¶Áē•„Ā®šĹćÁĹģ„Ā•„ĀĎ„ÄĀŚģėśįĎšłÄšĹď„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ÄĆ„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£ťĚ©ŚĎĹ„Äć„āíśé®„ĀóťÄ≤„āĀ„Ā¶„ĀĄ„āčÁĶźśěú„Āß„Āô„ÄāÁČĻ„Āꍼä„ĀĆ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„Āę„āą„Ā£„Ā¶ŚģöÁĺ©„Āē„āĆ„ÄĀ„āĻ„Éě„Éľ„Éą„Éē„ā©„É≥„Āģ„āą„ĀÜ„ĀęťÄ≤ŚĆĖ„ĀóÁ∂ö„ĀĎ„āčSDVÔľąSoftware Defined VehicleԾȄĀĮ„Āď„ĀģťĚ©ŚĎĹ„Āģšł≠ś†ł„āí„Ā™„Āô„ā≥„É≥„āĽ„Éó„Éą„Āß„Āô„Äā
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀ„Āď„ĀģŚ§ß„Āć„Ā™Ś§ČťĚ©śúü„āí„ÄĆśĒŅÁ≠Ė„ÉĽŚģüŤ®ľ„ÉĽśäÄŤ°ď„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ3„Ā§„ĀģŤ¶ĖÁāĻ„Āč„āČŚ§öŤßíÁöĄ„Āꌹܜ쟄Āó„Āĺ„Āô„ÄāśŅÄŚĆĖ„Āô„āč„āį„É≠„Éľ„Éź„ÉęÁę∂šļČ„Āģšł≠„ÄĀśó•śú¨„ĀĮ2030ŚĻī„Āĺ„Āß„ĀęSDVŚłāŚ†ī„Āß30%„Āģ„ā∑„āß„āĘÁć≤Śĺó„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁõģś®ô„āíśé≤„Āí„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āē„Āę„ÄĆÁ§ĺšľöŚģüŤ£ÖŚÖÉŚĻī„Äć„Ā®ŚĎľ„Ā∂„Āę„ĀĶ„Āē„āŹ„Āó„ĀĄ2025ŚĻī„ÄĀśó•śú¨„ĀĆ„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Āęśú™śĚ•„Āģ„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£„ā팹á„āäśčď„ĀĄ„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āģ„Āč„ÄĀ„ĀĚ„ĀģÁŹĺŚú®Śúį„Ā®šĽäŚĺĆ„ĀģŚĪēśúõ„ā퍩≥„Āó„ĀŹŤ¶č„Ā¶„ĀĄ„Āć„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„Äā
śó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼ʄĀģś¶āś≥Ā
„ɨ„Éô„Éę4„ĀģÁ§ĺšľöŚģüŤ£Ö„Āł
śó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼ʜäÄŤ°ď„ĀĮSAEÔľąÁĪ≥ŚõōᙌčēŤĽäśäÄŤ°ďšľöԾȄĀĆŚģö„āĀ„āčŚõĹťöõŚüļśļĖ„Āģ„ɨ„Éô„Éę0„Āč„āČ5„ĀģŚąÜť°ě„Āęś≤Ņ„Ā£„Ā¶ÁĚÄŚģü„ĀęťĖčÁôļ„ĀĆťÄ≤„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻŚģö„ĀģśĚ°šĽ∂šłč„Āß„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀĆťĀ荼ʄāíśčÖ„Ā܄ɨ„Éô„Éę3„ĀĮ„Āô„Āß„ĀꌳāŤ≤©ŤĽä„Āę„āāśź≠ŤľČ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„ĀģŚÖąťßÜ„ĀĎ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Āģ„ĀĆ„Éõ„É≥„ÉÄ„ĀĆ2021ŚĻī3śúą„ĀęÁôļŤ°®„Āó„Āü„ÄƄɨ„āł„āß„É≥„ÉČÔľąLEGENDԾȄÄć„Āß„Āô„Äā„Āď„Āģ„ÉĘ„Éá„Éę„Āę„ĀĮšłĖÁēĆ„ĀߌąĚ„āĀ„Ā¶Ť™ćŚŹĮ„Āē„āĆ„Āü„ɨ„Éô„Éę3śäÄŤ°ď„ÄĆHonda SENSING Elite„Äć„ĀĆśź≠ŤľČ„Āē„āĆ„ÄĀDMP„ĀģHD„Éě„ÉÉ„Éó„āíśīĽÁĒ®„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀßťęėťÄüťĀďŤ∑Į„Āß„Āģ„ÉŹ„É≥„āļ„ā™„ÉēŤĶįŤ°Ć„ā팏ĮŤÉĹ„Āę„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„ĀĚ„Āó„Ā¶ÁŹĺŚú®„ÄĀśó•śú¨„ĀģśĆĎśą¶„ĀĮÁČĻŚģö„Āģ„ā®„É™„āĘŚÜÖ„ĀßťĀ荼ʜČč„ĀĆšłćŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āč„ɨ„Éô„Éę4„ĀģÁ§ĺšľöŚģüŤ£Ö„Āł„Ā®ŚźĎ„Āč„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„ĀģŤĪ°ŚĺīÁöĄ„Ā™šļčšĺč„ĀĆÁ¶ŹšļēÁúĆśįłŚĻ≥ŚĮļÁĒļ„Āß2023ŚĻī5śúą„Āč„āČťĀ荰ƄĀó„Ā¶„ĀĄ„āčŚõĹŚÜÖŚąĚ„Āģ„ɨ„Éô„Éę4Ťá™ŚčēťĀ荼ʄāĶ„Éľ„Éď„āĻ„Āß„Āô„Äā„Āē„āČ„Āę2025ŚĻī2śúą„Āę„ĀĮŤĆ®ŚüéÁúĆ„Ā≤„Āü„Ā°Śłā„Āßšł≠Śěč„Éź„āĻ„Āę„āą„āč„ɨ„Éô„Éę4„ĀģŚĖ∂ś•≠ťĀ荰ƄĀĆ„āĻ„āŅ„Éľ„Éą„Āó„ÄĀÁīĄ6.1km„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚõĹŚÜÖśúÄťē∑„Āģ„Éę„Éľ„Éą„ĀߌģüÁĒ®ŚĆĖ„āíśěú„Āü„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„Āď„āĆ„āČ„ĀģśąźŚäüšļčšĺč„āíŤ∂≥„ĀĆ„Āč„āä„ĀęśĒŅŚļú„ĀĮ2025ŚĻīŚļ¶„Āĺ„Āß„ĀęŚÖ®ŚõĹ50„āęśČÄ„ÄĀ2027ŚĻīŚļ¶„Āĺ„Āß„Āę„ĀĮ100„āęśČÄšĽ•šłä„ĀߌźĆśßė„Āģ„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„āíŚĪēťĖč„Āô„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁõģś®ô„āíśé≤„Āí„Ā¶„Āä„āä„ÄĀśó•śú¨ŚźĄŚúį„ĀߍᙌčēťĀ荼ʄĀĆśó•Śłł„ĀģťĘ®śôĮ„Āę„Ā™„āčśó•„āā„ĀĚ„ĀÜťĀ†„ĀŹ„Ā™„ĀĄ„Āč„āā„Āó„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Äā
ŚõĹŚģ∂śą¶Áē•„Ā®„ĀĚ„āĆ„āíśĒĮ„Āą„āčś≥ēŚą∂Śļ¶
śó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼ʝĖčÁôļ„ĀĮŚÄč„ÄÖ„ĀģšľĀś•≠„ĀģŚä™Śäõ„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀśĒŅŚļú„Āę„āą„ā茾∑Śäõ„Ā™„É™„Éľ„ÉÄ„Éľ„ā∑„ÉÉ„Éó„ĀęśĒĮ„Āą„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āģšł≠ś†ł„āí„Ā™„Āô„Āģ„ĀĆ2024ŚĻī5śúąÁĶĆśłąÁĒ£ś•≠ÁúĀ„Ā®ŚõĹŚúüšļ§ťÄöÁúĀ„ĀĆŚÖĪŚźĆ„ĀßÁ≠ĖŚģö„Āó„Āü„ÄĆ„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£DXśą¶Áē•„Äć„Āß„Āô„Äā„Āď„Āģśą¶Áē•„ĀĮSDV„Āģ„āį„É≠„Éľ„Éź„ÉęŤ≤©Ś£≤ŚŹįśēį„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ÄĆśó•Á≥Ľ„ā∑„āß„āĘ3ŚČ≤„Äć„ĀģŚģüÁŹĺ„Ā®„ĀĄ„ĀÜťáéŚŅÉÁöĄ„Ā™Áõģś®ô„āíśé≤„Āí„ÄĀ‚φŚćĒŤ™Ņť†ėŚüü„Āß„ĀģťĖčÁôļŚä†ťÄü‚Ď°„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘšł≠ŚŅÉ„ĀģÁĒ£ś•≠śßčťÄ†„Āł„ĀģŤĽĘśŹõ‚ĎĘŚćäŚįéšĹďšĺõÁĶ¶Á∂≤„Ā™„Ā©„ĀģÁĶĆśłąŚģČŚÖ®šŅĚťöúŚľ∑ŚĆĖ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ3„Ā§„ĀģśüĪ„āíśėéÁĘļ„ĀęÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
‚Ė† Á§ĺšľöŚģüŤ£Ö„ā팏ĮŤÉĹ„Āę„Āô„āčś≥ēśēīŚāô
„Āď„ĀģŚõĹŚģ∂śą¶Áē•„āíŚģüÁŹĺ„Āô„āč„Āü„āĀ„ÄĀŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™ś≥ēŚą∂Śļ¶„ĀģśēīŚāô„āāŚźĆśôā„ĀęťÄ≤„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āö2023ŚĻī4śúą„ĀęśĖĹŤ°Ć„Āē„āĆ„ĀüśĒĻś≠£ťĀďŤ∑Įšļ§ťÄöś≥ē„ĀĮ„ɨ„Éô„Éę4Ťá™ŚčēťĀ荼ʄĀģŚÖ¨ťĀďŤĶįŤ°Ć„āíś≠£ŚľŹ„Ā™„ÄĆŤ®ĪŚŹĮŚą∂Śļ¶„Äć„Ā®„Āó„Ā¶ŚČĶŤ®≠„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āäšļčś•≠ŤÄÖ„ĀĮśėéÁĘļ„Ā™ś≥ēÁöĄś†Ļśč†„Āģ„āā„Ā®„ÄĀŤá™ŚčēťĀ荼ʄāĶ„Éľ„Éď„āĻ„āíšļčś•≠„Ā®„Āó„Ā¶ŚĪēťĖč„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā
‚Ė† SDVśôāšĽ£„ĀģśĖį„Āü„Ā™ŚģČŚÖ®ŚüļśļĖÔľö„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť¶ŹŚą∂
„Āē„āČ„Āę„ÄĀŤĽäšł°„ĀģSDVŚĆĖ„ĀĮOTA„Āę„āą„ā茹©šĺŅśÄß„ĀģŚźĎšłä„Ā®ŚźĆśôā„Āę„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„Āģ„É™„āĻ„āĮ„Ā®„ĀĄ„ĀÜśĖį„Āü„Ā™Ť™≤ť°Ć„āíÁĒü„ĀŅŚáļ„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āď„āĆ„ĀęŚĮĺŚŅú„Āô„āč„Āü„āĀ„ÄĀśó•śú¨„ĀĮŚõĹťÄ£„ĀģŚõĹťöõŚüļśļĖ„Āß„Āā„āčUN-R155Ôľą„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ÔľČ„Āä„āą„Ā≥UN-R156Ôľą„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„ɹԾȄāíŚõĹŚÜÖś≥ē„ĀęŤŅÖťÄü„ĀęŚįéŚÖ•„ÄāŤá™ŚčēŤĽä„É°„Éľ„āę„Éľ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶ŤĽäšł°„ĀģŤ®≠Ť®ą„Āč„āČŚĽÉś£Ą„Āĺ„Āß„Āģ„É©„ā§„Éē„āĶ„ā§„āĮ„ÉęŚÖ®šĹď„āíťÄö„Āė„Āü„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Áģ°ÁźÜšĹ∂ÔľąCSMS/SUMSԾȄĀģśßčÁĮČ„āíÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„ÄĀ„Éá„āł„āŅ„ÉęśôāšĽ£„ĀģśĖį„Āü„Ā™ŚģČŚÖ®ŚüļśļĖ„āíÁĘļÁęč„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā
‚Ė† śĆĎśą¶„āíŚĺĆśäľ„Āó„Āô„āčśĒĮśŹīÁ≠Ė
„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüŚą∂Śļ¶Ť®≠Ť®ą„Ā®šł¶Ť°Ć„Āó„ÄĀśĒŅŚļú„ĀĮ„ÄĆRoAD to the L4„Äć„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ŚõĹÁ≠Ėšļčś•≠„āíťÄö„Āė„Ā¶ŚÖąťÄ≤šļčšĺč„ĀģŚČĶŚáļ„āí„É™„Éľ„ÉČ„Āô„āč„ĀĽ„Āč„ÄĀŚúįśĖĻŚČĶÁĒüśé®ťÄ≤šļ§šĽėťáĎ„āĄ„Éá„āł„āŅ„Éę„ā§„É≥„Éē„É©śēīŚāôŚüļťáĎ„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚ§öśßė„Ā™śĒĮśŹīÁ≠Ė„āíŚĪē„Āó„ÄĀŤ¶ŹŚą∂„Ā®śĒĮśŹī„Āģšł°Ťľ™„ĀßÁ§ĺšľöŚģüŤ£Ö„ā팾∑Śäõ„Āęśé®ťÄ≤„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ŚģüŤ®ľ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Ā®Á§ĺšľöŚģüŤ£Ö
ŚõĹ„Āģśą¶Áē•„āĄś≥ēśēīŚāô„ĀĆśēī„ĀÜšł≠„ÄĀÁ§ĺšľöŚģüŤ£Ö„ĀģŚčē„Āć„āāŚÖ®ŚõĹŚźĄŚúį„ĀßśīĽÁôļŚĆĖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀšļ§ťÄöŤ™≤ť°Ć„āíśäĪ„Āą„āčŚúįśĖĻ„Āß„ĀģŚÖąŤ°Ćšļčšĺč„Āč„āČ„ÄĀÁČ©śĶĀ„ĀģŚäĻÁéáŚĆĖ„āíÁõģśĆá„ĀôŚ§ßŤ¶Źś®°„Ā™ŚģüŤ®ľ„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶„ĀĚ„āĆ„āČ„āíśĒĮ„Āą„āčŚüļÁõ§śäÄŤ°ď„ĀģťĖčÁôļ„Āĺ„Āߌ§öŚ≤ź„Āę„āŹ„Āü„āč„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀĆŚźĆśôāšł¶Ť°Ć„ĀßťÄ≤„āď„Āß„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ŚúįśĖĻšļ§ťÄö„Āģ„ÉĘ„Éá„Éę„āĪ„Éľ„āĻÔľąÁ¶ŹšļēÁúĆ„ÉĽŤĆ®ŚüéÁúĆÔľČ
Á¶ŹšļēÁúĆśįłŚĻ≥ŚĮļÁĒļ„Āß„ĀĮ„ÄĀ2023ŚĻī5śúą„Āč„āČŚõĹŚÜÖŚąĚ„Ā®„Ā™„āč„ɨ„Éô„Éę4Ťá™ŚčēťĀ荼ʄɟ„āĻ„ĀģŚēÜÁĒ®ťĀ荰ƄāíťĖčŚßč„Āó„Āĺ„Āó„Āü„ÄāťõĽÁ£ĀŤ™ėŚįéÁ∑ö„āíśīĽÁĒ®„Āó„ÄĀŚģČŚģö„Āó„ĀüťĀ荰ƄāíŚģüÁŹĺ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŤĆ®ŚüéÁúĆśó•Áę茳ā„Āß„ĀĮ2025ŚĻī2śúą„Āč„āČ„ÄĀ„āą„ā䌧ߌěč„Āģšł≠Śěč„Éź„āĻ„Āę„āą„āč„ɨ„Éô„Éę4ťĀ荰ƄĀĆBRTŤ∑ĮÁ∑ö„ĀߌģüÁĒ®ŚĆĖ„Āē„āĆ„ÄĀŚúįŚüüšļ§ťÄö„ĀģśĖį„Āü„Ā™ŚŹĮŤÉĹśÄß„āíÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ÁČ©śĶĀ„ÉĽťÉĹŚłāťÉ®„Āß„ĀģśĆĎśą¶ÔľąśĖįśĚĪŚźćťęėťÄü„ÉĽśĄõÁü•ÁúĆÔľČ
śĖįśĚĪŚźćťęėťÄüťĀďŤ∑Į„ĀģšłÄťÉ®ŚĆļťĖď„Āß„ĀĮ„ÄĀ„Éą„É©„ÉÉ„āĮ„Āģ„ÉČ„É©„ā§„Éź„ÉľšłćŤ∂≥Ťß£ś∂ą„āíÁõģśĆá„Āó„Ā¶ŚĺĆÁ∂öŤĽäÁĄ°šļļ„Āģťö䌹óŤĶįŤ°ĆÔľą„ɨ„Éô„Éę4ÁõłŚĹďԾȄĀꌟτĀĎ„ĀüŚ§ßŤ¶Źś®°„Ā™ŚģüŤ®ľ„ĀĆťÄ≤„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšłÄśĖĻ„ÄĀśĄõÁü•ÁúĆ„Āß„ĀĮŚźćŚŹ§ŚĪ茳ā„ĀģťÉĹŚŅɝɮ„āĄšł≠ťÉ®ŚõĹťöõÁ©ļśłĮŚĎ®Ťĺļ„ÄĀŚ§öśēį„Āģś≠©Ť°ĆŤÄÖ„ĀĆŤ°Ć„Āćšļ§„ĀÜŚÖ¨ŚúíÔľą„ÉĘ„É™„ā≥„É≠„ÉĎ„Éľ„āĮԾȄĀ™„Ā©ÁČĻśÄß„ĀģÁēį„Ā™„ā茧öśßė„Ā™ÁíįŚĘÉ„Āß„É≠„Éú„āŅ„āĮ„ā∑„Éľ„āĄś≠©ŤĽäŚÖĪŚ≠ė„ĀģśäÄŤ°ďś§úŤ®ľ„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„āą„ā䍧áťõĎ„Ā™ťÉĹŚłāÁíįŚĘÉ„Āł„ĀģťĀ©ÁĒ®„āíÁõģśĆá„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
Ťá™ŚčēťĀ荼ʄĀę„Āä„ĀĎ„āčśäÄŤ°ďŚčēŚźĎ
ÁĒüśąźAI„āíśīĽÁĒ®„Āô„āč„Éá„Éľ„āŅŚá¶ÁźÜśäÄŤ°ď„ĀģťęėŚļ¶ŚĆĖ
ŚĺďśĚ•„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼ʄĀĮšļļťĖď„ĀĆŤ®≠Śģö„Āó„ĀüÁĄ°śēį„Āģ„Éę„Éľ„Éę„ĀęŚĺď„ĀÜ„ÄĆ„Éę„Éľ„Éę„Éô„Éľ„āĻ„ÄćśĖĻŚľŹ„ĀĆšłĽśĶĀ„Āß„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀšļąśúü„Āõ„Ā¨Áä∂ś≥Ā„Āł„ĀģŚĮĺŚŅú„ĀęťôźÁēĆ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āď„ĀģŤ™≤ť°Ć„āíŚÖčśúć„Āô„āč„Āü„āĀ„ÄĀÁŹĺŚú®„ĀĮAI„ĀĆŤÜ®Ś§ß„Ā™ŤĶįŤ°Ć„Éá„Éľ„āŅ„Āč„āČťĀ荼ʜďćšĹú„āíÁõīśé•Ś≠¶ÁŅí„Āô„āč„ÄĆ„Éá„Éľ„āŅťßÜŚčēŚěč„Äć„Āł„Ā®ťĖčÁôļ„ĀģťáćŚŅÉ„ĀĆÁ߼„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„Éą„É®„āŅ„ĀĮNVIDIA„Ā®„ĀģśŹźśźļ„āíťÄö„Āė„Ā¶ŚźĆÁ§ĺ„ĀģAIťĖčÁôļŚüļÁõ§„ÄĆCosmos„Äć„Ā™„Ā©„āíśīĽÁĒ®„Āó„ÄĀŤ§áťõĎ„Ā™„ā∑„Éä„É™„ā™„āíAI„ĀęŚ≠¶ÁŅí„Āē„Āõ„āč„Āď„Ā®„Āß„āą„āäšļļťĖď„ĀęŤŅĎ„ĀĄśüĒŤĽü„Ā™ťĀ荼ʌą§śĖ≠ŤÉĹŚäõ„ĀģŚģüÁŹĺ„āíŚä†ťÄü„Āē„Āõ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
HD„Éě„ÉÉ„Éó„ÉĽ„āĮ„É©„ā¶„ÉČ„Éô„Éľ„āĻ„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼ʜĒĮśŹī
HD„Éě„ÉÉ„ÉóÔľąťęėÁ≤ĺŚļ¶3ś¨°ŚÖÉŚúįŚõ≥ԾȄĀĮŤ™§Ś∑ģśēį„āĽ„É≥„ÉĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜť©öÁēįÁöĄ„Ā™Á≤ĺŚļ¶„ĀßťĀďŤ∑Į„ĀģŚĹĘÁä∂„āĄŤĽäÁ∑ö„ÄĀś®ôŤ≠ė„Ā™„Ā©„ā퍮ėťĆ≤„Āó„Āü„ÄĆťĀďŤ∑Į„Āģ„Éá„āł„āŅ„Éę„ÉĄ„ā§„É≥„Äć„Āß„Āô„Äāśó•śú¨„Āß„ĀĮšłĽŤ¶ĀŤá™ŚčēŤĽä„É°„Éľ„āę„Éľ„Ā™„Ā©„ĀĆŚÖĪŚźĆŚáļŤ≥á„Āó„Āü„ÉÄ„ā§„Éä„Éü„ÉÉ„āĮ„Éě„ÉÉ„Éó„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆԾąDMPԾȄĀĆŚÖ®ŚõĹ„ĀģťęėťÄüťĀďŤ∑Į„ÉĽŤá™ŚčēŤĽäŚįāÁĒ®ťĀďŤ∑ĮÁīĄ32,000km„ĀģśēīŚāô„āíŚģĆšļÜ„Āē„Āõ„ÄĀś®ôśļĖŚĆĖ„Āē„āĆ„Āü„Éá„āł„āŅ„ÉęŚüļÁõ§„āíśßčÁĮČ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŤĶįŤ°Ćšł≠„ÄĀŤĽäšł°„ĀĮHD„Éě„ÉÉ„ÉóśÉÖŚ†Ī„Ā®„āĽ„É≥„āĶ„Éľ„Āߌĺó„Āü„É™„āĘ„Éę„āŅ„ā§„ɆśÉÖŚ†Ī„āíÁÖߌźą„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀßGPS„Ā†„ĀĎ„Āß„ĀĮšłćŚŹĮŤÉĹ„Ā™„āĽ„É≥„ÉĀ„É°„Éľ„Éą„ÉęŚćėšĹć„Āß„Āģś≠£ÁĘļ„Ā™Ťá™Ś∑ĪšĹćÁĹģśé®Śģö„ā팏ĮŤÉĹ„Āę„Āó„Āĺ„Āô„Äā
V2XťÄöšŅ°„ā§„É≥„Éē„É©„Ā®ŚģüŤ®ľÁä∂ś≥Ā
„āĮ„Éę„Éě„ĀĆšļí„ĀĄ„Āę„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ťĀďŤ∑Į„Ā®ťÄöšŅ°„Āô„āčV2XÔľąVehicle to EverythingԾȄĀĮŤĽäŤľČ„āĽ„É≥„āĶ„Éľ„Ā†„ĀĎ„Āß„ĀĮś§úÁü•„Āß„Āć„Ā™„ĀĄś≠ĽŤßí„ĀģŤĽäšł°„āĄŚÖą„Āģšļ§ťÄöÁä∂ś≥Ā„Ā™„Ā©„āíŚÖĪśúČ„Āó„Ā¶ŚģČŚÖ®śÄß„āíť£õŤļćÁöĄ„Āęťęė„āĀ„āčśäÄŤ°ď„Āß„Āô„Äāśó•śú¨„ĀĮšłĖÁēĆ„ĀęŚÖąťßÜ„ĀĎ„Ā¶760MHzŚłĮ„āíITSŚźĎ„ĀĎ„ĀęŚįéŚÖ•„Āó„Āĺ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀÁŹĺŚú®„ĀĮŚõĹťöõś®ôśļĖ„Āß„Āā„āč5.9GHzŚłĮ„Āł„ĀģŚĮĺŚŅú„ĀĆťá捶Ā„Ā™ŚõĹŚģ∂Ť™≤ť°Ć„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„Āä„āä„ÄĀÁ∑ŹŚčôÁúĀšłĽŚįé„Āß2030ŚĻīť†É„ĀģŚģüÁĒ®ŚĆĖ„āíÁõģś®ô„ĀęŚĎ®ś≥Ęśēį„ĀģŚČ≤„āäŚĹď„Ā¶„āíśé®ťÄ≤„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Ā®„āĀ„Ā®šĽäŚĺĆ„ĀģŚĪēśúõ
śó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼ʜą¶Áē•„ĀĮŚģėśįĎšłÄšĹď„ĀģšĹďÁ≥ĽÁöĄ„Ā™„āĘ„Éó„É≠„Éľ„ÉĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚľ∑Śõļ„Ā™ŚüļÁõ§„āíśĆĀ„Ā§šłÄśĖĻ„Āß„ÄĀťĖčÁôļťÄüŚļ¶„Ā®śäēŤ≥፶Źś®°„ĀģťĚĘ„ĀßÁĪ≥ŚõĹ„ÉĽšł≠ŚõĹ„ĀęŚä£ŚĺĆ„Āô„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜśßčťÄ†ÁöĄ„Ā™Ť™≤ť°Ć„ĀęÁõīťĚĘ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„āģ„É£„ÉÉ„Éó„āíŚüč„āĀ„ÄĀ2030ŚĻī„ĀģSDVŚłāŚ†ī„ā∑„āß„āĘ3ŚČ≤„Ā®„ĀĄ„ĀÜťáéŚŅÉÁöĄ„Ā™Áõģś®ô„āíťĀĒśąź„Āô„āčťćĶ„ĀĮ„Āĺ„Āē„Āę„ÄĆ„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£DXśą¶Áē•„Äć„Āę„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äāśú¨śą¶Áē•„ĀĮťęėÁ≤ĺŚļ¶ŚúįŚõ≥„āĄAIťĖčÁôļŚüļÁõ§„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āü„ÄĆŚćĒŤ™Ņť†ėŚüü„Äć„ĀęŚģėśįĎ„Āģ„É™„āĹ„Éľ„āĻ„āíťõÜšł≠„Āē„Āõ„āč„Āď„Ā®„ĀßťĖčÁôļŚäĻÁéá„āíťęė„āĀ„āč„Ā®ŚźĆśôā„Āę„ÄĀV2X„āĄ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚąÜťáé„Āß„ĀģŚõĹťöõś®ôśļĖŚĆĖ„āíšłĽŚįé„Āó„Ā¶śó•śú¨„ĀģśäÄŤ°ďÁöĄŚĄ™šĹćśÄß„āíÁĘļšŅĚ„Āô„āč„Āď„Ā®„āíÁõģśĆá„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā2025ŚĻī„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼ʄĀĆ„ÄĆŚģüŤ®ľ„Äć„Āč„āČ„ÄĆŚģüŤ£Ö„Äć„Āł„Ā®śú¨ś†ľÁöĄ„ĀęÁ߼Ť°Ć„Āô„ā荼ʜŹõÁāĻ„Āß„Āā„āä„ÄĀšĽäŚĺĆťÉĹŚłāťÉ®„Āß„Āģ„É≠„Éú„āŅ„āĮ„ā∑„Éľ„āĄŚĻĻÁ∑öÁČ©śĶĀ„ĀģŤá™ŚčēŚĆĖ„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āü„Éē„É©„ÉÉ„āį„ā∑„ÉÉ„Éó„ÉĽ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„āíśąźŚäü„Āē„Āõ„ÄĀ„ÉŹ„Éľ„ÉČ„ā¶„āß„āĘšł≠ŚŅÉ„Āč„āČ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„ÉĽ„āĶ„Éľ„Éď„āĻšł≠ŚŅÉ„Āł„ĀģŤŅÖťÄü„Ā™ÁĒ£ś•≠śßčťÄ†ŤĽĘśŹõ„āíŚģüÁŹĺ„Āß„Āć„āč„Āč„ĀĆ„ÄĀśó•śú¨„Āģ„āį„É≠„Éľ„Éź„ÉꌳāŚ†ī„Āę„Āä„ĀĎ„āčÁę∂šļČŚäõ„āíŚ∑¶ŚŹ≥„Āô„ā荩¶ťáĎÁü≥„Ā®„Ā™„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
Ťá™ŚčēťĀ荼ʄĀģÁ§ĺšľöŚģüŤ£Ö„Āę„ĀĮŤ®≠Ť®ą„ÄĀś§úŤ®ľ„ÄĀŚģüŤ£Ö„ÄĀťĀčÁĒ®„Āĺ„ĀßšłÄśįóťÄöŤ≤ę„Āߌõě„Āõ„āčšĹ∂„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„ÄāAUTOCRYPT„ĀĮUN R155/R156„ÉĽISO/SAE 21434„ā퍼ł„ĀęCSMS/SUMSśßčÁĮČ„Āč„āČECU„ÉĽHSM„ĀģŚģüŤ£Ö„ÄĀOTA„Ā®ťćĶÁģ°ÁźÜ„ÄĀŚģüŤĽäÔľŹHILÁíįŚĘÉ„Āß„Āģ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ś§úŤ®ľ„ÄĀťĀčÁĒ®Áõ£Ť¶Ė„Āĺ„Āß„āí„āę„Éź„Éľ„Āô„āčśäÄŤ°ď„āíśĆĀ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāśó•śú¨ŚłāŚ†ī„ĀęśúÄťĀ©ŚĆĖ„Āó„Āü„ÉČ„ā≠„É•„É°„É≥„Éą„Ā®„Éó„É≠„āĽ„āĻ„ĀߍᙌčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀģśßčÁĮČ„ÉĽś§úŤ®ľ„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥„ā휏źšĺõ„Āó„Āĺ„Āô„ÄāšľĀś•≠ÁíįŚĘÉ„Āꌟą„āŹ„Āõ„ĀüŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™śŹźś°ą„āāŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„Āģ„Āß„ÄĀ„Āĺ„Āö„ĀĮ„ĀäśįóŤĽĹ„Āę„ĀĒÁõłŤęá„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā