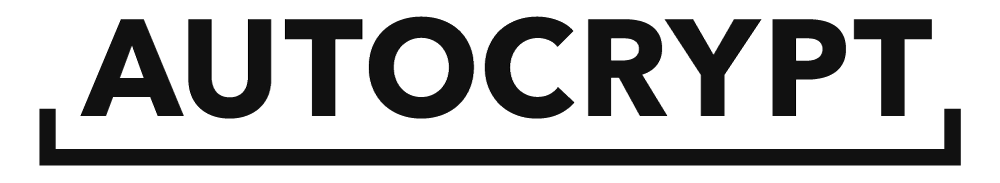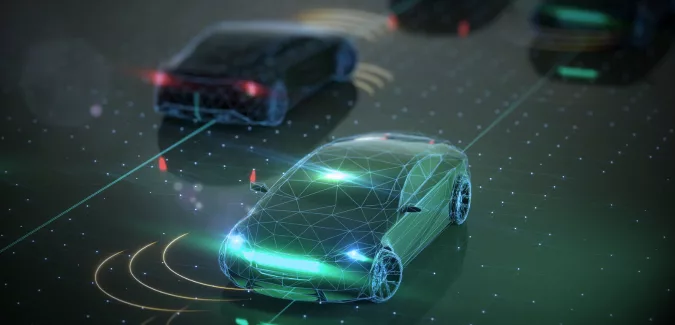SDV„Āę„Āä„ĀĎ„āčOTA„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„Āģťá捶ĀśÄß

„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éą„ÄĀťüďŚõĹ„Āģ„ā≥„āĻ„ÉÄ„ÉÉ„āĮÔľąKOSDAQԾȄĀęśĖįŤ¶ŹšłäŚ†ī
2025ŚĻī7śúą16śó•
V2X„Ā®„ĀĮÔľüŚõĹŚÜÖŚčēŚźĎ„Ā®šĽäŚĺĆ„ĀģŤ™≤ť°Ć„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶ „ÄĆ2025ŚĻīÁČą„Äć
2025ŚĻī8śúą5śó•
śó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆ„ĀĮŚďĀŤ≥™„āíśúÄŚĄ™ŚÖą„Āę„Āó„Ā¶„ÄĀšŅ°ť†ľśÄß„Āģťęė„ĀĄ„ÉĘ„Éé„Ā•„ĀŹ„āä„Āęťē∑ŚĻīŚŹĖ„āäÁĶĄ„āď„Āß„Āć„Āĺ„Āó„Āü„ÄāśĖį„Āó„ĀĄśäÄŤ°ď„āíŚįéŚÖ•„Āô„āčťöõ„Āę„āā„ÄĀŚģČŚÖ®śÄß„āĄŚģČŚģöśÄß„āíŚćĀŚąÜ„ĀęÁĘļŤ™ć„Āó„Ā™„ĀĆ„āČ„ÄĀšłÄś≠©šłÄś≠©ÁĚÄŚģü„ĀęŚģüŤ£Ö„āíťÄ≤„āĀ„āčŚßŅŚčĘ„ĀĆś†ĻšĽė„ĀĄ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀÜ„Āó„Āüšł≠„ÄĀ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘŚģöÁĺ©ŤĽäšł°ÔľąSDV: Software Defined VehicleԾȄĀł„ĀģÁ߼Ť°Ć„Āƌ䆝Äü„Āô„āčÁŹĺŚú®„ÄĀÁĄ°Á∑öťÄöšŅ°„Āę„āą„āč„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘśõīśĖįÔľąOTA: Over‚ÄĎthe‚ÄĎAirԾȄĀģ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„āā„ÄĀ„Āď„āĆ„Āĺ„ĀßšĽ•šłä„ĀęÁúüŚČ£„Ā™ŚĮĺŚŅú„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
2024ŚĻī7śúą„Āč„āČŚõĹťÄ£Ť¶ŹŚČáUN-R155Ôľą„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Áģ°ÁźÜ„ā∑„āĻ„É܄ɆԾȄĀä„āą„Ā≥UN-R156Ôľą„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„ÉąÁģ°ÁźÜ„ā∑„āĻ„É܄ɆԾȄĀĆÁĺ©ŚčôŚĆĖ„Āē„āĆ„Āü„Āď„Ā®„Āß„ÄĀOTA„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀĮťĀłśäě„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀšļčś•≠Á∂ôÁ∂ö„Āģ„Āü„āĀ„ĀģŚŅÖť†ąŤ¶ĀšĽ∂„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀśó•śú¨Ťá™ŚčēŤĽäŚ∑•ś•≠šľöÔľąJAMAԾȄĀ®śó•śú¨Ťá™ŚčēŤĽäťÉ®ŚďĀŚ∑•ś•≠šľöÔľąJAPIAԾȄĀĆŚÖĪŚźĆ„ĀßÁôļŤ°Ć„Āó„Āü„ÄĆ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥v2.2„Äć„ĀĮ„ÄĀś•≠ÁēĆ„ĀģŚģüŤ≥™ÁöĄ„Ā™ś®ôśļĖ„Ā®„Āó„Ā¶ś©üŤÉĹ„Āó„ÄĀŚģĆśąźŤĽä„É°„Éľ„āę„Éľ„Āč„āȝɮŚďĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„ĀęŤá≥„āč„Āĺ„Āß„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āęťęė„ĀĄ„ɨ„Éô„Éę„Āģ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„āíśĪā„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
OTA„ĀĮšĹē„ĀčÔľü„ĀĚ„ĀģšĽēÁĶĄ„ĀŅ„Ā®ŚĹĻŚČ≤
OTAÔľąOver-the-AirԾȄĀ®„ĀĮŤĽäšł°„Āęśź≠ŤľČ„Āē„āĆ„ĀüECUÔľąťõĽŚ≠źŚą∂Śĺ°„ɶ„Éč„ÉɄɹԾȄāĄŤĽäŤľČ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„āíÁĄ°Á∑öťÄöšŅ°„āíťÄö„Āė„Ā¶ťĀ†ťöĒ„Āč„āČśõīśĖį„ÉĽšŅģś≠£„ÉĽś©üŤÉĹŤŅŌ䆄Āô„āčśäÄŤ°ď„Āß„Āô„ÄāŚĺďśĚ•„Āģ„āą„ĀÜ„Āę„Éá„ā£„Éľ„É©„Éľ„āĄśēīŚāôŚ∑•Ś†ī„ĀęśĆĀ„Ā°Ťĺľ„āÄŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„ĀģŚą©šĺŅśÄß„āíťęė„āĀ„āč„Ā®„Ā®„āā„Āę„ÄĀ„É°„Éľ„āę„Éľ„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶„āāťĀčÁĒ®„ā≥„āĻ„Éą„ĀģŚČäśłõ„Ā®šłćŚÖ∑Śźą„ĀęŚĮĺ„Āô„āčŤŅÖťÄü„Ā™ŚĮĺŚŅú„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āę„Ā™„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚ§ß„Āć„Ā™„É°„É™„ÉÉ„Éą„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
SDVÔľą„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘŚģöÁĺ©ŤĽäšł°ÔľČ„ĀģśôģŚŹä„Āę„āą„āä„ÄĀŤĽäšł°„Āģś©üŤÉĹ„ĀĆ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„Āߌą∂Śĺ°„Āē„āĆ„āč„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„Ā£„ĀüšĽä„ÄĀOTA„ĀĮŚćė„Ā™„āč„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„ÉąśČčśģĶ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„ÄĆ„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„Ā®„Āó„Ā¶„Āģś©üŤÉĹÔľąFunction as a ServiceԾȄÄć„ā휏źšĺõ„Āô„āčšł≠ś†ł„ā§„É≥„Éē„É©„Ā®„Ā™„āä„Ā§„Ā§„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀOTA„ĀģŚįéŚÖ•„ĀĆťÄ≤„āÄ„ĀĽ„Ā©„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„Āģ„É™„āĻ„āĮ„āāŚĘóŚ§ß„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāOTA„Āę„āą„Ā£„Ā¶ŤĽäšł°„ĀĆŚłłśôā„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„Éą„Āęśé•Á∂ö„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀśĒĽśíÉŤÄÖ„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶„āĘ„āĮ„āĽ„āĻ„Āó„ĀÜ„āčŚÖ•ŚŹ£„ĀĆŚĘó„Āą„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„ÄĀÁĶźśěú„Ā®„Āó„Ā¶„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„ĀĆ„āą„āäťá捶Ā„Āę„Ā™„āč„Ā®ŤÄÉ„Āą„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
OTA„ā횼č„Āó„Āü„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„ĀģŤĄÖŚ®Ā„Ā®Śģüšĺč
„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Āꌧ߄Āć„Ā™„É°„É™„ÉÉ„Éą„āí„āā„Āü„āČ„ĀôOTA„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚą©šĺŅśÄß„ĀģŤ£Ź„Āę„ĀĮś∑ĪŚąĽ„Ā™„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„É™„āĻ„āĮ„ĀĆśĹú„āď„Āß„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„āł„Éľ„Éó„ÉĽ„ÉĀ„āß„É≠„ā≠„Éľ„Āģ„ÉŹ„ÉÉ„ā≠„É≥„āįšļčšĺč
OTA„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„āíÁčô„Ā£„Āü„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„ĀĮ„ÄĀ„Āô„Āß„ĀęÁŹĺŚģü„ĀģŤĄÖŚ®Ā„Ā®„Āó„Ā¶šłĖÁēĆ„ĀßÁĘļŤ™ć„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāšł≠„Āß„āāśúČŚźć„Ā™„Āģ„ĀĆ„ÄĀ2015ŚĻī„ĀęÁĪ≥ŚõĹ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„Āü„āł„Éľ„Éó„ÉĽ„ÉĀ„āß„É≠„ā≠„Éľ„Āģ„ÉŹ„ÉÉ„ā≠„É≥„āįšļ蚼∂„Āß„Āô„Äā„Āď„Āģšļ蚼∂„Āß„ĀĮ„ÄĀ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Á†ĒÁ©∂ŤÄÖ„ĀĆ16kmšĽ•šłäťõĘ„āĆ„ĀüŚ†īśČÄ„Āč„āČ„ÄĀŤĶįŤ°Ćšł≠„ĀģŤĽäšł°„Āģ„ā®„āĘ„ā≥„É≥„āĄ„É©„āł„ā™„āíťĀ†ťöĒśďćšĹú„Āó„ÄĀśúÄÁĶāÁöĄ„Āę„ĀĮ„ā®„É≥„āł„É≥„āíŚĀúś≠Ę„Āē„Āõ„āč„Āď„Ā®„Āę„āāśąźŚäü„Āó„Āĺ„Āó„Āü„ÄāOTAťÄöšŅ°ÁĶĆŤ∑Į„āíšĻó„Ā£ŚŹĖ„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŤĽäšł°Śą∂Śĺ°„Āęś∑ĪŚąĽ„Ā™ŚĹĪťüŅ„āíšłé„Āą„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚģüŤ®ľ„Āē„āĆ„Āü„Āģ„Āß„Āô„Äā„Āď„ĀģšļčśÖč„ā팏ó„ĀĎ„ÄĀÁīĄ140šłáŚŹį„ĀĆ„É™„ā≥„Éľ„ÉęŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āä„ÄĀŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆ„Āꌧ߄Āć„Ā™Ť°ĚśíÉ„āíšłé„Āą„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™šļčšĺč„ĀĮ„ÄĀOTAś©üŤÉĹ„ĀĆšĺŅŚą©„Āß„Āā„ā蚳ĜĖĻ„Āß„ÄĀ„ĀĚ„āƍᙚĹď„ĀĆśĖį„Āü„Ā™śĒĽśíÉÁĶĆŤ∑Į„Āę„āā„Ā™„āä„ĀÜ„āč„Āď„Ā®„āíÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŤĽäšł°„ĀĆŚłłśôā„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„Éą„Ā®śé•Á∂ö„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀśĒĽśíÉŤÄÖ„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶„Āģ‚ÄúŚÖ•ŚŹ£‚ÄĚ„ĀĆŚĘó„Āą„āč„Āü„āĀ„ÄĀOTAŚįéŚÖ•„ĀĆťÄ≤„āÄ„ĀĽ„Ā©ťęėŚļ¶„Ā™„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
OTA„Āęťôź„āČ„Ā™„ĀĄ„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āł„ĀģŤĄÖŚ®Ā
śó•śú¨ŚõĹŚÜÖ„Āß„āā„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„ĀģŤĄÖŚ®Ā„ĀĮÁŹĺŚģü„Āģ„āā„Āģ„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā2022ŚĻī„Āę„ĀĮ„ÄĀ„Éą„É®„āŅŤá™ŚčēŤĽä„ĀģšłĽŤ¶Ā„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„Āß„Āā„āčŚįŹŚ≥∂„Éó„ɨ„āĻŚ∑•ś•≠„ĀĆ„É©„É≥„āĶ„Ɇ„ā¶„āß„āĘśĒĽśíÉ„ā팏ó„ĀĎ„ÄĀ„Éą„É®„āŅ„ĀģŚõĹŚÜÖŚÖ®Ś∑•Ś†ī„ĀĆšłÄśôāÁöĄ„ĀęÁ®ľŚÉćŚĀúś≠Ę„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āĺ„Āü2020ŚĻī„Āę„ĀĮ„ÄĀ„Éõ„É≥„ÉÄ„ĀĆśĶ∑Ś§ĖŚ∑•Ś†ī„Āß„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„ā팏ó„ĀĎ„ÄĀÁĒüÁĒ£„ĀęśĒĮťöú„āí„Āć„Āü„Āó„Āüšļčšĺč„āāŚ†ĪŚĎä„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„āĆ„āČ„ĀģśĒĽśíÉ„ĀĮOTA„āíÁõīśé•ÁöĄ„ĀęÁčô„Ā£„Āü„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„ĀĆ„ÄĀŚÖĪťÄö„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„ĀĮ„ÄĆ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀģŚľĪ„ĀĄ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„ĀĆÁčô„āŹ„āĆ„ÄĀÁĶźśěú„Ā®„Āó„Ā¶ŚģĆśąźŤĽä„É°„Éľ„āę„ÉľŚÖ®šĹď„ĀęŚĹĪťüŅ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁāĻ„Āß„Āô„Äā„Ā§„Āĺ„āä„ÄĀŤĽäšł°śú¨šĹď„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„ā퍶čśćģ„Āą„Āü„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āę„Ā™„āä„Ā§„Ā§„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
OTA„Āę„Āä„ĀĎ„āčśäÄŤ°ďÁöĄ„É™„āĻ„āĮ
OTA„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀĆŤĄÜŚľĪ„Ā™Ś†īŚźą„ÄĀŤĽäšł°„ĀģŚą∂Śĺ°„āĄ„Éá„Éľ„āŅ„āíšĻó„Ā£ŚŹĖ„āČ„āĆ„āčś∑ĪŚąĽ„Ā™„É™„āĻ„āĮ„ĀĆŚ≠ėŚú®„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āü„Ā®„Āą„Āį„ÄĆťĀ†ťöĒ„Āß„ĀģŤĽäšł°Śą∂Śĺ°Ś•™ŚŹĖ„Äć„ĀĮ„ÄĀŚ§ĖťÉ®„ĀģśĒĽśíÉŤÄÖ„ĀĆ„ÉĖ„ɨ„Éľ„ā≠„ÄĀ„āĻ„ÉÜ„āĘ„É™„É≥„āį„ÄĀ„āĘ„āĮ„āĽ„Éę„Ā™„Ā©„ĀģECUÔľąťõĽŚ≠źŚą∂Śĺ°„ɶ„Éč„ÉɄɹԾȄĀęšłćś≠£„āĘ„āĮ„āĽ„āĻ„Āó„ÄĀÁČ©ÁźÜÁöĄ„ĀęšĻóŤĽä„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄ„Āę„āā„Āč„Āč„āŹ„āČ„Āö„ÄĀŤĽäšł°„ā휥Ź„Āģ„Āĺ„Āĺ„Āęśďć„āč„Āď„Ā®„ā팏ĮŤÉĹ„Āę„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮšļļŚĎĹ„ĀęÁõīÁĶź„Āô„āčŚģČŚÖ®šłä„ĀģŤĄÖŚ®Ā„Āß„Āô„Äā„ÄĆśā™śĄŹ„Āģ„Āā„āč„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„Āģś≥®ŚÖ•„Äć„ĀĮ„ÄĀś≠£Ť¶Ź„ĀģOTA„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„āíŤ£Ö„Ā£„Ā¶„Éě„Éę„ā¶„āß„āĘ„ā퍼䚳°„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀęťÄĀ„āäŤĺľ„āÄśČčś≥ē„Āß„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„ā䍼䚳°„Āģś©üŤÉĹŚĀúś≠Ę„ÄĀ„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„ĀģšĹćÁĹģśÉÖŚ†Ī„āĄťĀ荼ʌĪ•ś≠ī„Ā™„Ā©„ĀģŚÄčšļļśÉÖŚ†ĪśľŹ„Āą„ĀĄ„Āę„Ā§„Ā™„ĀĆ„āčśĀź„āĆ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„ÄĆšł≠ťĖďŤÄÖśĒĽśíÉÔľąMITMԾȄÄć„Āß„ĀĮ„ÄĀOTA„ĀģťÄöšŅ°ÁĶĆŤ∑Į„ĀęŚČ≤„āäŤĺľ„ĀŅ„ÄĀ„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„Éē„ā°„ā§„Éę„ĀģśĒĻ„ĀĖ„āď„āĄŚĀĹ„Éá„Éľ„āŅ„Āģś≥®ŚÖ•„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāśöóŚŹ∑ŚĆĖ„āĄŤ™ćŤ®ľ„ĀĆšłćŚćĀŚąÜ„Ā™Ś†īŚźą„ÄĀśĒĽśíÉŤÄÖ„ĀĮśõīśĖį„ĀģśēīŚźąśÄß„āíÁ†īŚ£ä„Āó„ÄĀś∑ĪŚąĽ„Ā™„ā∑„āĻ„É܄ɆťöúŚģ≥„ā팾ē„ĀćŤĶ∑„Āď„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āē„āČ„Āę„ÄĀ„ÄĆCAN„ā§„É≥„Éô„Éľ„ÉÄ„ÉľśĒĽśíÉ„Äć„ĀĮ„ÄĀÁČ©ÁźÜÁöĄ„Āꍼ䚳°„Āę„āĘ„āĮ„āĽ„āĻ„Āó„ÄĀCANÔľąController Area NetworkԾȄɟ„āĻ„Āęšłćś≠£„Ā™šŅ°ŚŹ∑„āíśĶĀ„Āô„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŚÜ֝ɮťÄöšŅ°„āíšĻó„Ā£ŚŹĖ„Ā£„Ā¶ŤĽäšł°„ĀģŚą∂Śĺ°Á≥ĽÁĶĪ„āí„ÉŹ„ā§„āł„É£„ÉÉ„āĮ„Āô„āčťęėŚļ¶„Ā™śĒĽśíÉ„Āß„Āô„ÄāŤŅĎŚĻī„ĀĮŚłāŤ≤©ś©üśĚź„Āß„āāŚŹĮŤÉĹ„Āę„Ā™„āä„Ā§„Ā§„Āā„āä„ÄĀŤĄÖŚ®Ā„ĀĆšłÄŚĪ§ťęė„Āĺ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Āę„ÄĀOTA„ā팏Ė„āäŚ∑Ľ„ĀŹśĒĽśíÉśČčś≥ē„ĀĮśó•„ÄÖŚ∑ߌ¶ôŚĆĖ„ÉĽŚ§öśßėŚĆĖ„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„ĀĮ‚ÄúŚįéŚÖ•„Āô„ĀĻ„Āćś©üŤÉĹ‚ÄĚ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀ‚ÄúŚČ朏ź„Ā®„Āô„ĀĻ„Ā据≠Ť®ąśÄĚśÉ≥‚ÄĚ„Ā®„Āó„Ā¶śćČ„Āą„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
Ťá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀꌟτĀĎ„ĀüśĒŅŚļú„Ā®ś•≠ÁēĆ„ĀģťÄ£śźļ
śó•śú¨śĒŅŚļú„ĀĮÁĶĆśłąÁĒ£ś•≠ÁúĀÔľąMETIԾȄāíšł≠ŚŅÉ„ĀęŤá™ŚčēŤĽäÁĒ£ś•≠„Āę„Āä„ĀĎ„āč„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Śľ∑ŚĆĖ„āíŚõĹŚģ∂śą¶Áē•„Āģťá捶ĀŤ™≤ť°Ć„Ā®šĹćÁĹģ„Ā•„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„ĀęŤá™ŚčēťĀ荼ʄāĄ„ā≥„Éć„āĮ„ÉÜ„ÉÉ„ÉČ„āę„Éľ„ĀģśôģŚŹä„Āęšľī„ĀĄ„ÄĀŤĽäšł°„ĀĆ„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„Āģś®ôÁöĄ„Ā®„Ā™„āč„É™„āĻ„āĮ„ĀĆť°ēŚú®ŚĆĖ„Āó„Āü„Āď„Ā®„ā팏ó„ĀĎ„ÄĀ„ÄĆŤÉĹŚčēÁöĄ„āĶ„ā§„Éź„Éľťė≤Śĺ°ÔľąActive Cyber DefenseԾȄÄć„ĀęťĖĘ„Āô„āčś≥ēśēīŚāô„Āģś§úŤ®é„āíťÄ≤„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀśĒĽśíÉÁôļÁĒüŚČć„Āꍥ֌®Ā„ā휧úÁü•„Āó„ÄĀťė≤Śĺ°„ÉĽŚĮĺŚŅú„āíŤŅÖťÄü„ĀęŚģüśĖĹ„Āß„Āć„āčšĹ∂„ĀģśßčÁĮČ„āíÁõģśĆá„Āó„ÄĀś≥ēŚĺčťĚĘ„Āß„ĀģŚĮĺŚŅú„āíśé®ťÄ≤„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀśĒŅŚļú„ĀĮ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£śäÄŤ°ď„ĀģÁ†ĒÁ©∂ťĖčÁôļ„āĄś®ôśļĖŚĆĖ„ÄĀŤ©ēšĺ°śäÄŤ°ď„ĀģśēīŚāô„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶Á©ćś•ĶÁöĄ„ĀęšļąÁģóśäēŚÖ•„ā퍰ƄĀĄ„ÄĀśįĎťĖďšľĀś•≠„Ā®ťÄ£śźļ„Āó„Ā¶ŚģČŚÖ®ŚģČŚŅÉ„Ā™„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£Á§ĺšľö„ĀģŚģüÁŹĺ„ĀꌟτĀĎ„ĀüÁíįŚĘÉśēīŚāô„āíšŅÉťÄ≤„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
šłÄśĖĻ„ÄĀŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆŚĀī„Āß„ĀĮśó•śú¨Ťá™ŚčēŤĽäŚ∑•ś•≠šľöÔľąJAMAԾȄĀä„āą„Ā≥śó•śú¨Ťá™ŚčēŤĽäťÉ®ŚďĀŚ∑•ś•≠šľöÔľąJAPIAԾȄĀĆŚÖĪŚźĆ„ĀßÁ≠ĖŚģö„Āó„Āü„ÄĆ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥v2.2„Äć„ĀęŚüļ„Ā•„Āć„ÄĀŚźąŤ®ą21„ĀģŤ¶ĀśĪāšļ蝆քĀ®153„ĀģťĀĒśąźśĚ°šĽ∂„ā퍮≠„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„āČ„ĀĮ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āß„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ɨ„Éô„Éę„āíÁĶĪšłÄ„ÉĽŚźĎšłä„Āē„Āõ„āčÁčô„ĀĄ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀTier 1„Āč„āČTier 3„Āĺ„Āߌ§öśģĶťöé„Āę„āŹ„Āü„āč„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„ĀĆ„Āď„āĆ„āíťĀĶŚģą„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŤĽäšł°Ť£ĹťÄ†„Āč„āȝɮŚďĀšĺõÁĶ¶„ÄĀ„āĶ„Éľ„Éď„āĻśŹźšĺõ„ĀęŤá≥„āč„Āĺ„ĀߌļÉÁĮĄ„Āę„āŹ„Āü„āč„āĶ„ā§„Éź„Éľ„É™„āĻ„āĮÁģ°ÁźÜ„ĀĆŚģüÁŹĺŚŹĮŤÉĹ„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„ĀęśĒŅŚļú„Ā®ś•≠ÁēĆ„ĀĆťÄ£śźļ„Āó„ÄĀ„Éę„Éľ„ÉęšĹú„āä„āĄśäÄŤ°ďťĖčÁôļ„ÄĀšĹ∂śēīŚāô„āíśé®ťÄ≤„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„ā§„É≥„ā∑„Éá„É≥„Éą„É™„āĻ„āĮ„ĀģśúÄŚįŹŚĆĖ„āíŚõ≥„āä„ÄĀŚģČŚÖ®„Ā™Ťá™ŚčēŤĽäÁ§ĺšľö„ĀģÁĘļÁęč„āíÁõģśĆá„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
UN-R156„ĀęŚüļ„Ā•„ĀŹOTA„ĀģśäÄŤ°ďÁöĄťė≤Ť°õśą¶Áē•
OTAÔľąOver-The-AirԾȄāĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„ĀĮ„ÄĀŤá™ŚčēŤĽä„ĀģŚą©šĺŅśÄß„āĄś©üŤÉĹŚźĎšłä„āíŚäáÁöĄ„ĀęšŅÉťÄ≤„Āô„ā蚳ĜĖĻ„Āß„ÄĀ„āł„Éľ„Éó„ÉĽ„ÉĀ„āß„É≠„ā≠„Éľšļ蚼∂„Āꚼ£Ť°®„Āē„āĆ„āč„āą„ĀÜ„Ā™ÁŹĺŚģü„Āģ„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉšļčšĺč„ĀĆÁ§ļ„ĀôťÄö„āä„ÄĀťęėŚļ¶„Ā™„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„Ā™„ĀŹ„Āó„Ā¶ŚģČŚÖ®śÄß„ĀĮśčÖšŅĚ„Āß„Āć„Āĺ„Āõ„āď„ÄāÁČĻ„ĀęŤŅĎŚĻī„ĀĮ„ÄĀŤĽäšł°„ĀĆ„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„ÉąŚłłśôāśé•Á∂ö„Ā®„Ā™„āč„Āď„Ā®„ĀßśĒĽśíÉ„ĀģŚÖ•ŚŹ£„ĀĆŚĘóŚ§ß„Āó„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āł„Āģ„É™„āĻ„āĮ„āāť°ēŚú®ŚĆĖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ŤÉĆśôĮ„ā팏ó„ĀĎ„Ā¶„ÄĀŚõĹťöõŤ¶Źś†ľ„ÄĆUN-R156„Äć„ĀĮOTA„āíťÄö„Āė„Āü„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘśõīśĖį„ĀģŚģČŚÖ®śÄß„ÉĽšŅ°ť†ľśÄß„ā퍼䚳°„É©„ā§„Éē„āĶ„ā§„āĮ„ÉęŚÖ®šĹď„ĀßšŅĚŤ®ľ„Āô„āč„Āď„Ā®„āíÁõģÁöĄ„Ā®„Āó„ÄĀšĽ•šłč„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™Ś§öŚĪ§ťė≤Śĺ°śą¶Áē•„āíśėéÁĘļ„ĀꍶŹŚģö„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„ÉąśÉÖŚ†Ī„ĀģŚģĆŚÖ®śÄßÔľąIntegrityԾȄĀ®Áúüś≠£śÄßÔľąAuthenticityԾȄĀģšŅĚŤ®ľ
OTA„Éó„É≠„āĽ„āĻ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶śúÄ„āāťá捶Ā„Ā™„Āģ„ĀĮ„ÄĀ„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„Éē„ā°„ā§„Éę„ĀĆśĒĻ„ĀĖ„āď„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āČ„Āö„ÄĀšŅ°ť†ľ„Āß„Āć„āčÁôļŤ°ĆŚÖÉÔľąŤá™ŚčēŤĽä„É°„Éľ„āę„ɾԾȄĀč„āČśŹźšĺõ„Āē„āĆ„Āü„āā„Āģ„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„āíÁĘļŚģü„ĀęšŅĚŤ®ľ„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā„Āď„āĆ„āíŚģüÁŹĺ„Āô„āč„Āü„āĀ„Āę„ÄĀ„Āô„ĀĻ„Ā¶„Āģ„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„ÉĎ„ÉÉ„āĪ„Éľ„āł„Āę„ĀĮŤ£ĹťÄ†ŤÄÖ„ĀģÁßėŚĮÜťćĶ„Āę„āą„Ā£„Ā¶ÁĒüśąź„Āē„āĆ„Āü„Éá„āł„āŅ„ÉęÁĹ≤Śźć„ĀĆšĽėšłé„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāŤĽäšł°ŚĀī„Āß„ĀĮ„ÄĀšļčŚČć„ĀęÁôĽťĆ≤„Āē„āĆ„ĀüŚÖ¨ťĖčťćĶ„āíÁĒ®„ĀĄ„Ā¶ÁĹ≤Śźć„ā휧úŤ®ľ„Āó„Ā¶ŤĽĘťÄĀšł≠„Āę„Éá„Éľ„āŅ„ĀĆśĒĻ„ĀĖ„āď„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„Ā®ś≠£Ť¶Ź„ĀģŤ£ĹťÄ†ŤÄÖ„Āč„āČťÄĀšŅ°„Āē„āĆ„Āü„āā„Āģ„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„āíÁĘļŤ™ć„Āó„Āĺ„Āô„Äā
ŚģČŚÖ®„Ā™OTA„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„ĀģÁĶĆŤ∑ĮÔľą„āĽ„ā≠„É•„āĘ„ÉĀ„É£„Éć„ÉęÔľČ
„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„Éá„Éľ„āŅ„ĀĆ„āĶ„Éľ„Éź„Éľ„Āč„āČŤĽäšł°„Āł„Ā®ŤĽĘťÄĀ„Āē„āĆ„āčťĀéÁ®č„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģťÄöšŅ°ÁĶĆŤ∑Į„ĀĆÁõóŤĀī„āĄśĒĻ„ĀĖ„āď„ĀģŤĄÖŚ®Ā„Āę„Āē„āČ„Āē„āĆ„Ā™„ĀĄ„āą„ĀÜ„ÄĀŚé≥ťáć„ĀęšŅĚŤ≠∑„Āē„āĆ„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āď„ÄāŚÖ∑šĹďÁöĄ„Āę„ĀĮ„ÄĀ„āĶ„Éľ„Éź„Éľ„Ā®ŤĽäšł°ťĖď„Āߍ°Ć„āŹ„āĆ„āč„Āô„ĀĻ„Ā¶„ĀģťÄöšŅ°„ĀĮTLS 1.2šĽ•šłä„ĀģśöóŚŹ∑ŚĆĖ„Éó„É≠„Éą„ā≥„Éę„āíÁĒ®„ĀĄ„Ā¶śöóŚŹ∑ŚĆĖ„Āē„āĆ„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀšł≠ťĖďŤÄÖśĒĽśíÉÔľąMan-in-the-MiddleԾȄāíťė≤„Āé„Ā™„ĀĆ„āČ„ÄĀ„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„ĀęťĖĘ„Āô„āč„Éá„Éľ„āŅ„Āģś©üŚĮÜśÄß„Ā®śēīŚźąśÄß„āíÁ∂≠śĆĀ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā
ŚģČŚÖ®„Ā™„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„Āģ„ā§„É≥„āĻ„Éą„Éľ„Éę„Āä„āą„Ā≥ŚģüŤ°Ć„Éó„É≠„āĽ„āĻ
„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„ā퍼䚳°„Āę„ā§„É≥„āĻ„Éą„Éľ„Éę„Āó„Ā¶ŚģüŤ°Ć„Āô„āčśģĶťöé„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚá¶ÁźÜ„ĀĆŚģČŚÖ®„Āč„Ā§ÁĘļŚģü„ĀꍰƄāŹ„āĆ„āč„āą„ĀÜ„Āꍧáśēį„Āģś§úŤ®ľśČ蝆܄ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āô„Äā„Āĺ„Āö„ÄĀ„ā§„É≥„āĻ„Éą„Éľ„ÉęŚČć„Āę„ĀĮ„ÄĀ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„ĀĆŤĽäšł°„Āģ„ÉŹ„Éľ„ÉČ„ā¶„āß„āĘ„āĄÁŹĺŚú®„Āģ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„Éź„Éľ„āł„Éß„É≥„Ā®šļ휏õśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Āč„ÄĀ„Āĺ„Āü„ā§„É≥„āĻ„Éą„Éľ„Éę„ĀęŚŅÖŤ¶Ā„Ā™„Éź„ÉÉ„ÉÜ„É™„ÉľťõĽŚäõ„āĄ„É°„ÉĘ„É™ŚģĻťáŹ„ĀĆŚćĀŚąÜ„ĀęÁĘļšŅĚ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āč„Ā™„Ā©„āíšļčŚČć„Āę„ÉĀ„āß„ÉÉ„āĮ„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āģ„ĀÜ„Āą„ÄĀECUÔľąťõĽŚ≠źŚą∂Śĺ°„ɶ„Éč„ÉɄɹԾȄĀĆŤĶ∑Śčē„Āô„āčťöõ„Āę„ĀĮ„ÄĀ„āĽ„ā≠„É•„āĘ„ÉĖ„Éľ„Éąś©üŤÉĹ„Āę„āą„āä„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„ĀģÁĹ≤Śźć„ā휧úŤ®ľ„Āó„ÄĀšŅ°ť†ľ„Āß„Āć„āč„ā≥„Éľ„ÉČ„Āģ„ĀŅ„ĀĆŚģüŤ°Ć„Āē„āĆ„āč„āą„ĀÜšŅĚŤ®ľ„Āē„āĆ„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀšłá„ĀĆšłÄ„Éě„Éę„ā¶„āß„āĘ„ĀĆś≥®ŚÖ•„Āē„āĆ„ĀüŚ†īŚźą„Āß„āā„ÄĀŤĶ∑ŚčēśģĶťöé„Āß„ĀĚ„ĀģŚģüŤ°Ć„āíťėĽś≠Ę„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éąšł≠„Āę„ā®„É©„Éľ„āĄšł≠śĖ≠„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ĀęŚāô„Āą„ÄĀ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„āíÁõīŚČć„ĀģŚģČŚģö„Āó„ĀüÁä∂śÖč„ĀłŚĺ©śóßÔľą„É≠„Éľ„Éę„Éź„ÉÉ„āĮԾȄĀß„Āć„ā蚼ēÁĶĄ„ĀŅ„ÄĀ„Āā„āč„ĀĄ„ĀĮśúÄšĹéťôź„ĀģŤĶįŤ°ĆŚģČŚÖ®„āíÁĘļšŅĚ„Āô„āčŚĺ©śóß„É°„āę„Éč„āļ„Ɇ„āāšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„Äā
ŤĽäšł°„ĀģÁČ©ÁźÜÁöĄ„Ā™ŚģČŚÖ®Áä∂śÖč„ĀģšŅĚŤ®ľ
OTA„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„ĀĆŤĽäšł°„ĀģŤĶįŤ°ĆŚģČŚÖ®„Āęśā™ŚĹĪťüŅ„ā팏ä„Āľ„Āô„Āď„Ā®„Āģ„Ā™„ĀĄ„āą„ĀÜ„ÄĀ„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„ĀģŚģüŤ°ĆśĚ°šĽ∂„Āę„āāŚą∂ÁīĄ„ĀĆŤ®≠„ĀĎ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÉĖ„ɨ„Éľ„ā≠„āĄ„āĻ„ÉÜ„āĘ„É™„É≥„āį„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŤĶįŤ°Ć„Āꚳ挏Įś¨†„Ā™„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀęŚĮĺ„Āô„āč„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„ĀĮ„ÄĀŤĽäšł°„ĀĆťßźŤĽäšł≠„Āß„Āā„āč„Ā™„Ā©„ÄĀŚģČŚÖ®„ĀĆŚćĀŚąÜ„ĀęÁĘļšŅĚ„Āē„āĆ„ĀüÁä∂ś≥Ā„Āß„Āģ„ĀŅŚģüŤ°Ć„Āē„āĆ„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āę„ĀĮ„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„ÉąŚģüśĖĹŚČć„Āę„ÄĀśõīśĖįŚÜÖŚģĻ„āĄśČÄŤ¶ĀśôāťĖď„ÄĀ„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éąšł≠„Āꌹ©ÁĒ®„Āß„Āć„Ā™„ĀŹ„Ā™„āčś©üŤÉĹ„Ā™„Ā©„āíśėéÁĘļ„ĀęťÄöÁü•„Āó„ÄĀŚźĆśĄŹ„āíŚĺó„āč„Āď„Ā®„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀŚģČŚÖ®śÄß„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ɶ„Éľ„ā∂„ÉľšĹďť®ď„āĄšŅ°ť†ľśÄß„ĀģŤ¶≥ÁāĻ„Āč„āČ„āāťĀ©Śąá„Ā™Áģ°ÁźÜ„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
RXSWIN„Āę„āą„āčťÄŹśėéśÄß„Ā®„Éą„ɨ„Éľ„āĶ„Éď„É™„ÉÜ„ā£„ĀģÁĘļšŅĚ
UN-R156„Āß„ĀĮ„ÄĀŚźĄŤĽäšł°„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ÄĆRXSWINÔľąRegulation X Software Identification NumberԾȄÄć„Ā®ŚĎľ„Āį„āĆ„ā蚳ĜĄŹ„Āģ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘŤ≠ėŚą•Áē™ŚŹ∑„āíŚČ≤„āäŚĹď„Ā¶„ÄĀŚě茾ŹŤ™ćŤ®ľ„ĀęťĖĘťÄ£„Āô„āč„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„Āģ„Éź„Éľ„āł„Éß„É≥Áģ°ÁźÜ„āíÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀOTA„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„ÉąŚĺĆ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀŚĹ≤ŤĽäšł°„ĀĆšĺĚÁĄ∂„Ā®„Āó„Ā¶Śě茾ŹŤ™ćŤ®ľ„ĀģśĚ°šĽ∂„āíśļÄ„Āü„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āč„Ā©„ĀÜ„Āč„ā퍶ŹŚą∂ŚĹďŚĪÄ„ĀƝďśėéśÄß„āí„āā„Ā£„Ā¶ŤŅĹŤ∑°„ÉĽÁõ£śüĽ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģšĽēÁĶĄ„ĀŅ„ĀĮ„ÄĀOTA„Āę„āą„āč„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘśõīśĖį„ĀģšŅ°ť†ľśÄß„Ā®ś≥ēÁöĄ„Éą„ɨ„Éľ„āĶ„Éď„É™„ÉÜ„ā£„ā팟Ɯôā„ĀęÁĘļšŅĚ„Āô„āč„Āü„āĀ„Āģťá捶Ā„Ā™ŚüļÁõ§„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„āĆ„āČ„ĀģśäÄŤ°ďÁöĄťė≤Ť°õśą¶Áē•„āíÁõłšļíŤ£úŚģĆÁöĄ„ĀęťĀ©ÁĒ®„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŤá™ŚčēŤĽä„É°„Éľ„āę„Éľ„ĀĮOTA„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„Éą„āíťęė„ĀĄŚģČŚÖ®śÄß„Ā®šŅ°ť†ľśÄß„Āģ„āā„Ā®„ĀßśŹźšĺõ„Āó„ÄĀŤĽäšł°„Āģ„É©„ā§„Éē„āĶ„ā§„āĮ„ÉęŚÖ®šĹď„Āę„āŹ„Āü„Ā£„Ā¶„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„Ā®UN-R156„Āł„ĀģŤ¶ŹŚą∂śļĖśč†„āíÁ∂ôÁ∂öÁöĄ„ĀęśčÖšŅĚ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā
śú¨ś†ľÁöĄ„Ā™OTA„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā
Ťá™ŚčēŤĽä„ĀĆŤĶį„āčIT„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Āł„Ā®ťÄ≤ŚĆĖ„Āô„āčšł≠„Āß„ÄĀOTA„ĀĮšĽäŚĺĆ„Āģ„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£śą¶Áē•„Āę„Āä„ĀĎ„āčšł≠ś†łśäÄŤ°ď„Ā®„Ā™„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĮŤĽäšł°„Ā®Ś§ĖťÉ®„Éć„ÉÉ„Éą„ÉĮ„Éľ„āĮ„ā팳ł„Āęśé•Á∂ö„Āē„Āõ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ā휥ŹŚĎ≥„Āó„ÄĀśā™śĄŹ„Āā„āčśĒĽśíÉŤÄÖ„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶śĖį„Āü„Ā™šĺĶŚÖ•ŚŹ£„ĀĆÁĒü„Āĺ„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āß„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āĺ„ĀßÁīĻšĽč„Āó„Ā¶„Āć„ĀüUN-R156„ĀęŚüļ„Ā•„ĀŹŚ§öŚĪ§ÁöĄ„Ā™ťė≤Ť°õśą¶Áē•„ĀĮ„ÄĀŤ¶ŹŚą∂ŚĮĺŚŅú„ĀģšłÄÁíį„Āß„Āā„āč„Ā®ŚźĆśôā„Āę„ÄĀšľĀś•≠„ĀģšŅ°ť†ľśÄß„āíśĒĮ„Āą„āč„ÄĆÁ§ĺšľöÁöĄ„ā§„É≥„Éē„É©„Äć„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģŤ≤¨šĽĽ„Āß„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āę„āŹ„Āü„āč„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£šĹ∂„ĀģśßčÁĮČ„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶OTA„ĀģŤ®≠Ť®ąśģĶťöé„Āč„āČ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„āíŚČ朏ź„Āęśćģ„Āą„āč„ÄĆ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ÉĽ„Éź„ā§„ÉĽ„Éá„ā∂„ā§„É≥„Äć„ĀģŚģüŤ∑Ķ„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„ÉąOTA„ĀģśôģŚŹä„Ā®„Ā®„āā„Āęťęė„Āĺ„āč„āĶ„ā§„Éź„Éľ„É™„āĻ„āĮ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀ„āĽ„ā≠„É•„āĘ„ÉĖ„Éľ„Éą„āĄśöóŚŹ∑ŚĆĖťÄöšŅ°„ÄĀ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘś§úŤ®ľ„Ā™„Ā©Ś§öŚĪ§ťė≤Śĺ°„ĀęŚĮĺŚŅú„Āó„Āü„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥„āíťÄö„Āė„Ā¶„ÄĀŚģČŚÖ®„Ā™„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£Á§ĺšľö„Ā•„ĀŹ„āä„āí„āĶ„ÉĚ„Éľ„Éą„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāOTA„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£śßčÁĮČ„āĄśą¶Áē•„Āęśā©„ĀŅ„ĀĆ„Āā„āčśĖĻ„ĀĮśįóŤĽĹ„Āę„ĀäŚēŹ„ĀĄŚźą„āŹ„Āõ„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā