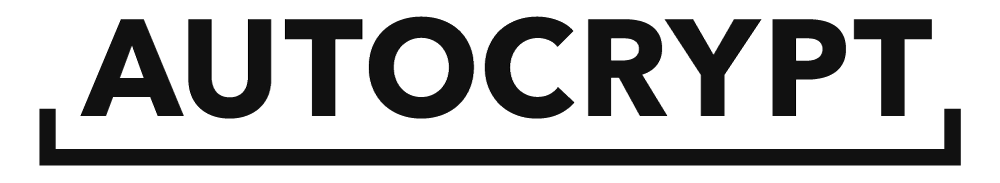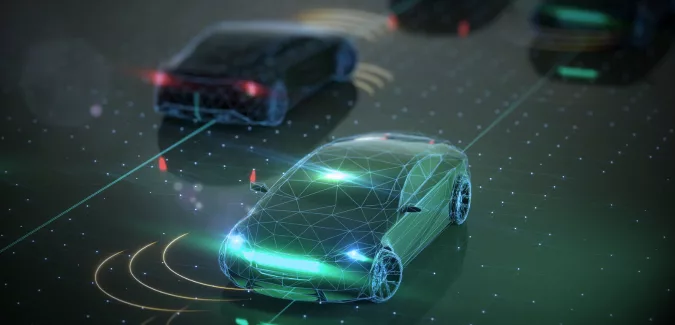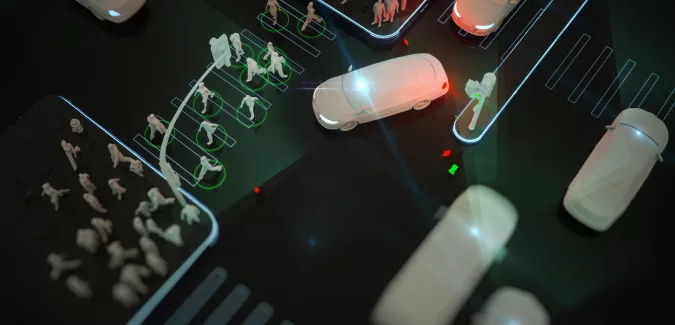- Filter by
- Categories
- Tags
- Authors
- Show all
- All
- 2024年問題
- 5gaa
- A-SPICE
- aee2023
- AIセキュリティ
- Analyzer
- AUTOCRYPT
- AutoCrypt CSTP
- AutoCrypt IDS
- AutoCrypt IVS-TEE
- AutoCrypt SA
- AutoCrypt Security Analyzer
- AUTOCYRPT
- Automotive SPICE
- automotive world
- AUTOSAR
- Autosar Adaptive
- Autosar Classic
- Autoware
- AWF
- Butterfly Key Expansion
- C-ITS
- C-V2X
- CAN通信
- CASE
- CCS & ISO/IEC 15118 Testing Symposium
- CES2023
- CES2024
- CES2025
- CES2026
- CRA
- CRA製品分類
- CSMS
- CSTP
- DEF CON
- DSRC
- E/Eアーキテクチャ
- ECU
- ECUテスティング
- ECU制御
- ECU開発
- EV
- EVS 31
- EVセキュリティ
- EV充電
- forbes asia
- Forbes Asia 100 to Watch
- Fuzz testing
- Fuzzer
- GB
- GB/T
- Gridwiz
- Hardware security module
- Hareware in the loop simulation
- HILS
- HSM
- Hubject
- International Transport Forum
- ISO 15118
- ISO 17978
- ISO 21434
- ISO/IEC 15118
- ISO/SAE 21434
- ISO/TS 5083
- ISO15118
- ITF
- ITS
- ITS Connect
- ITSフォーラム
- japan mobility show
- JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024
- JMS
- Korea IT EXPO
- KOTRA
- MaaS
- MaaS実現
- MBD
- Mobility as a Service
- OmniAir Plugfest
- OSS
- OSSセキュリティ
- OSS分析
- OTA
- OTA(Over The Air)
- PKI
- PKI認証
- Plug and Charge
- Polarion
- popcornsar
- PQC
- PSIRT
- Root CA
- SAE J2945/7
- SBOM
- SCMS
- SDV
- SDV EXPO
- SDVセキュリティ
- SDV時代
- Security Analyzer
- Security Anayzer
- Security Credential Management System
- Security Days
- software update management system
- SOVD
- SUMS
- TARA
- TEE
- TELEDRIVING
- TU-Automotive
- TU-Automotive Awards
- UAM
- UDS
- UN-R155
- UN-R156
- UNR-155
- Urban Air Mobility
- V2G
- V2I
- V2N
- V2P
- V2V
- V2X
- V2Xセキュリティ
- V2Xセキュリティ認証システム
- V2X通信
- Vehicle to grid
- VinCSS
- vSOC
- VTA
- V字モデル
- WP29
- WP29ウェビナー
- アウトクリプト
- インド
- ウェビナー
- オートモーティブワールド
- オープンソースソフトウェア
- オンデマンドウェビナー
- カーボンニュートラル
- クラウドサービス
- コネクティッドカー
- コネクティッドカーセキュリティ
- コネクテッドカー
- コネクテッドカーセキュリティ
- サイバーセキュリティ
- サイバーレジリエンス法
- ジャパンモビリティショー
- スマートファジング
- セキュリティ
- セキュリティ検証
- セキュリティ証明書管理システム
- セキュリティ評価
- ソフトウェアセキュリティインフラ
- ソフトウェアリコール
- ソフトウェア定義型自動車
- ソフトウェア定義型自動車(SDV)
- ソフトウェア部品表
- テクニカルサービス
- デフコン
- トヨタ
- ハードウェアセキュリティモジュール
- パートナーシップ
- ファジング
- ファジングテスト
- ファズテスト
- フリートマネジメントシステム
- ペネトレーションテスト
- ポップコーンザー
- モビリティ
- モビリティサービス
- モビリティ技術
- ルート認証局
- ロボタクシー
- 上場
- 不正行動検知
- 中国サイバーセキュリティ規格
- 交通弱者
- 人とクルマのテクノロジー展
- 位置情報システム
- 侵入検知システム
- 充電インフラ
- 免許制度
- 公開鍵暗号基盤
- 出荷後の自動車にサイバーセキュリティ
- 協調型自動運転
- 協調型高度道路交通システム
- 国際交通フォーラム
- 型式認証
- 安全性検証
- 展示会
- 日本におけるMaaS
- 日本のEV市場
- 日本の自動運転
- 日産
- 日産サクラ
- 標準仕様
- 横浜展示会
- 次世代エアモビリティ
- 次世代モビリティ
- 次世代モビリティ技術展
- 次世代空モビリティ
- 異常行動検知
- 空飛ぶクルマ
- 耐量子計算機暗号
- 脆弱性スキャン
- 脆弱性管理
- 自動車サイバーセキュリティ
- 自動車サイバーセキュリティテスティング
- 自動車サイバーセキュリティテスト
- 自動車サイバーセキュリティ規格
- 自動車セキュリティ
- 自動車セキュリティ検証
- 自動車のリコール
- 自動車ハッキング
- 自動車技術展
- 自動運転
- 自動運転OS
- 自動運転システム
- 自動運転セキュリティ
- 自動運転とEV
- 自動運転トラック
- 自動運転レベル
- 自動運転免許
- 自工会/部工会・サイバーセキュリティガイドライン
- 診断規格
- 車両IDS
- 車両サイバーセキュリティ
- 車両セキュリティ
- 車両向けのファイアウォール
- 車両型式認証
- 車内セキュリティ
- 車載Ethernet
- 車載イーザネット
- 車載システム
- 車載セキュリティ
- 車載ソフトウェア
- 車載組み込みシステム
- 運転免許
- 遠隔型自動運転
- 鍵管理
- 鍵管理統合ソリューション
- 電気自動車
- 電気自動車セキュリティ
- 電気自動車普及
- 韓国次世代モビリティ技術展
- 高度道路交通システム
2026年1月23日
2026年1月23日
近年、日本の自動車業界における最大のトピックは間違いなく「サイバーセキュリティ」です。国土交通省が道路運送車両法の保安基準を改正し、UN-R155(サイバーセキュリティ法規)への適合を義務付けたことにより、セキュリティはもはや「選択」ではなく、販売のための「必須条件」となりました。これに伴い、以下の2つの基準を満たすことが、これからの自動車業界にとって重要になっています。 UN-R155: 自動車メーカー(OEM)が実施すべきセキュリティ活動を定義 ISO/SAE 21434: 上記を遵守するためのプロセスやエンジニアリングの国際標準 しかし、現場の皆様は一つの大きな課題に直面しているのではないでしょうか。それは、ガイドラインが「手順」は示してくれても、「実際にどう技術を適用して車を守るか」という具体的な実装解までは教えてくれないという点です。特に技術的な観点において、「どれほど強力な暗号アルゴリズムを採用しても、その鍵(Key)が漏えいすれば全てのセキュリティは無効化される」という事実は見落とされがちです。結局のところ、セキュリティの成否はアルゴリズムそのものではなく、それを運用する「鍵(Key)」の管理にかかっています。本記事では、自動車セキュリティの根幹となる「鍵管理(Key Management)」について、SDV時代のサプライチェーンリスクと照らし合わせながら説明します。 なぜ今、自動車セキュリティで「鍵管理」が重要なのか? 自動車セキュリティの国際標準である ISO/SAE 21434では、暗号鍵や証明書を含むセキュリティ資産を車両ライフサイクル全体で適切に管理することが求められており、その実現手段として KMS(Key Management System)のような仕組みが実務上不可欠になりつつあります。一方、自動車環境における鍵管理は一般的なIT環境とは比較にならないほど複雑かつ過酷です。 膨大な制御ユニット(ECU): 車両1台あたり数十〜百個以上のECUが存在し、それぞれに固有の鍵が必要です。 複雑なサプライチェーン: OEMとTier 1、Tier 2といったサプライヤー間での安全な鍵の受け渡しが必須となります。 長期にわたるライフサイクル: 車両が製造され、10年以上走行し、廃棄されるまでの長期間、鍵の安全性と更新性を保証しなければなりません。 もし鍵管理に不備があれば、それは単なるバグではなく、UN-R155やISO/SAE 21434のTARA(脅威分析及びリスク評価)において「高リスク項目」として分類され、CSMS認証やVTA取得に悪影響を及ぼす可能性があります。 特に、SDV(Software Defined […]
2025年12月16日
2025年12月16日
レベル3以上の自動運転システム(ADS)の実用化が加速する中、日本の自動車業界にとって最大の課題は「いかにしてシステムの安全性を証明するか」という点にありました。これまでガイドライン的な位置付けであったISO/TR 4804はすでにISO/TS 5083に置き換えられ、ガイドラインからより具体的な技術仕様へと進化しました。こうした状況下で登場した ISO/TS 5083 (Road vehicles — Safety for automated driving systems) は自動車業界に明確な解を提示しています。この規格は単なるテスト項目のリストではありません。自動運転システム(ADS)の設計、検証、妥当性確認(V&V)の全工程を網羅する最上位の技術仕様書であり、自動運転車が公道を走行するために不可欠な「安全性への説明責任(Accountability)」を体系化した文書です。本記事では、ISO/TS 5083が既存のISO 26262やISO 21448とどのような関係にあり、開発現場において何を準備すべきかについて解説します。 ISO/TS 5083の全体像:安全ライフサイクルと規格構成 ISO/TS 5083規格は、設計(Design)・検証(Verification)・妥当性確認(Validation)の各プロセスをV字モデルとして体系化しており、自動運転システム(ADS)開発における一連の安全活動を包括しています。ISO/TS 5083に基づくと、自動運転システム(ADS)の安全開発は以下のようなフローで進行します。 コンセプト・要件定義段階 すべての起点はODD(運行設計領域)の定義です。「どこで・どのような条件で走るか」を明確にします。これと並行して、RAC(リスク受容基準)を設定し、「どの程度のリスクまでなら許容されるか」という定量的なゴールを策定します。 開発・設計段階 […]
2025年11月25日
2025年11月25日
近年、自動車業界では「ソフトウェア定義車両(Software-Defined Vehicle:SDV)」という言葉を耳にする機会が増えています。簡単に言うと、SDVはこれまでの「機械としてのクルマ」から、「コンピュータとしてのクルマ」へと大きくシフトしていく流れのことです。その中心にいるのが、高い処理能力と計算能力を備えた高性能コンピュータ(HPC:High Performance Computer)です。クルマの中に、まるでデータセンターのサーバーが載っているようなイメージです。このHPCがあるからこそ、ソフトウェア定義車両(SDV)は周囲の状況をリアルタイムに理解し、自ら判断して動く高い自律性や、クラウドや他の車両・インフラとつながる高い相互接続性を手に入れることができます。 一方で、「車両診断」という観点から見ると、ここには大きなパラダイムシフトが生まれようとしています。これまでの診断基準は、主にセンサーやアクチュエーター、その配線、ECU間をつなぐバスシステムの故障を見つけることに焦点を当ててきました。例えば、「このセンサーの値がおかしい」「このECUとの通信が途切れている」といった、ハードウェアや配線レベルのトラブルを検出することが中心でした。 しかし、HPCによって駆動されるSDVでは、それだけでは不十分となる可能性があります。「どこかの部品が壊れているかどうか」を見るだけではなく、HPC上で動作している複雑なソフトウェアそのものについても、その動作状況を詳細に分析し、異常や不具合を的確に診断する必要があります。つまり、SDV時代の診断は、従来のようなハードウェア中心の「壊れた部品探し」から、「ソフトウェアとハードウェアを一体として捉え、そのライフサイクル全体を管理・検証する診断」へと役割が拡大しています。こうした新しい要求が、従来とは異なる新たな診断基準や診断フレームワークを定義する動きにつながっており、その代表例の一つが本稿で取り上げるSOVD(Service Oriented Vehicle Diagnostics)です。 SOVDとは何か 従来の車両診断は、車載ECU(電子制御ユニット)ごとに個別に設計された診断プロトコル(主にUDS:Unified Diagnostic Services)を使って行われてきました。現在もこのアプローチは広く利用されていますが、近年のSDV化によって車両ソフトウェアが複雑化し、HPCをはじめとする車載コンピュータの役割が拡大する中で、ECU単位での診断だけでは将来の要求を十分に満たしきれないのではないかという課題が指摘されるようになってきました。 この課題に対応するため、業界標準の整備を行う団体であるASAM(Association for Standardisation of Automation and Measuring Systems)がSOVDの標準化プロジェクトを立ち上げました。ASAMは、車両の診断・試験・検証に関する標準的な仕様を策定し、国際的に普及させることで、自動車メーカーやサプライヤー間の製品やサービスの互換性を高めつつ、診断の高度化と効率化を促進している団体です。SOVD(Service Oriented Vehicle Diagnostics)は、その名のとおり車両診断を「サービス」として捉え直すための標準です。従来の診断では、診断テスターと各ECUが直接対話し、UDS(ISO 14229)などのプロトコルを用いてECU単位でDTCを読み出したり、計測値を取得したり、ソフトウェアを書き換えたりしていました。これに対してSOVDは、車両内に存在する診断機能や状態情報を「サービス群」として抽象化し、そのサービスに対して工場の診断機器、クラウド上のバックエンドシステム、HPC上で動作する車内アプリケーションなど、さまざまなクライアントが共通のインターフェースとデータモデルでアクセスできるようにすることを目指します。言い換えれば、車両全体を「診断サービスを提供するプラットフォーム」と見なし、その入り口を統一するためのAPI仕様がSOVDです。なお、ASAMで策定されたSOVDの内容は、現在ISO […]
2025年10月31日
2025年10月31日
量子コンピューターの急速な進化により、私たちのデジタル社会を支えてきた暗号技術はかつてない危機に直面しています。特に、コネクテッドカーや自動運転車が普及する自動車業界では、その影響が極めて大きくなると予測されています。本稿では、量子コンピューターによって生じる脅威とそれに対抗する「耐量子計算機暗号(Post-Quantum Cryptography:PQC)」の必要性、さらには日本を含む各国の取り組みについて解説します。 PQCとは何か 耐量子計算機暗号(Post-Quantum Cryptography:PQC)は量子コンピューターによる攻撃にも耐えられるよう設計された新しい暗号技術です。量子暗号通信のように量子現象を利用するのではなく、現在のコンピューター上で動作し、既存のシステムと互換性を保ちながら安全性を確保することを目的としています。 量子コンピューターがもたらす暗号の危機 現在、広く使われている素因数分解に基づく暗号方式(Rivest Shamir Adleman:RSA)および楕円曲線暗号(ECC)は素因数分解の困難さ・離散対数問題の困難さなどの数学的問題に依存した暗号方式です。これらは従来型コンピューターでは解読に数百万年を要するほど安全とされてきました。しかし、量子コンピューターが実用化されれば事情は一変します。ショアのアルゴリズム(量子アルゴリズム)を活用することで、RSA-2048やECC-256といった暗号は数時間で解読可能になると予測されています。専門家によれば、2030年代半ばには暗号解読ができる「暗号的に関連する量子コンピューター」が登場する可能性があります。 さらに懸念されるのが「Harvest Now, Decrypt Later(今収集し、後で解読する)」攻撃です。これは、現在暗号化されている重要データを大量に収集し、量子コンピューターが実用化された後に解読を試みる手法です。企業の知的財産、R&Dデータ、または自動車関連の設計情報など、長期間価値を持つデータほどリスクが高くなります。 新しい暗号方式の標準化:NISTの取り組み 暗号が量子計算機により破られるリスクに対処するには、単に「新しい暗号」を用意するだけでは不十分です。(1) 鍵共有(キー合意)の置き換え、(2) 電子署名の置き換え、(3) 既存プロトコルへの統合と段階移行(ハイブリッド)、(4) 将来の更新に耐える暗号アジリティ—少なくともこの四点を満たす体系的な対策が必要でした。 この要件に応えるかたちで、米国のNISTは2016年にPQC標準化プロジェクトを開始し、複数ラウンドの公開評価を経て2024年8月に鍵共有用のML-KEM(FIPS 203)、署名用のML-DSA(FIPS 204)とSLH-DSA(FIPS 205)を最終標準として公表しました。これにより、従来のRSA/ECCが担っていた役割に対する量子耐性の「正規の後継部品」が初めて揃ったことになります。 […]
2025年8月22日
2025年8月22日
自動運転の未来がついに日本の路上で現実のものとなりつつあります。2025年はレベル4の自動運転バスがすでに公道を走り始め、海外からは先進的なロボタクシーがテスト走行を開始するなど、多くの人が「未来の乗り物」を肌で感じられるようになった記念すべき年です。この急速な変化は、単なる技術の進歩だけによってもたらされたわけではありません。日本政府がこれを国家戦略と位置づけ、官民一体となって「モビリティ革命」を推し進めている結果です。特に車がソフトウェアによって定義され、スマートフォンのように進化し続けるSDV(Software Defined Vehicle)はこの革命の中核をなすコンセプトです。 本記事では、この大きな変革期を「政策・実証・技術」という3つの視点から多角的に分析します。激化するグローバル競争の中、日本は2030年までにSDV市場で30%のシェア獲得という目標を掲げています。まさに「社会実装元年」と呼ぶにふさわしい2025年、日本がどのように未来のモビリティを切り拓いていくのか、その現在地と今後の展望を詳しく見ていきましょう。 日本の自動運転の概況 レベル4の社会実装へ 日本の自動運転技術はSAE(米国自動車技術会)が定める国際基準のレベル0から5の分類に沿って着実に開発が進められています。特定の条件下でシステムが運転を担うレベル3はすでに市販車にも搭載されています。その先駆けとなったのがホンダが2021年3月に発表した「レジェンド(LEGEND)」です。このモデルには世界で初めて認可されたレベル3技術「Honda SENSING Elite」が搭載され、DMPのHDマップを活用することで高速道路でのハンズオフ走行を可能にしました。 そして現在、日本の挑戦は特定のエリア内で運転手が不要となるレベル4の社会実装へと向かっています。その象徴的な事例が福井県永平寺町で2023年5月から運行している国内初のレベル4自動運転サービスです。さらに2025年2月には茨城県ひたち市で中型バスによるレベル4の営業運行がスタートし、約6.1kmという国内最長のルートで実用化を果たしました。 これらの成功事例を足がかりに政府は2025年度までに全国50カ所、2027年度までには100カ所以上で同様のサービスを展開するという目標を掲げており、日本各地で自動運転が日常の風景になる日もそう遠くないかもしれません。 国家戦略とそれを支える法制度 日本の自動運転開発は個々の企業の努力だけでなく、政府による強力なリーダーシップに支えられています。その中核をなすのが2024年5月経済産業省と国土交通省が共同で策定した「モビリティDX戦略」です。この戦略はSDVのグローバル販売台数における「日系シェア3割」の実現という野心的な目標を掲げ、①協調領域での開発加速②ソフトウェア中心の産業構造への転換③半導体供給網などの経済安全保障強化という3つの柱を明確に示しています。 ■ 社会実装を可能にする法整備 この国家戦略を実現するため、具体的な法制度の整備も同時に進められています。まず2023年4月に施行された改正道路交通法はレベル4自動運転の公道走行を正式な「許可制度」として創設しました。これにより事業者は明確な法的根拠のもと、自動運転サービスを事業として展開できるようになりました。 ■ SDV時代の新たな安全基準:サイバーセキュリティ規制 さらに、車両のSDV化はOTAによる利便性の向上と同時にサイバー攻撃のリスクという新たな課題を生み出しました。これに対応するため、日本は国連の国際基準であるUN-R155(サイバーセキュリティ)およびUN-R156(ソフトウェアアップデート)を国内法に迅速に導入。自動車メーカーに対して車両の設計から廃棄までのライフサイクル全体を通じたセキュリティ管理体制(CSMS/SUMS)の構築を義務付け、デジタル時代の新たな安全基準を確立しました。 ■ 挑戦を後押しする支援策 こうした制度設計と並行し、政府は「RoAD to the […]
2025年8月5日
2025年8月5日
今、100年に1度とも言われる大変革期を迎えている自動車業界では、特に「自動運転車」の実現に大きな期待が寄せられています。 本記事では、自動運転技術の中核を担う「V2X」について、自動運転との関係や今後の課題に焦点を当てて詳しく解説していきます。 V2Xとは? V2X(Vehicle to Everything)は、「自動車」と「あらゆるモノ」をつなげる無線通信技術の総称です。ITS(Intelligent Transport Systems)の主要な要素の1つとして近年特に注目されており、V2Xの発展は交通安全だけでなく、交通渋滞の解消、環境負荷の低減、快適な移動体験の提供など、多様な分野での活躍が期待されています。 車と接続する「モノ」として想定されているのは以下の4つです。 V2V (Vehicle to Vehicle): 車車間通信 V2Vとは、車両が周辺の他の車両と直接ワイヤレス通信を行い、互いの位置、速度、進行方向といった走行情報をリアルタイムで共有する技術です。この技術の主な目的は、車両同士の衝突事故を未然に防ぐことにあります。例えば、見通しの悪い交差点に進入する際、死角から接近してくる車両の情報を事前に受け取ったり、前方の車両が急ブレーキをかけた場合にその後続車へ即座に信号を伝え、追突事故を防ぐといった運転支援システムの実現が可能です。ただし、この技術は通信機能を搭載した自動車が十分に普及する必要があるという課題があります。 V2I (Vehicle to Infrastructure): 路車間通信 V2Iとは、車両が道路に設置された信号機、交通標識、路側センサーといった交通インフラと通信する技術です。ドライバーはこの技術を通じて前方の信号機の情報、工事、事故発生エリアといった情報を事前に受け取ることができます。また、インフラに設置されたセンサーが歩行者やV2X非対応の車両を検知し、その情報を周辺車両に通知することも可能です。V2I技術を広く活用するためには、道路インフラ自体の高度化と関連機器の整備が不可欠となります。 V2P (Vehicle to Pedestrian): […]
2025年7月24日
2025年7月24日
日本の自動車業界は品質を最優先にして、信頼性の高いモノづくりに長年取り組んできました。新しい技術を導入する際にも、安全性や安定性を十分に確認しながら、一歩一歩着実に実装を進める姿勢が根付いています。こうした中、ソフトウェア定義車両(SDV: Software Defined Vehicle)への移行が加速する現在、無線通信によるソフトウェア更新(OTA: Over‑the‑Air)のセキュリティについても、これまで以上に真剣な対応が求められています。 2024年7月から国連規則UN-R155(サイバーセキュリティ管理システム)およびUN-R156(ソフトウェアアップデート管理システム)が義務化されたことで、OTAセキュリティは選択ではなく、事業継続のための必須要件となりました。特に、日本自動車工業会(JAMA)と日本自動車部品工業会(JAPIA)が共同で発行した「サイバーセキュリティガイドラインv2.2」は、業界の実質的な標準として機能し、完成車メーカーから部品サプライヤーに至るまで、サプライチェーン全体に高いレベルのセキュリティを求めています。 OTAは何か?その仕組みと役割 OTA(Over-the-Air)とは車両に搭載されたECU(電子制御ユニット)や車載ソフトウェアを無線通信を通じて遠隔から更新・修正・機能追加する技術です。従来のようにディーラーや整備工場に持ち込む必要がなく、ユーザーの利便性を高めるとともに、メーカーにとっても運用コストの削減と不具合に対する迅速な対応が可能になるという大きなメリットがあります。 SDV(ソフトウェア定義車両)の普及により、車両の機能がソフトウェアで制御されるようになった今、OTAは単なるアップデート手段ではなく、「サービスとしての機能(Function as a Service)」を提供する中核インフラとなりつつあります。しかし、OTAの導入が進むほど、サイバー攻撃のリスクも増大しています。OTAによって車両が常時インターネットに接続されることで、攻撃者にとってアクセスしうる入口が増えることになり、結果としてセキュリティ対策がより重要になると考えられます。 OTAを介したサイバー攻撃の脅威と実例 このように大きなメリットをもたらすOTAですが、その利便性の裏には深刻なセキュリティリスクが潜んでいます。 ジープ・チェロキーのハッキング事例 OTAシステムを狙ったサイバー攻撃は、すでに現実の脅威として世界で確認されています。中でも有名なのが、2015年に米国で発生したジープ・チェロキーのハッキング事件です。この事件では、セキュリティ研究者が16km以上離れた場所から、走行中の車両のエアコンやラジオを遠隔操作し、最終的にはエンジンを停止させることにも成功しました。OTA通信経路を乗っ取ることで、車両制御に深刻な影響を与えることが可能であることが実証されたのです。この事態を受け、約140万台がリコール対象となり、自動車業界に大きな衝撃を与えました。 このような事例は、OTA機能が便利である一方で、それ自体が新たな攻撃経路にもなりうることを示しています。車両が常時インターネットと接続されることで、攻撃者にとっての“入口”が増えるため、OTA導入が進むほど高度なセキュリティ対策が求められます。 OTAに限らない、サプライチェーン全体への脅威 日本国内でも、サイバー攻撃の脅威は現実のものとなっています。2022年には、トヨタ自動車の主要サプライヤーである小島プレス工業がランサムウェア攻撃を受け、トヨタの国内全工場が一時的に稼働停止となりました。また2020年には、ホンダが海外工場でサイバー攻撃を受け、生産に支障をきたした事例も報告されています。 これらの攻撃はOTAを直接的に狙ったものではありませんが、共通しているのは「セキュリティの弱いサプライチェーンが狙われ、結果として完成車メーカー全体に影響している」という点です。つまり、車両本体だけでなく、サプライチェーン全体を見据えたセキュリティ対策が不可欠になりつつあります。 OTAにおける技術的リスク OTAセキュリティが脆弱な場合、車両の制御やデータを乗っ取られる深刻なリスクが存在します。たとえば「遠隔での車両制御奪取」は、外部の攻撃者がブレーキ、ステアリング、アクセルなどのECU(電子制御ユニット)に不正アクセスし、物理的に乗車していないにもかかわらず、車両を意のままに操ることを可能にします。これは人命に直結する安全上の脅威です。「悪意のあるソフトウェアの注入」は、正規のOTAアップデートを装ってマルウェアを車両システムに送り込む手法です。これにより車両の機能停止、ユーザーの位置情報や運転履歴などの個人情報漏えいにつながる恐れがあります。「中間者攻撃(MITM)」では、OTAの通信経路に割り込み、アップデートファイルの改ざんや偽データの注入が可能になります。暗号化や認証が不十分な場合、攻撃者は更新の整合性を破壊し、深刻なシステム障害を引き起こします。さらに、「CANインベーダー攻撃」は、物理的に車両にアクセスし、CAN(Controller Area […]
2025年6月24日
2025年6月24日
日本の自動車産業において、「安全」という言葉の意味が根底から変わろうとしています。これまでの「安全」とは、衝突時の人の保護や事故の予防といった物理的側面を中心としたものでした。しかし、コネクテッドカーやソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)の本格的な普及を背景に、デジタル領域での信頼性が新たな「安全」の中核となりつつあります。現在のクルマは、1億行を超えるソフトウェアコードによって制御され、常時ネットワークに接続された“走るIT機器”とも呼ばれています。この状況において、サイバーセキュリティはもはや情報システム部門の専門領域にとどまる問題ではありません。車両制御の乗っ取りによる人命へのリスク、大規模なリコール対応、さらには企業ブランドへの甚大な信頼喪失に直結する、経営リスクそのものとなっています。さらに、脅威は一台の車両にとどまらず、数百社に及ぶサプライヤーが複雑に関与するサプライチェーン全体に波及する構造的リスクです。日本の自動車業界はサイバーセキュリティ課題に対して個社の対応だけでなく、業界全体でセキュリティ体制の底上げに取り組んでいます。 その中心にあるのが、以下の2つの柱です: 業界横断での連携と標準化 サプライチェーン全体への包括的支援 これらは単独の施策ではなく、相互に連動しながら日本のモビリティ産業の“新しい安全保障”を構築する枠組みと言えます。ここでは、これら2つの柱を軸に、日本の自動車業界が進める最新の取り組みについて説明します。 爆発的に成長する市場と現実化する脅威 日本の自動車サイバーセキュリティ市場は、かつてない成長を遂げています。Imarcの市場調査によると、2024年に2億1,900万ドル規模であった市場は、2033年までには7億9,500万ドルに達すると予測されており、その年平均成長率(CAGR)は15.4%に達する見込みです。市場が急拡大する理由の一つは、サイバー攻撃がもはや想定上のリスクではなく、事業に影響を及ぼす脅威として顕在化していることにあります。2022年、トヨタ自動車の一次サプライヤーである小島プレス工業がランサムウェア攻撃を受けて国内14工場が全面停止した事件はサプライチェーンの脆弱性が事業継続に直結することを業界全体につきつけました。また、2022年にはデンソーのドイツ法人がハッカー集団「Pandora」の攻撃を受けるなど、グローバルなサプライチェーンが常に脅威に晒されています。警察庁の報告によれば、2022年の国内ランサムウェア被害230件のうち、製造業が32.6%と最多を占めました。警察庁の報告は、日本の基幹産業の一つである自動車産業もサイバー攻撃の標的となり得ることを強く示しています。深刻な被害を未然に防ぎ、事業継続性を確保するためにも今こそ体系的で堅牢なセキュリティ対策の構築が求められています。 政府の強力な後押しと法規制 こうした脅威に対し、日本政府も法規制の側面から対応を強化しています。その中核となるのが、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で採択されたサイバーセキュリティ法規(UN-R155)です。日本ではこのUN-R155が迅速に国内法制化され、2022年7月からOTA(無線アップデート)対応の新型車に、2024年7月からは継続生産される全てのOTA対応車両に義務化されました。この法規への準拠は、自動車の設計から廃棄に至るまでのセキュリティ対策を定めた国際標準規格「ISO/SAE 21434」への対応と密接に関連しています。これにより、自動車メーカー(OEM)は自社のみならず、部品を供給するサプライヤーが開発プロセス全体でセキュリティを確保する管理体制(CSMS)を適切に構築・運用しているかを審査し、証明する責任を負うことになります。これはセキュリティ対策が個社の問題ではなく、サプライチェーン全体で取り組むべき必須要件となったことを意味しています。 業界の具体的なアクション:連携・支援 個社の努力だけでは対応しきれないという共通認識のもと、業界は具体的な協調行動を加速させています。 1. 業界横断での連携と標準化 個社の努力だけでは対応しきれない複雑なサイバー脅威に対し、日本の自動車業界は「競争ではなく協調」を基本として業界での連携と標準化を加速させています。その中心にあるのが2021年2月に設立された「一般社団法人日本自動車ISAC(J-Auto-ISAC)」です。J-Auto-ISACは、設立からわずか2年で会員企業が100社を超え、現在もその数は増え続けています。加盟企業は、トヨタ、ホンダ、日産といった主要自動車メーカー(OEM)とデンソーやアイシンといった大手サプライヤー、さらには車載ソフトウェアや半導体を手がけるIT企業まで、業界を越えて多岐にわたります。 その活動の中で最も重要なところは脅威情報の共有です。J-Auto-ISACは国内外から最新の脆弱性情報や攻撃事例を収集・分析し、会員企業に迅速に共有するハブとして機能しています。特に、個社で契約すれば年間数億円に上ることもある高価な脆弱性情報を共同で購入・共有することで、経営体力の限られる中小企業の負担を大幅に軽減し、サプライチェーン全体のセキュリティ対応能力の向上に貢献しています。また、サイバー脅威に対応するため、理事会と運営委員会の下に「技術委員会」「情報収集・分析センター(SOC)」「サポートセンター」といった専門組織を設置しています。技術委員会では最新の攻撃手法の分析や防御技術の研究開発を推進し、SOCはリアルタイムでの脅威監視とインシデント対応を担当しています。 国際連携も積極的で、2024年には米国のAuto-ISACと情報共有に関する協力覚書(MOU)を締結しました。これにより、国境を越えて仕掛けられるサイバー攻撃に対し、グローバルな視点での迅速な情報共有と共同対処が可能となりました。さらに、J-Auto-ISACは業界標準の策定にも深く関与しています。特に、ソフトウェアの構成要素を可視化するソフトウェア部品表(SBOM)の標準化を推進しており、これにより車両に搭載される複雑なソフトウェアの透明性を高め、脆弱性の早期発見と迅速な対応を可能にする管理体制の構築を目指しています。これは、将来のソフトウェア・アップデート管理(SUMS)においても不可欠な基盤となります。 このように、J-Auto-ISACは単なる情報共有だけでなく、技術研究、インシデント対応支援、標準化、国際連携といった多岐にわたる活動を通じて日本の自動車業界におけるサイバーセキュリティの中核的な役割を果たし、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献しています。 2. サプライチェーン全体への支援 2022年の小島プレス工業へのサイバー攻撃がトヨタの国内全工場を停止させた事件は、「サプライチェーンの脆弱性がOEMの事業継続に直結する」という事実を業界全体に強く認識させました。この事件をきっかけに、日本の自動車業界はサプライチェーン全体のセキュリティレベルを底上げするための、包括的な支援体制の構築を急いでいます。 その基盤となるのが、日本自動車工業会(JAMA)と日本自動車部品工業会(JAPIA)が連携して策定した「自動車産業サイバーセキュリティガイドライン」です。このガイドラインは、経済産業省が推進する「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)」を自動車産業向けに具体化したものであり、サプライチェーン全体でのリスク管理と対策の標準化を目指すものです。 このガイドラインの最大の特徴は完成車メーカーだけでなく、サプライヤーから小規模な事業者まで、数千社に及ぶサプライチェーンの全階層を対象としている点です。ガイドラインでは各企業が遵守すべきセキュリティ対策項目が具体的に示されており、企業はこれを用いて自社のセキュリティレベルを自己評価し、継続的な改善を図ることが求められます。このガイドラインにより、中小企業の意識と対応を引き上げてサプライチェーン全体の対応力を高めることを狙いとしています。また、ガイドラインを示すだけでなく、その実効性を高めるための支援策も講じられています。特に中小企業に対してはガイドラインの理解を深めるための教育プログラムや具体的な対策を導入するための技術的な支援が提供されています。これにより、単なる「努力目標」で終わらせることなく、実効性のある対策へと繋げています。 さらに、経済産業省はサプライチェーン全体のセキュリティ対策を客観的に可視化・評価するための新たな制度設計を進めており、2026年度中の制度開始を目指しています。この制度が導入されれば、OEMは取引先のセキュリティ対策状況を定量的に把握し、リスクの高い企業に対して改善を促すといったサプライチェーン管理が可能になります。これは、UN-R155で求められるサプライヤーの管理責任を果たす上でも重要な仕組みとなるでしょう。 […]
2025年5月22日
2025年5月22日
CRA製品分類の重要性 2024年に正式採択されたサイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act:CRA)は、ネットワーク接続機能を持つハードウェア・ソフトウェア製品に対して、設計・運用・更新・廃棄のすべての段階でサイバーセキュリティ要件の実装を義務づけるEUの新しい規制です。前回(CRA法とは?知っておくべき新たなセキュリティ義務と対応ポイント)の記事では、CRAの背景、対象となる製品の概要、そしてなぜ今、欧州が本気でセキュリティ強化に乗り出したのかを解説しました。この記事から読み始める方にとっても問題ありません。今回のテーマは、CRAの全体像の中でも「製品分類とそれに応じた対応策」にフォーカスを当てた実務的なガイドです。 CRAでは、すべての製品をそのサイバーリスクのレベルに応じてクラスを分けて、それぞれに異なる評価方式とセキュリティ要件が求められます。特に「自社製品がどのクラスに該当するのか」を理解することは、CRA対応の第一歩です。本記事では、以下の3点を軸に、法令に基づく実践的な視点で解説します。 CRAにおける製品クラスの違いと分類方法 各クラスごとに求められる具体的なセキュリティ対策 適合性評価の進め方と準備のポイント CRA対応は、単なる法令遵守にとどまらず、製品価値の向上と市場競争力を強化するチャンスでもあります。CRA対応を進めるうえで避けて通れない「製品分類」と「クラスごとの対応要件」について、実務に役立つ視点で解説していきます。 CRAにおける製品分類 サイバーレジリエンス法では、すべての製品が一律に同じセキュリティ対策を求められるわけではありません。製品の特性やリスクの程度に応じて、求められる対応や評価方法が異なります。その判断の基準となるのが、製品の「分類」です。CRAでは、対象製品を大きく以下の4カテゴリに分類しています。 一般製品(デフォルトカテゴリ):特に高いリスクを持たない製品 重要製品(Class I):中リスクを持つ製品。(Annex III) 重要製品(Class II):高リスクを持つ製品。(Annex III) クリティカル製品:社会インフラ・国家安全に関わる製品(Annex IV) この分類によって、適合性評価においてどのような対応が求められるか、どのモジュールを使うべきかが決定されます。たとえば、Class IIやクリティカル製品では、EU認定のNotified Body(認証機関)による正式な評価が必要となるなど、手続きの負荷も大きく変わります。この分類により、リスクが高い製品ほど、より高度なセキュリティ対策と厳格な評価プロセスが必要となります。それぞれに応じた適合性評価とセキュリティ要件が定められています。以下では、それぞれのカテゴリに属する製品の特徴と、代表的な例を紹介します。 ■ 一般製品(デフォルトカテゴリ) […]