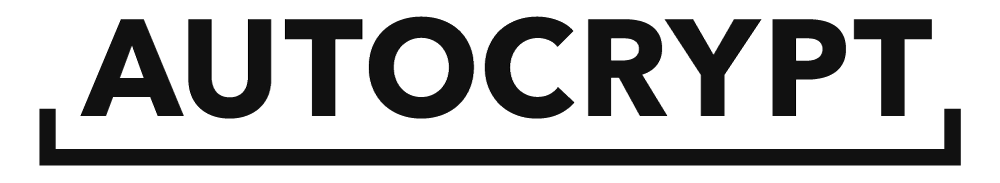- Filter by
- Categories
- Tags
- Authors
- Show all
- All
- 2024年問題
- 5gaa
- A-SPICE
- aee2023
- AIセキュリティ
- Analyzer
- AUTOCRYPT
- AutoCrypt CSTP
- AutoCrypt IDS
- AutoCrypt IVS-TEE
- AutoCrypt SA
- AutoCrypt Security Analyzer
- AUTOCYRPT
- Automotive SPICE
- automotive world
- AUTOSAR
- Autosar Adaptive
- Autosar Classic
- Autoware
- AWF
- Butterfly Key Expansion
- C-ITS
- C-V2X
- CAN通信
- CASE
- CCS & ISO/IEC 15118 Testing Symposium
- CES2023
- CES2024
- CES2025
- CES2026
- CRA
- CRA製品分類
- CSMS
- CSTP
- DEF CON
- DSRC
- E/Eアーキテクチャ
- ECU
- ECUテスティング
- ECU制御
- ECU開発
- EV
- EVS 31
- EVセキュリティ
- EV充電
- forbes asia
- Forbes Asia 100 to Watch
- Fuzz testing
- Fuzzer
- GB
- GB/T
- Gridwiz
- Hardware security module
- Hareware in the loop simulation
- HILS
- HSM
- Hubject
- International Transport Forum
- ISO 15118
- ISO 17978
- ISO 21434
- ISO/IEC 15118
- ISO/SAE 21434
- ISO/TS 5083
- ISO15118
- ITF
- ITS
- ITS Connect
- ITSフォーラム
- japan mobility show
- JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024
- JMS
- Korea IT EXPO
- KOTRA
- MaaS
- MaaS実現
- MBD
- Mobility as a Service
- OmniAir Plugfest
- OSS
- OSSセキュリティ
- OSS分析
- OTA
- OTA(Over The Air)
- PKI
- PKI認証
- Plug and Charge
- Polarion
- popcornsar
- PQC
- PSIRT
- Root CA
- SAE J2945/7
- SBOM
- SCMS
- SDV
- SDV EXPO
- SDVセキュリティ
- SDV時代
- Security Analyzer
- Security Anayzer
- Security Credential Management System
- Security Days
- software update management system
- SOVD
- SUMS
- TARA
- TEE
- TELEDRIVING
- TU-Automotive
- TU-Automotive Awards
- UAM
- UDS
- UN-R155
- UN-R156
- UNR-155
- Urban Air Mobility
- V2G
- V2I
- V2N
- V2P
- V2V
- V2X
- V2Xセキュリティ
- V2Xセキュリティ認証システム
- V2X通信
- Vehicle to grid
- VinCSS
- vSOC
- VTA
- V字モデル
- WP29
- WP29ウェビナー
- アウトクリプト
- インド
- ウェビナー
- オートモーティブワールド
- オープンソースソフトウェア
- オンデマンドウェビナー
- カーボンニュートラル
- クラウドサービス
- コネクティッドカー
- コネクティッドカーセキュリティ
- コネクテッドカー
- コネクテッドカーセキュリティ
- サイバーセキュリティ
- サイバーレジリエンス法
- ジャパンモビリティショー
- スマートファジング
- セキュリティ
- セキュリティ検証
- セキュリティ証明書管理システム
- セキュリティ評価
- ソフトウェアセキュリティインフラ
- ソフトウェアリコール
- ソフトウェア定義型自動車
- ソフトウェア定義型自動車(SDV)
- ソフトウェア部品表
- テクニカルサービス
- デフコン
- トヨタ
- ハードウェアセキュリティモジュール
- パートナーシップ
- ファジング
- ファジングテスト
- ファズテスト
- フリートマネジメントシステム
- ペネトレーションテスト
- ポップコーンザー
- モビリティ
- モビリティサービス
- モビリティ技術
- ルート認証局
- ロボタクシー
- 上場
- 不正行動検知
- 中国サイバーセキュリティ規格
- 交通弱者
- 人とクルマのテクノロジー展
- 位置情報システム
- 侵入検知システム
- 充電インフラ
- 免許制度
- 公開鍵暗号基盤
- 出荷後の自動車にサイバーセキュリティ
- 協調型自動運転
- 協調型高度道路交通システム
- 国際交通フォーラム
- 型式認証
- 安全性検証
- 展示会
- 日本におけるMaaS
- 日本のEV市場
- 日本の自動運転
- 日産
- 日産サクラ
- 標準仕様
- 横浜展示会
- 次世代エアモビリティ
- 次世代モビリティ
- 次世代モビリティ技術展
- 次世代空モビリティ
- 異常行動検知
- 空飛ぶクルマ
- 耐量子計算機暗号
- 脆弱性スキャン
- 脆弱性管理
- 自動車サイバーセキュリティ
- 自動車サイバーセキュリティテスティング
- 自動車サイバーセキュリティテスト
- 自動車サイバーセキュリティ規格
- 自動車セキュリティ
- 自動車セキュリティ検証
- 自動車のリコール
- 自動車ハッキング
- 自動車技術展
- 自動運転
- 自動運転OS
- 自動運転システム
- 自動運転セキュリティ
- 自動運転とEV
- 自動運転トラック
- 自動運転レベル
- 自動運転免許
- 自工会/部工会・サイバーセキュリティガイドライン
- 診断規格
- 車両IDS
- 車両サイバーセキュリティ
- 車両セキュリティ
- 車両向けのファイアウォール
- 車両型式認証
- 車内セキュリティ
- 車載Ethernet
- 車載イーザネット
- 車載システム
- 車載セキュリティ
- 車載ソフトウェア
- 車載組み込みシステム
- 運転免許
- 遠隔型自動運転
- 鍵管理
- 鍵管理統合ソリューション
- 電気自動車
- 電気自動車セキュリティ
- 電気自動車普及
- 韓国次世代モビリティ技術展
- 高度道路交通システム
2025年11月25日
2025年11月25日
近年、自動車業界では「ソフトウェア定義車両(Software-Defined Vehicle:SDV)」という言葉を耳にする機会が増えています。簡単に言うと、SDVはこれまでの「機械としてのクルマ」から、「コンピュータとしてのクルマ」へと大きくシフトしていく流れのことです。その中心にいるのが、高い処理能力と計算能力を備えた高性能コンピュータ(HPC:High Performance Computer)です。クルマの中に、まるでデータセンターのサーバーが載っているようなイメージです。このHPCがあるからこそ、ソフトウェア定義車両(SDV)は周囲の状況をリアルタイムに理解し、自ら判断して動く高い自律性や、クラウドや他の車両・インフラとつながる高い相互接続性を手に入れることができます。 一方で、「車両診断」という観点から見ると、ここには大きなパラダイムシフトが生まれようとしています。これまでの診断基準は、主にセンサーやアクチュエーター、その配線、ECU間をつなぐバスシステムの故障を見つけることに焦点を当ててきました。例えば、「このセンサーの値がおかしい」「このECUとの通信が途切れている」といった、ハードウェアや配線レベルのトラブルを検出することが中心でした。 しかし、HPCによって駆動されるSDVでは、それだけでは不十分となる可能性があります。「どこかの部品が壊れているかどうか」を見るだけではなく、HPC上で動作している複雑なソフトウェアそのものについても、その動作状況を詳細に分析し、異常や不具合を的確に診断する必要があります。つまり、SDV時代の診断は、従来のようなハードウェア中心の「壊れた部品探し」から、「ソフトウェアとハードウェアを一体として捉え、そのライフサイクル全体を管理・検証する診断」へと役割が拡大しています。こうした新しい要求が、従来とは異なる新たな診断基準や診断フレームワークを定義する動きにつながっており、その代表例の一つが本稿で取り上げるSOVD(Service Oriented Vehicle Diagnostics)です。 SOVDとは何か 従来の車両診断は、車載ECU(電子制御ユニット)ごとに個別に設計された診断プロトコル(主にUDS:Unified Diagnostic Services)を使って行われてきました。現在もこのアプローチは広く利用されていますが、近年のSDV化によって車両ソフトウェアが複雑化し、HPCをはじめとする車載コンピュータの役割が拡大する中で、ECU単位での診断だけでは将来の要求を十分に満たしきれないのではないかという課題が指摘されるようになってきました。 この課題に対応するため、業界標準の整備を行う団体であるASAM(Association for Standardisation of Automation and Measuring Systems)がSOVDの標準化プロジェクトを立ち上げました。ASAMは、車両の診断・試験・検証に関する標準的な仕様を策定し、国際的に普及させることで、自動車メーカーやサプライヤー間の製品やサービスの互換性を高めつつ、診断の高度化と効率化を促進している団体です。SOVD(Service Oriented Vehicle Diagnostics)は、その名のとおり車両診断を「サービス」として捉え直すための標準です。従来の診断では、診断テスターと各ECUが直接対話し、UDS(ISO 14229)などのプロトコルを用いてECU単位でDTCを読み出したり、計測値を取得したり、ソフトウェアを書き換えたりしていました。これに対してSOVDは、車両内に存在する診断機能や状態情報を「サービス群」として抽象化し、そのサービスに対して工場の診断機器、クラウド上のバックエンドシステム、HPC上で動作する車内アプリケーションなど、さまざまなクライアントが共通のインターフェースとデータモデルでアクセスできるようにすることを目指します。言い換えれば、車両全体を「診断サービスを提供するプラットフォーム」と見なし、その入り口を統一するためのAPI仕様がSOVDです。なお、ASAMで策定されたSOVDの内容は、現在ISO […]