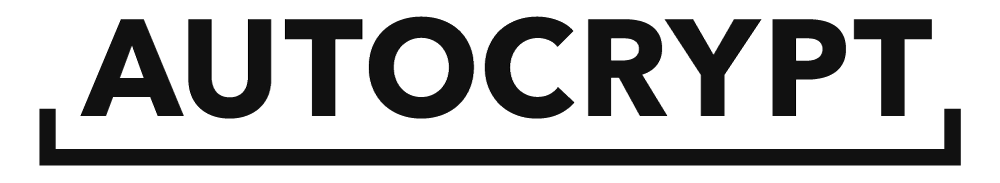- Filter by
- Categories
- Tags
- Authors
- Show all
- All
- 2024年問題
- 5gaa
- A-SPICE
- aee2023
- AIセキュリティ
- Analyzer
- AUTOCRYPT
- AutoCrypt CSTP
- AutoCrypt IDS
- AutoCrypt IVS-TEE
- AutoCrypt SA
- AutoCrypt Security Analyzer
- AUTOCYRPT
- Automotive SPICE
- automotive world
- AUTOSAR
- Autosar Adaptive
- Autosar Classic
- Autoware
- AWF
- Butterfly Key Expansion
- C-ITS
- C-V2X
- CAN通信
- CASE
- CCS & ISO/IEC 15118 Testing Symposium
- CES2023
- CES2024
- CES2025
- CES2026
- CRA
- CRA製品分類
- CSMS
- CSTP
- DEF CON
- DSRC
- E/Eアーキテクチャ
- ECU
- ECUテスティング
- ECU制御
- ECU開発
- EV
- EVS 31
- EVセキュリティ
- EV充電
- forbes asia
- Forbes Asia 100 to Watch
- Fuzz testing
- Fuzzer
- GB
- GB/T
- Gridwiz
- Hardware security module
- Hareware in the loop simulation
- HILS
- HSM
- Hubject
- International Transport Forum
- ISO 15118
- ISO 17978
- ISO 21434
- ISO/IEC 15118
- ISO/SAE 21434
- ISO/TS 5083
- ISO15118
- ITF
- ITS
- ITS Connect
- ITSフォーラム
- japan mobility show
- JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024
- JMS
- Korea IT EXPO
- KOTRA
- MaaS
- MaaS実現
- MBD
- Mobility as a Service
- OmniAir Plugfest
- OSS
- OSSセキュリティ
- OSS分析
- OTA
- OTA(Over The Air)
- PKI
- PKI認証
- Plug and Charge
- Polarion
- popcornsar
- PQC
- PSIRT
- Root CA
- SAE J2945/7
- SBOM
- SCMS
- SDV
- SDV EXPO
- SDVセキュリティ
- SDV時代
- Security Analyzer
- Security Anayzer
- Security Credential Management System
- Security Days
- software update management system
- SOVD
- SUMS
- TARA
- TEE
- TELEDRIVING
- TU-Automotive
- TU-Automotive Awards
- UAM
- UDS
- UN-R155
- UN-R156
- UNR-155
- Urban Air Mobility
- V2G
- V2I
- V2N
- V2P
- V2V
- V2X
- V2Xセキュリティ
- V2Xセキュリティ認証システム
- V2X通信
- Vehicle to grid
- VinCSS
- vSOC
- VTA
- V字モデル
- WP29
- WP29ウェビナー
- アウトクリプト
- インド
- ウェビナー
- オートモーティブワールド
- オープンソースソフトウェア
- オンデマンドウェビナー
- カーボンニュートラル
- クラウドサービス
- コネクティッドカー
- コネクティッドカーセキュリティ
- コネクテッドカー
- コネクテッドカーセキュリティ
- サイバーセキュリティ
- サイバーレジリエンス法
- ジャパンモビリティショー
- スマートファジング
- セキュリティ
- セキュリティ検証
- セキュリティ証明書管理システム
- セキュリティ評価
- ソフトウェアセキュリティインフラ
- ソフトウェアリコール
- ソフトウェア定義型自動車
- ソフトウェア定義型自動車(SDV)
- ソフトウェア部品表
- テクニカルサービス
- デフコン
- トヨタ
- ハードウェアセキュリティモジュール
- パートナーシップ
- ファジング
- ファジングテスト
- ファズテスト
- フリートマネジメントシステム
- ペネトレーションテスト
- ポップコーンザー
- モビリティ
- モビリティサービス
- モビリティ技術
- ルート認証局
- ロボタクシー
- 上場
- 不正行動検知
- 中国サイバーセキュリティ規格
- 交通弱者
- 人とクルマのテクノロジー展
- 位置情報システム
- 侵入検知システム
- 充電インフラ
- 免許制度
- 公開鍵暗号基盤
- 出荷後の自動車にサイバーセキュリティ
- 協調型自動運転
- 協調型高度道路交通システム
- 国際交通フォーラム
- 型式認証
- 安全性検証
- 展示会
- 日本におけるMaaS
- 日本のEV市場
- 日本の自動運転
- 日産
- 日産サクラ
- 標準仕様
- 横浜展示会
- 次世代エアモビリティ
- 次世代モビリティ
- 次世代モビリティ技術展
- 次世代空モビリティ
- 異常行動検知
- 空飛ぶクルマ
- 耐量子計算機暗号
- 脆弱性スキャン
- 脆弱性管理
- 自動車サイバーセキュリティ
- 自動車サイバーセキュリティテスティング
- 自動車サイバーセキュリティテスト
- 自動車サイバーセキュリティ規格
- 自動車セキュリティ
- 自動車セキュリティ検証
- 自動車のリコール
- 自動車ハッキング
- 自動車技術展
- 自動運転
- 自動運転OS
- 自動運転システム
- 自動運転セキュリティ
- 自動運転とEV
- 自動運転トラック
- 自動運転レベル
- 自動運転免許
- 自工会/部工会・サイバーセキュリティガイドライン
- 診断規格
- 車両IDS
- 車両サイバーセキュリティ
- 車両セキュリティ
- 車両向けのファイアウォール
- 車両型式認証
- 車内セキュリティ
- 車載Ethernet
- 車載イーザネット
- 車載システム
- 車載セキュリティ
- 車載ソフトウェア
- 車載組み込みシステム
- 運転免許
- 遠隔型自動運転
- 鍵管理
- 鍵管理統合ソリューション
- 電気自動車
- 電気自動車セキュリティ
- 電気自動車普及
- 韓国次世代モビリティ技術展
- 高度道路交通システム
2025年10月31日
2025年10月31日
量子コンピューターの急速な進化により、私たちのデジタル社会を支えてきた暗号技術はかつてない危機に直面しています。特に、コネクテッドカーや自動運転車が普及する自動車業界では、その影響が極めて大きくなると予測されています。本稿では、量子コンピューターによって生じる脅威とそれに対抗する「耐量子計算機暗号(Post-Quantum Cryptography:PQC)」の必要性、さらには日本を含む各国の取り組みについて解説します。 PQCとは何か 耐量子計算機暗号(Post-Quantum Cryptography:PQC)は量子コンピューターによる攻撃にも耐えられるよう設計された新しい暗号技術です。量子暗号通信のように量子現象を利用するのではなく、現在のコンピューター上で動作し、既存のシステムと互換性を保ちながら安全性を確保することを目的としています。 量子コンピューターがもたらす暗号の危機 現在、広く使われている素因数分解に基づく暗号方式(Rivest Shamir Adleman:RSA)および楕円曲線暗号(ECC)は素因数分解の困難さ・離散対数問題の困難さなどの数学的問題に依存した暗号方式です。これらは従来型コンピューターでは解読に数百万年を要するほど安全とされてきました。しかし、量子コンピューターが実用化されれば事情は一変します。ショアのアルゴリズム(量子アルゴリズム)を活用することで、RSA-2048やECC-256といった暗号は数時間で解読可能になると予測されています。専門家によれば、2030年代半ばには暗号解読ができる「暗号的に関連する量子コンピューター」が登場する可能性があります。 さらに懸念されるのが「Harvest Now, Decrypt Later(今収集し、後で解読する)」攻撃です。これは、現在暗号化されている重要データを大量に収集し、量子コンピューターが実用化された後に解読を試みる手法です。企業の知的財産、R&Dデータ、または自動車関連の設計情報など、長期間価値を持つデータほどリスクが高くなります。 新しい暗号方式の標準化:NISTの取り組み 暗号が量子計算機により破られるリスクに対処するには、単に「新しい暗号」を用意するだけでは不十分です。(1) 鍵共有(キー合意)の置き換え、(2) 電子署名の置き換え、(3) 既存プロトコルへの統合と段階移行(ハイブリッド)、(4) 将来の更新に耐える暗号アジリティ—少なくともこの四点を満たす体系的な対策が必要でした。 この要件に応えるかたちで、米国のNISTは2016年にPQC標準化プロジェクトを開始し、複数ラウンドの公開評価を経て2024年8月に鍵共有用のML-KEM(FIPS 203)、署名用のML-DSA(FIPS 204)とSLH-DSA(FIPS 205)を最終標準として公表しました。これにより、従来のRSA/ECCが担っていた役割に対する量子耐性の「正規の後継部品」が初めて揃ったことになります。 […]