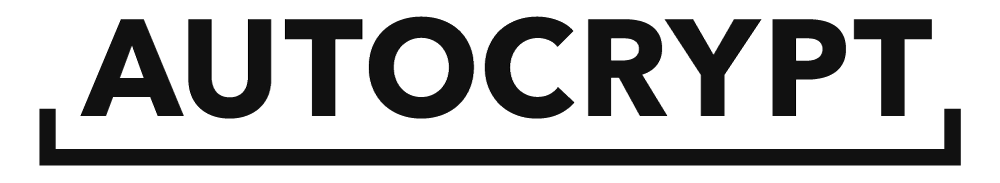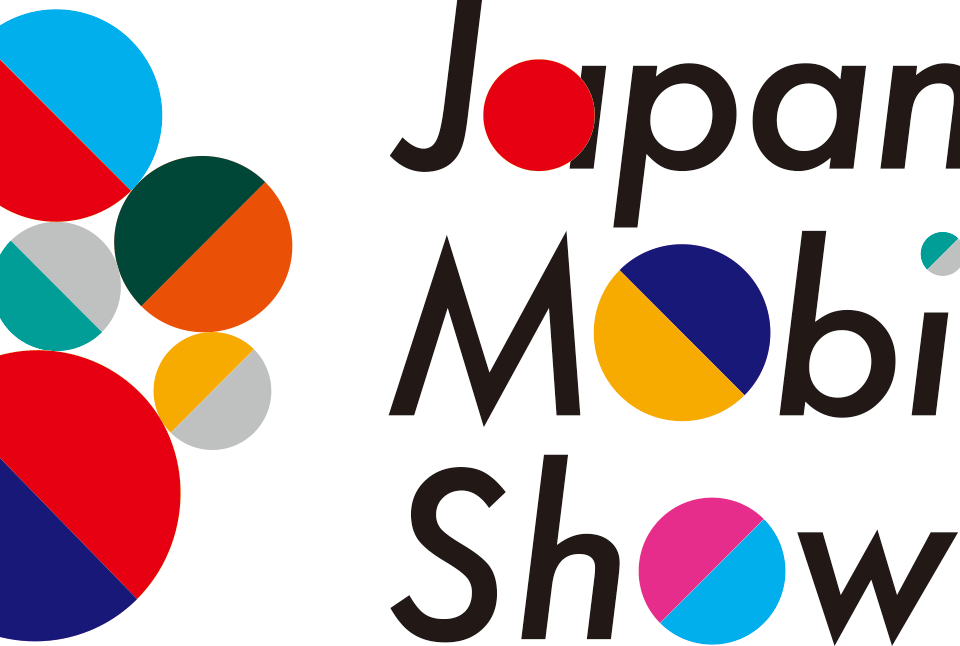Ťá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- Filter by
- Categories
- Tags
- Authors
- Show all
- All
- 5gaa
- A-SPICE
- aee2023
- Analyzer
- AUTOCRYPT
- AutoCrypt CSTP
- AutoCrypt IDS
- AutoCrypt IVS-TEE
- AutoCrypt SA
- AutoCrypt Security Analyzer
- AUTOCYRPT
- Automotive SPICE
- automotive world
- AUTOSAR
- Autosar Adaptive
- Autosar Classic
- Autoware
- AWF
- Butterfly Key Expansion
- C-ITS
- C-V2X
- CANťÄöšŅ°
- CASE
- CCS & ISO/IEC 15118 Testing Symposium
- CES2023
- CES2024
- CES2025
- CRA
- CRAŤ£ĹŚďĀŚąÜť°ě
- CSMS
- CSTP
- DEF CON
- DSRC
- E/E„āĘ„Éľ„ā≠„ÉÜ„āĮ„ÉĀ„É£
- ECU
- ECU„ÉÜ„āĻ„ÉÜ„ā£„É≥„āį
- ECUŚą∂Śĺ°
- ECUťĖčÁôļ
- EV
- EVS 31
- EV„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- EVŚÖÖťõĽ
- forbes asia
- Forbes Asia 100 to Watch
- Fuzz testing
- GB
- GB/T
- Gridwiz
- Hardware security module
- Hareware in the loop simulation
- HILS
- HSM
- Hubject
- International Transport Forum
- ISO 15118
- ISO 21434
- ISO/IEC 15118
- ISO/SAE 21434
- ISO15118
- ITF
- ITS
- ITS Connect
- ITS„Éē„ā©„Éľ„É©„Ɇ
- japan mobility show
- JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2024
- JMS
- Korea IT EXPO
- KOTRA
- MaaS
- MaaSŚģüÁŹĺ
- MBD
- Mobility as a Service
- OmniAir Plugfest
- OSS
- OSS„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- OSSŚąÜśěź
- OTAÔľąOver The AirÔľČ
- PKI
- PKIŤ™ćŤ®ľ
- Plug and Charge
- Polarion
- popcornsar
- PSIRT
- Root CA
- SAE J2945/7
- SBOM
- SCMS
- SDV
- SDV EXPO
- SDV„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- SDVśôāšĽ£
- Security Analyzer
- Security Anayzer
- Security Credential Management System
- Security Days
- software update management system
- SUMS
- TARA
- TEE
- TELEDRIVING
- TU-Automotive
- TU-Automotive Awards
- UAM
- UN-R155
- UN-R156
- UNR-155
- Urban Air Mobility
- V2G
- V2I
- V2N
- V2P
- V2V
- V2X
- V2X„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- V2X„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť™ćŤ®ľ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ
- V2XťÄöšŅ°
- Vehicle to grid
- VinCSS
- vSOC
- VTA
- VŚ≠ó„ÉĘ„Éá„Éę
- WP29
- WP29„ā¶„āß„Éď„Éä„Éľ
- „āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éą
- „ā§„É≥„ÉČ
- „ā™„Éľ„Éą„ÉĘ„Éľ„ÉÜ„ā£„ÉĖ„ÉĮ„Éľ„Éę„ÉČ
- „ā™„Éľ„Éó„É≥„āĹ„Éľ„āĻ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ
- „ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČ„ā¶„āß„Éď„Éä„Éľ
- „āę„Éľ„Éú„É≥„Éč„É•„Éľ„Éą„É©„Éę
- „āĮ„É©„ā¶„ÉČ„āĶ„Éľ„Éď„āĻ
- „ā≥„Éć„āĮ„ÉÜ„ā£„ÉÉ„ÉČ„āę„Éľ
- „ā≥„Éć„āĮ„ÉÜ„ā£„ÉÉ„ÉČ„āę„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- „ā≥„Éć„āĮ„ÉÜ„ÉÉ„ÉČ„āę„Éľ
- „ā≥„Éć„āĮ„ÉÜ„ÉÉ„ÉČ„āę„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- „āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- „āĶ„ā§„Éź„Éľ„ɨ„āł„É™„ā®„É≥„āĻś≥ē
- „āł„É£„ÉĎ„É≥„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£„ā∑„Éß„Éľ
- „āĻ„Éě„Éľ„Éą„Éē„ā°„āł„É≥„āį
- „āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- „āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť®ľśėéśõłÁģ°ÁźÜ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ
- „āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť©ēšĺ°
- „āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ā§„É≥„Éē„É©
- „āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„É™„ā≥„Éľ„Éę
- „āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘŚģöÁĺ©ŚěčŤá™ŚčēŤĽä
- „āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘŚģöÁĺ©ŚěčŤá™ŚčēŤĽäÔľąSDVÔľČ
- „āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āʝɮŚďĀŤ°®
- „ÉÜ„āĮ„Éč„āę„Éę„āĶ„Éľ„Éď„āĻ
- „Éá„Éē„ā≥„É≥
- „Éą„É®„āŅ
- „ÉŹ„Éľ„ÉČ„ā¶„āß„āĘ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ÉĘ„āł„É•„Éľ„Éę
- „ÉĎ„Éľ„Éą„Éä„Éľ„ā∑„ÉÉ„Éó
- „Éē„ā°„āł„É≥„āį
- „Éē„ā°„āł„É≥„āį„ÉÜ„āĻ„Éą
- „Éē„ā°„āļ„ÉÜ„āĻ„Éą
- „Éē„É™„Éľ„Éą„Éě„Éć„āł„É°„É≥„Éą„ā∑„āĻ„É܄Ɇ
- „Éö„Éć„Éą„ɨ„Éľ„ā∑„Éß„É≥„ÉÜ„āĻ„Éą
- „ÉĚ„ÉÉ„Éó„ā≥„Éľ„É≥„ā∂„Éľ
- „ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£
- „ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£„āĶ„Éľ„Éď„āĻ
- „ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£śäÄŤ°ď
- „Éę„Éľ„ÉąŤ™ćŤ®ľŚĪÄ
- šłäŚ†ī
- šłćś≠£Ť°ĆŚčēś§úÁü•
- šł≠ŚõĹ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť¶Źś†ľ
- šļ§ťÄöŚľĪŤÄÖ
- šļļ„Ā®„āĮ„Éę„Éě„Āģ„ÉÜ„āĮ„Éé„É≠„āł„ÉľŚĪē
- šĹćÁĹģśÉÖŚ†Ī„ā∑„āĻ„É܄Ɇ
- šĺĶŚÖ•ś§úÁü•„ā∑„āĻ„É܄Ɇ
- ŚÖÖťõĽ„ā§„É≥„Éē„É©
- ŚÖ据ĪŚą∂Śļ¶
- ŚÖ¨ťĖčťćĶśöóŚŹ∑ŚüļÁõ§
- ŚáļŤć∑ŚĺĆ„ĀģŤá™ŚčēŤĽä„Āę„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- ŚćĒŤ™ŅŚěčŤá™ŚčēťĀ荼Ę
- ŚćĒŤ™ŅŚěčťęėŚļ¶ťĀďŤ∑Įšļ§ťÄö„ā∑„āĻ„É܄Ɇ
- ŚõĹťöõšļ§ťÄö„Éē„ā©„Éľ„É©„Ɇ
- Śě茾ŹŤ™ćŤ®ľ
- ŚĪēÁ§ļšľö
- śó•śú¨„Āę„Āä„ĀĎ„āčMaaS
- śó•śú¨„ĀģEVŚłāŚ†ī
- śó•ÁĒ£
- śó•ÁĒ£„āĶ„āĮ„É©
- ś®ôśļĖšĽēśßė
- ś®™śĶúŚĪēÁ§ļšľö
- ś¨°šłĖšĽ£„ā®„āĘ„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£
- ś¨°šłĖšĽ£„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£
- ś¨°šłĖšĽ£„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£śäÄŤ°ďŚĪē
- ś¨°šłĖšĽ£Á©ļ„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£
- ÁēįŚłłŤ°ĆŚčēś§úÁü•
- Á©ļť£õ„Ā∂„āĮ„Éę„Éě
- ŤĄÜŚľĪśÄß„āĻ„ā≠„É£„É≥
- ŤĄÜŚľĪśÄßÁģ°ÁźÜ
- Ťá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- Ťá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ÉÜ„āĻ„ÉÜ„ā£„É≥„āį
- Ťá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ÉÜ„āĻ„Éą
- Ťá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť¶Źś†ľ
- Ťá™ŚčēŤĽä„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- Ťá™ŚčēŤĽä„Āģ„É™„ā≥„Éľ„Éę
- Ťá™ŚčēŤĽä„ÉŹ„ÉÉ„ā≠„É≥„āį
- Ťá™ŚčēŤĽäśäÄŤ°ďŚĪē
- Ťá™ŚčēťĀ荼Ę
- Ťá™ŚčēťĀ荼ĘOS
- Ťá™ŚčēťĀ荼ʄāĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- Ťá™ŚčēťĀ荼ʄĀ®EV
- Ťá™ŚčēťĀ荼ʄɨ„Éô„Éę
- Ťá™ŚčēťĀ荼ʌÖ据Ī
- Ťá™Ś∑•šľöÔľŹťÉ®Ś∑•šľö„ÉĽ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥
- ŤĽäšł°IDS
- ŤĽäšł°„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- ŤĽäšł°„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- ŤĽäšł°ŚźĎ„ĀĎ„Āģ„Éē„ā°„ā§„āĘ„ā¶„ā©„Éľ„Éę
- ŤĽäšł°Śě茾ŹŤ™ćŤ®ľ
- ŤĽäŚÜÖ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- ŤĽäŤľČEthernet
- ŤĽäŤľČ„ā§„Éľ„ā∂„Éć„ÉÉ„Éą
- ŤĽäŤľČ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ
- ŤĽäŤľČ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- ŤĽäŤľČ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ
- ŤĽäŤľČÁĶĄ„ĀŅŤĺľ„ĀŅ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ
- ťĀ荼ʌÖ据Ī
- ťĀ†ťöĒŚěčŤá™ŚčēťĀ荼Ę
- ťćĶÁģ°ÁźÜ
- ťćĶÁģ°ÁźÜÁĶĪŚźą„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥
- ťõĽśįóŤá™ŚčēŤĽä
- ťõĽśįóŤá™ŚčēŤĽä„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
- ťõĽśįóŤá™ŚčēŤĽäśôģŚŹä
- ťüďŚõĹś¨°šłĖšĽ£„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£śäÄŤ°ďŚĪē
- ťęėŚļ¶ťĀďŤ∑Įšļ§ťÄö„ā∑„āĻ„É܄Ɇ
2025ŚĻī6śúą24śó•
2025ŚĻī6śúą24śó•
śó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēŤĽäÁĒ£ś•≠„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„ÄĆŚģČŚÖ®„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ®ÄŤĎČ„ĀģśĄŹŚĎ≥„ĀĆś†ĻŚļē„Āč„āČŚ§Č„āŹ„āć„ĀÜ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āĺ„Āß„Āģ„ÄĆŚģČŚÖ®„Äć„Ā®„ĀĮ„ÄĀŤ°ĚÁ™Āśôā„Āģšļļ„ĀģšŅĚŤ≠∑„āĄšļčśēÖ„Āģšļąťė≤„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüÁČ©ÁźÜÁöĄŚĀīťĚĘ„āíšł≠ŚŅÉ„Ā®„Āó„Āü„āā„Āģ„Āß„Āó„Āü„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„ā≥„Éć„āĮ„ÉÜ„ÉÉ„ÉČ„āę„Éľ„āĄ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„ÉĽ„Éá„Éē„ā°„ā§„É≥„ÉČ„ÉĽ„Éď„Éľ„āĮ„ÉęÔľąSDVԾȄĀģśú¨ś†ľÁöĄ„Ā™śôģŚŹä„āíŤÉĆśôĮ„Āę„ÄĀ„Éá„āł„āŅ„ÉꝆėŚüü„Āß„ĀģšŅ°ť†ľśÄß„ĀĆśĖį„Āü„Ā™„ÄĆŚģČŚÖ®„Äć„Āģšł≠ś†ł„Ā®„Ā™„āä„Ā§„Ā§„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁŹĺŚú®„Āģ„āĮ„Éę„Éě„ĀĮ„ÄĀ1ŚĄĄŤ°Ć„āíŤ∂Ö„Āą„āč„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„ā≥„Éľ„ÉČ„Āę„āą„Ā£„Ā¶Śą∂Śĺ°„Āē„āĆ„ÄĀŚłłśôā„Éć„ÉÉ„Éą„ÉĮ„Éľ„āĮ„Āęśé•Á∂ö„Āē„āĆ„Āü‚ÄúŤĶį„āčITś©üŚô®‚ÄĚ„Ā®„āāŚĎľ„Āį„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģÁä∂ś≥Ā„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀĮ„āā„ĀĮ„āĄśÉÖŚ†Ī„ā∑„āĻ„É܄ɆťÉ®ťĖÄ„ĀģŚįāťĖÄť†ėŚüü„Āę„Ā®„Ā©„Āĺ„āčŚēŹť°Ć„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„ÄāŤĽäšł°Śą∂Śĺ°„ĀģšĻó„Ā£ŚŹĖ„āä„Āę„āą„āčšļļŚĎĹ„Āł„Āģ„É™„āĻ„āĮ„ÄĀŚ§ßŤ¶Źś®°„Ā™„É™„ā≥„Éľ„ÉęŚĮĺŚŅú„ÄĀ„Āē„āČ„Āę„ĀĮšľĀś•≠„ÉĖ„É©„É≥„ÉČ„Āł„ĀģÁĒöŚ§ß„Ā™šŅ°ť†ľŚĖ™Ś§Ī„ĀęÁõīÁĶź„Āô„āč„ÄĀÁĶĆŚĖ∂„É™„āĻ„āĮ„ĀĚ„Āģ„āā„Āģ„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āē„āČ„Āę„ÄĀŤĄÖŚ®Ā„ĀĮšłÄŚŹį„ĀģŤĽäšł°„Āę„Ā®„Ā©„Āĺ„āČ„Āö„ÄĀśēįÁôĺÁ§ĺ„Āꌏä„Ā∂„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„ĀĆŤ§áťõĎ„ĀęťĖĘšłé„Āô„āč„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āęś≥ĘŚŹä„Āô„āčśßčťÄ†ÁöĄ„É™„āĻ„āĮ„Āß„Āô„Äāśó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆ„ĀĮ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť™≤ť°Ć„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶ŚÄčÁ§ĺ„ĀģŚĮĺŚŅú„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀś•≠ÁēĆŚÖ®šĹď„Āß„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£šĹ∂„ĀģŚļēšłä„Āí„ĀꌏĖ„āäÁĶĄ„āď„Āß„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā „ĀĚ„Āģšł≠ŚŅÉ„Āę„Āā„āč„Āģ„ĀĆ„ÄĀšĽ•šłč„Āģ2„Ā§„ĀģśüĪ„Āß„ĀôÔľö ś•≠ÁēĆś®™śĖ≠„Āß„ĀģťÄ£śźļ„Ā®ś®ôśļĖŚĆĖ „āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āł„ĀģŚĆÖśč¨ÁöĄśĒĮśŹī „Āď„āĆ„āČ„ĀĮŚćėÁ訄ĀģśĖĹÁ≠Ė„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀÁõłšļí„ĀęťÄ£Śčē„Āó„Ā™„ĀĆ„āČśó•śú¨„Āģ„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£ÁĒ£ś•≠„Āģ‚ÄúśĖį„Āó„ĀĄŚģČŚÖ®šŅĚťöú‚ÄĚ„āíśßčÁĮČ„Āô„āčśě†ÁĶĄ„ĀŅ„Ā®Ť®Ä„Āą„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āď„Āß„ĀĮ„ÄĀ„Āď„āĆ„āČ2„Ā§„ĀģśüĪ„ā퍼ł„Āę„ÄĀśó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆ„ĀĆťÄ≤„āĀ„āčśúÄśĖį„ĀģŚŹĖ„āäÁĶĄ„ĀŅ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶Ť™¨śėé„Āó„Āĺ„Āô„Äā ÁąÜÁôļÁöĄ„Āęśąźťē∑„Āô„ā茳āŚ†ī„Ā®ÁŹĺŚģüŚĆĖ„Āô„ā荥֌®Ā śó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚłāŚ†ī„ĀĮ„ÄĀ„Āč„Ā§„Ā¶„Ā™„ĀĄśąźťē∑„āíťĀā„Āí„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāImarc„ĀģŚłāŚ†īŤ™ŅśüĽ„Āę„āą„āč„Ā®„ÄĀ2024ŚĻī„Āę2ŚĄĄ1,900šłá„ÉČ„ÉꍶŹś®°„Āß„Āā„Ā£„ĀüŚłāŚ†ī„ĀĮ„ÄĀ2033ŚĻī„Āĺ„Āß„Āę„ĀĮ7ŚĄĄ9,500šłá„ÉČ„Éę„ĀęťĀĒ„Āô„āč„Ā®šļąśł¨„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĻīŚĻ≥ŚĚáśąźťē∑ÁéáÔľąCAGRԾȄĀĮ15.4%„ĀęťĀĒ„Āô„ā荶čŤĺľ„ĀŅ„Āß„Āô„ÄāŚłāŚ†ī„ĀƜĕśč°Ś§ß„Āô„āčÁźÜÁĒĪ„ĀģšłÄ„Ā§„ĀĮ„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„ĀĆ„āā„ĀĮ„āĄśÉ≥Śģöšłä„Āģ„É™„āĻ„āĮ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀšļčś•≠„ĀęŚĹĪťüŅ„ā팏ä„Āľ„ĀôŤĄÖŚ®Ā„Ā®„Āó„Ā¶ť°ēŚú®ŚĆĖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„Āę„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā2022ŚĻī„ÄĀ„Éą„É®„āŅŤá™ŚčēŤĽä„ĀģšłÄś¨°„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„Āß„Āā„āčŚįŹŚ≥∂„Éó„ɨ„āĻŚ∑•ś•≠„ĀĆ„É©„É≥„āĶ„Ɇ„ā¶„āß„āĘśĒĽśíÉ„ā팏ó„ĀĎ„Ā¶ŚõĹŚÜÖ14Ś∑•Ś†ī„ĀĆŚÖ®ťĚĘŚĀúś≠Ę„Āó„Āüšļ蚼∂„ĀĮ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„ĀģŤĄÜŚľĪśÄß„ĀĆšļčś•≠Á∂ôÁ∂ö„ĀęÁõīÁĶź„Āô„āč„Āď„Ā®„āíś•≠ÁēĆŚÖ®šĹď„Āę„Ā§„Āć„Ā§„ĀĎ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ2022ŚĻī„Āę„ĀĮ„Éá„É≥„āĹ„Éľ„Āģ„ÉČ„ā§„ÉĄś≥ēšļļ„ĀĆ„ÉŹ„ÉÉ„āę„ÉľťõÜŚõ£„ÄĆPandora„Äć„ĀģśĒĽśíÉ„ā팏ó„ĀĎ„āč„Ā™„Ā©„ÄĀ„āį„É≠„Éľ„Éź„Éę„Ā™„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„ĀĆŚłł„Āꍥ֌®Ā„Āęśôí„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŤ≠¶ŚĮüŚļĀ„ĀģŚ†ĪŚĎä„Āę„āą„āĆ„Āį„ÄĀ2022ŚĻī„ĀģŚõĹŚÜÖ„É©„É≥„āĶ„Ɇ„ā¶„āß„āĘŤĘęŚģ≥230šĽ∂„Āģ„ĀÜ„Ā°„ÄĀŤ£ĹťÄ†ś•≠„ĀĆ32.6%„Ā®śúÄŚ§ö„āíŚć†„āĀ„Āĺ„Āó„Āü„ÄāŤ≠¶ŚĮüŚļĀ„ĀģŚ†ĪŚĎä„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„ĀģŚüļŚĻĻÁĒ£ś•≠„ĀģšłÄ„Ā§„Āß„Āā„āčŤá™ŚčēŤĽäÁĒ£ś•≠„āā„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„Āģś®ôÁöĄ„Ā®„Ā™„āäŚĺó„āč„Āď„Ā®„ā팾∑„ĀŹÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāś∑ĪŚąĽ„Ā™ŤĘęŚģ≥„āíśú™ÁĄ∂„Āęťė≤„Āé„ÄĀšļčś•≠Á∂ôÁ∂öśÄß„āíÁĘļšŅĚ„Āô„āč„Āü„āĀ„Āę„āāšĽä„Āď„ĀĚšĹďÁ≥ĽÁöĄ„Āߌ†ÖÁČĘ„Ā™„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„ĀģśßčÁĮČ„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā śĒŅŚļú„ĀģŚľ∑Śäõ„Ā™ŚĺĆśäľ„Āó„Ā®ś≥ēŤ¶ŹŚą∂ „Āď„ĀÜ„Āó„ĀüŤĄÖŚ®Ā„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀśó•śú¨śĒŅŚļú„āāś≥ēŤ¶ŹŚą∂„ĀģŚĀīťĚĘ„Āč„āČŚĮĺŚŅú„ā팾∑ŚĆĖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āģšł≠ś†ł„Ā®„Ā™„āč„Āģ„ĀĆ„ÄĀŚõĹťÄ£„ĀģŤá™ŚčēŤĽäŚüļśļĖŤ™ŅŚíĆšłĖÁēĆ„Éē„ā©„Éľ„É©„ɆԾąWP29ԾȄĀßśé°śäě„Āē„āĆ„Āü„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ś≥ēŤ¶ŹÔľąUN-R155ԾȄĀß„Āô„Äāśó•śú¨„Āß„ĀĮ„Āď„ĀģUN-R155„ĀĆŤŅÖťÄü„ĀęŚõĹŚÜÖś≥ēŚą∂ŚĆĖ„Āē„āĆ„ÄĀ2022ŚĻī7śúą„Āč„āČOTAÔľąÁĄ°Á∑ö„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„ɹԾȌĮĺŚŅú„ĀģśĖįŚě荼ä„Āę„ÄĀ2024ŚĻī7śúą„Āč„āČ„ĀĮÁ∂ôÁ∂öÁĒüÁĒ£„Āē„āĆ„āčŚÖ®„Ā¶„ĀģOTAŚĮĺŚŅúŤĽäšł°„ĀęÁĺ©ŚčôŚĆĖ„Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āď„Āģś≥ēŤ¶Ź„Āł„ĀģśļĖśč†„ĀĮ„ÄĀŤá™ŚčēŤĽä„ĀģŤ®≠Ť®ą„Āč„āČŚĽÉś£Ą„ĀęŤá≥„āč„Āĺ„Āß„Āģ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„āíŚģö„āĀ„ĀüŚõĹťöõś®ôśļĖŤ¶Źś†ľ„ÄĆISO/SAE 21434„Äć„Āł„ĀģŚĮĺŚŅú„Ā®ŚĮÜśé•„ĀęťĖĘťÄ£„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀŤá™ŚčēŤĽä„É°„Éľ„āę„ÉľÔľąOEMԾȄĀĮŤá™Á§ĺ„Āģ„ĀŅ„Ā™„āČ„Āö„ÄĀťÉ®ŚďĀ„āíšĺõÁĶ¶„Āô„āč„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„ĀĆťĖčÁôļ„Éó„É≠„āĽ„āĻŚÖ®šĹď„Āß„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„āíÁĘļšŅĚ„Āô„āčÁģ°ÁźÜšĹ∂ÔľąCSMSԾȄāíťĀ©Śąá„ĀęśßčÁĮČ„ÉĽťĀčÁĒ®„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āč„āíŚĮ©śüĽ„Āó„ÄĀŤ®ľśėé„Āô„āčŤ≤¨šĽĽ„āíŤ≤†„ĀÜ„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„ĀĆŚÄčÁ§ĺ„ĀģŚēŹť°Ć„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„ĀߌŹĖ„āäÁĶĄ„āÄ„ĀĻ„ĀćŚŅÖť†ąŤ¶ĀšĽ∂„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Āď„Ā®„ā휥ŹŚĎ≥„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā ś•≠ÁēĆ„ĀģŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™„āĘ„āĮ„ā∑„Éß„É≥ÔľöťÄ£śźļ„ÉĽśĒĮśŹī ŚÄčÁ§ĺ„ĀģŚä™Śäõ„Ā†„ĀĎ„Āß„ĀĮŚĮĺŚŅú„Āó„Āć„āĆ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚÖĪťÄöŤ™ćŤ≠ė„Āģ„āā„Ā®„ÄĀś•≠ÁēĆ„ĀĮŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™ŚćĒŤ™ŅŤ°ĆŚčē„āíŚä†ťÄü„Āē„Āõ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā 1. ś•≠ÁēĆś®™śĖ≠„Āß„ĀģťÄ£śźļ„Ā®ś®ôśļĖŚĆĖ ŚÄčÁ§ĺ„ĀģŚä™Śäõ„Ā†„ĀĎ„Āß„ĀĮŚĮĺŚŅú„Āó„Āć„āĆ„Ā™„ĀĄŤ§áťõĎ„Ā™„āĶ„ā§„Éź„ÉľŤĄÖŚ®Ā„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀśó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆ„ĀĮ„ÄĆÁę∂šļČ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹŚćĒŤ™Ņ„Äć„āíŚüļśú¨„Ā®„Āó„Ā¶ś•≠ÁēĆ„Āß„ĀģťÄ£śźļ„Ā®ś®ôśļĖŚĆĖ„āíŚä†ťÄü„Āē„Āõ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āģšł≠ŚŅÉ„Āę„Āā„āč„Āģ„ĀĆ2021ŚĻī2śúą„Āꍮ≠Áęč„Āē„āĆ„Āü„ÄĆšłÄŤą¨Á§ĺŚõ£ś≥ēšļļśó•śú¨Ťá™ŚčēŤĽäISACÔľąJ-Auto-ISACԾȄÄć„Āß„Āô„ÄāJ-Auto-ISAC„ĀĮ„ÄĀŤ®≠Áęč„Āč„āČ„āŹ„Āö„Āč2ŚĻī„ĀßšľöŚď°šľĀś•≠„ĀĆ100Á§ĺ„āíŤ∂Ö„Āą„ÄĀÁŹĺŚú®„āā„ĀĚ„Āģśēį„ĀĮŚĘó„ĀąÁ∂ö„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚä†ÁõüšľĀś•≠„ĀĮ„ÄĀ„Éą„É®„āŅ„ÄĀ„Éõ„É≥„ÉÄ„ÄĀśó•ÁĒ£„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüšłĽŤ¶ĀŤá™ŚčēŤĽä„É°„Éľ„āę„ÉľÔľąOEMԾȄĀ®„Éá„É≥„āĹ„Éľ„āĄ„āĘ„ā§„ā∑„É≥„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚ§ßśČč„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„ÄĀ„Āē„āČ„Āę„ĀĮŤĽäŤľČ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„āĄŚćäŚįéšĹď„āíśČč„ĀĆ„ĀĎ„āčITšľĀś•≠„Āĺ„Āß„ÄĀś•≠ÁēĆ„āíŤ∂ä„Āą„Ā¶Ś§öŚ≤ź„Āę„āŹ„Āü„āä„Āĺ„Āô„Äā „ĀĚ„ĀģśīĽŚčē„Āģšł≠„ĀßśúÄ„āāťá捶Ā„Ā™„Ā®„Āď„āć„ĀĮŤĄÖŚ®ĀśÉÖŚ†Ī„ĀģŚÖĪśúČ„Āß„Āô„ÄāJ-Auto-ISAC„ĀĮŚõĹŚÜÖŚ§Ė„Āč„āČśúÄśĖį„ĀģŤĄÜŚľĪśÄßśÉÖŚ†Ī„āĄśĒĽśíÉšļčšĺč„ā팏éťõÜ„ÉĽŚąÜśěź„Āó„ÄĀšľöŚď°šľĀś•≠„ĀęŤŅÖťÄü„ĀęŚÖĪśúČ„Āô„āč„ÉŹ„ÉĖ„Ā®„Āó„Ā¶ś©üŤÉĹ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀŚÄčÁ§ĺ„Āߌ•ĎÁīĄ„Āô„āĆ„ĀįŚĻīťĖďśēįŚĄĄŚÜÜ„Āęšłä„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āčťęėšĺ°„Ā™ŤĄÜŚľĪśÄßśÉÖŚ†Ī„āíŚÖĪŚźĆ„Āߍ≥ľŚÖ•„ÉĽŚÖĪśúČ„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀÁĶĆŚĖ∂šĹďŚäõ„Āģťôź„āČ„āĆ„āčšł≠ŚįŹšľĀś•≠„ĀģŤ≤†śčÖ„ā팧ߌĻÖ„ĀꍼŜłõ„Āó„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āģ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺŚŅúŤÉĹŚäõ„ĀģŚźĎšłä„ĀęŤ≤ĘÁĆģ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„ÉľŤĄÖŚ®Ā„ĀęŚĮĺŚŅú„Āô„āč„Āü„āĀ„ÄĀÁźÜšļčšľö„Ā®ťĀčŚĖ∂ŚßĒŚď°šľö„Āģšłč„Āę„ÄĆśäÄŤ°ďŚßĒŚď°šľö„Äć„ÄĆśÉÖŚ†ĪŚŹéťõÜ„ÉĽŚąÜśěź„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąSOCԾȄÄć„ÄĆ„āĶ„ÉĚ„Éľ„Éą„āĽ„É≥„āŅ„Éľ„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚįāťĖÄÁĶĄÁĻĒ„ā퍮≠ÁĹģ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāśäÄŤ°ďŚßĒŚď°šľö„Āß„ĀĮśúÄśĖį„ĀģśĒĽśíÉśČčś≥ē„ĀģŚąÜśěź„āĄťė≤Śĺ°śäÄŤ°ď„ĀģÁ†ĒÁ©∂ťĖčÁôļ„āíśé®ťÄ≤„Āó„ÄĀSOC„ĀĮ„É™„āĘ„Éę„āŅ„ā§„Ɇ„Āß„ĀģŤĄÖŚ®ĀÁõ£Ť¶Ė„Ā®„ā§„É≥„ā∑„Éá„É≥„ÉąŚĮĺŚŅú„āíśčÖŚĹď„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā ŚõĹťöõťÄ£śźļ„āāÁ©ćś•ĶÁöĄ„Āß„ÄĀ2024ŚĻī„Āę„ĀĮÁĪ≥ŚõĹ„ĀģAuto-ISAC„Ā®śÉÖŚ†ĪŚÖĪśúČ„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚćĒŚäõŤ¶öśõłÔľąMOUԾȄāíÁ∑†ÁĶź„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀŚõĹŚĘÉ„āíŤ∂ä„Āą„Ā¶šĽēśéõ„ĀĎ„āČ„āĆ„āč„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀ„āį„É≠„Éľ„Éź„Éę„Ā™Ť¶ĖÁāĻ„Āß„ĀģŤŅÖťÄü„Ā™śÉÖŚ†ĪŚÖĪśúČ„Ā®ŚÖĪŚźĆŚĮĺŚá¶„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āē„āČ„Āę„ÄĀJ-Auto-ISAC„ĀĮś•≠ÁēĆś®ôśļĖ„ĀģÁ≠ĖŚģö„Āę„āāś∑Ī„ĀŹťĖĘšłé„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„ĀģśßčśąźŤ¶ĀÁī†„ā팏ĮŤ¶ĖŚĆĖ„Āô„āč„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āʝɮŚďĀŤ°®ÔľąSBOMԾȄĀģś®ôśļĖŚĆĖ„āíśé®ťÄ≤„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„Āď„āĆ„Āę„āą„ā䍼䚳°„Āęśź≠ŤľČ„Āē„āĆ„ā荧áťõĎ„Ā™„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„ĀģťÄŹśėéśÄß„āíťęė„āĀ„ÄĀŤĄÜŚľĪśÄß„Āģśó©śúüÁôļŤ¶č„Ā®ŤŅÖťÄü„Ā™ŚĮĺŚŅú„ā팏ĮŤÉĹ„Āę„Āô„āčÁģ°ÁźÜšĹ∂„ĀģśßčÁĮČ„āíÁõģśĆá„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀŚįܜ̕„Āģ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„ÉĽ„āĘ„ÉÉ„Éó„Éá„Éľ„ÉąÁģ°ÁźÜÔľąSUMSԾȄĀę„Āä„ĀĄ„Ā¶„āāšłćŚŹĮś¨†„Ā™ŚüļÁõ§„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā „Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Āę„ÄĀJ-Auto-ISAC„ĀĮŚćė„Ā™„āčśÉÖŚ†ĪŚÖĪśúČ„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀśäÄŤ°ďÁ†ĒÁ©∂„ÄĀ„ā§„É≥„ā∑„Éá„É≥„ÉąŚĮĺŚŅúśĒĮśŹī„ÄĀś®ôśļĖŚĆĖ„ÄĀŚõĹťöõťÄ£śźļ„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚ§öŚ≤ź„Āę„āŹ„Āü„āčśīĽŚčē„āíťÄö„Āė„Ā¶śó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆ„Āę„Āä„ĀĎ„āč„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„Āģšł≠ś†łÁöĄ„Ā™ŚĹĻŚČ≤„āíśěú„Āü„Āó„ÄĀśĆĀÁ∂öŚŹĮŤÉĹ„Ā™„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£Á§ĺšľö„ĀģŚģüÁŹĺ„ĀęŤ≤ĘÁĆģ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā 2. „āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āł„ĀģśĒĮśŹī 2022ŚĻī„ĀģŚįŹŚ≥∂„Éó„ɨ„āĻŚ∑•ś•≠„Āł„Āģ„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„ĀĆ„Éą„É®„āŅ„ĀģŚõĹŚÜÖŚÖ®Ś∑•Ś†ī„āíŚĀúś≠Ę„Āē„Āõ„Āüšļ蚼∂„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„ĀģŤĄÜŚľĪśÄß„ĀĆOEM„Āģšļčś•≠Á∂ôÁ∂ö„ĀęÁõīÁĶź„Āô„āč„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜšļčŚģü„āíś•≠ÁēĆŚÖ®šĹď„Āꌾ∑„ĀŹŤ™ćŤ≠ė„Āē„Āõ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āď„Āģšļ蚼∂„āí„Āć„Ā£„Āč„ĀĎ„Āę„ÄĀśó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆ„ĀĮ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āģ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ɨ„Éô„Éę„āíŚļēšłä„Āí„Āô„āč„Āü„āĀ„Āģ„ÄĀŚĆÖśč¨ÁöĄ„Ā™śĒĮśŹīšĹ∂„ĀģśßčÁĮČ„āíśÄ•„ĀĄ„Āß„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā „ĀĚ„ĀģŚüļÁõ§„Ā®„Ā™„āč„Āģ„ĀĆ„ÄĀśó•śú¨Ťá™ŚčēŤĽäŚ∑•ś•≠šľöÔľąJAMAԾȄĀ®śó•śú¨Ťá™ŚčēŤĽäťÉ®ŚďĀŚ∑•ś•≠šľöÔľąJAPIAԾȄĀĆťÄ£śźļ„Āó„Ā¶Á≠ĖŚģö„Āó„Āü„ÄƍᙌčēŤĽäÁĒ£ś•≠„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„Äć„Āß„Āô„Äā„Āď„Āģ„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„ĀĮ„ÄĀÁĶĆśłąÁĒ£ś•≠ÁúĀ„ĀƜ鮝Ä≤„Āô„āč„ÄĆ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„ÉĽ„Éē„ā£„āł„āę„Éę„ÉĽ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„Éē„ɨ„Éľ„Ɇ„ÉĮ„Éľ„āĮÔľąCPSFԾȄÄć„āíŤá™ŚčēŤĽäÁĒ£ś•≠ŚźĎ„ĀĎ„ĀęŚÖ∑šĹďŚĆĖ„Āó„Āü„āā„Āģ„Āß„Āā„āä„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āß„Āģ„É™„āĻ„āĮÁģ°ÁźÜ„Ā®ŚĮĺÁ≠Ė„Āģś®ôśļĖŚĆĖ„āíÁõģśĆá„Āô„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā „Āď„Āģ„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„ĀģśúÄŚ§ß„ĀģÁČĻŚĺī„ĀĮŚģĆśąźŤĽä„É°„Éľ„āę„Éľ„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„Āč„āČŚįŹŤ¶Źś®°„Ā™šļčś•≠ŤÄÖ„Āĺ„Āß„ÄĀśēįŚćÉÁ§ĺ„Āꌏä„Ā∂„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„ĀģŚÖ®ťöéŚĪ§„āíŚĮĺŤĪ°„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„āčÁāĻ„Āß„Āô„Äā„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„Āß„ĀĮŚźĄšľĀś•≠„ĀĆťĀĶŚģą„Āô„ĀĻ„Āć„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ėť†ÖÁõģ„ĀĆŚÖ∑šĹďÁöĄ„ĀęÁ§ļ„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀšľĀś•≠„ĀĮ„Āď„āĆ„āíÁĒ®„ĀĄ„Ā¶Ťá™Á§ĺ„Āģ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ɨ„Éô„Éę„āíŤá™Ś∑ĪŤ©ēšĺ°„Āó„ÄĀÁ∂ôÁ∂öÁöĄ„Ā™śĒĻŚĖĄ„āíŚõ≥„āč„Āď„Ā®„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„Āę„āą„āä„ÄĀšł≠ŚįŹšľĀś•≠„ĀģśĄŹŤ≠ė„Ā®ŚĮĺŚŅú„ā팾ē„Āćšłä„Āí„Ā¶„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„ĀģŚĮĺŚŅúŚäõ„āíťęė„āĀ„āč„Āď„Ā®„āíÁčô„ĀĄ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„āíÁ§ļ„Āô„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚģüŚäĻśÄß„āíťęė„āĀ„āč„Āü„āĀ„ĀģśĒĮśŹīÁ≠Ė„āāŤ¨õ„Āė„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āęšł≠ŚįŹšľĀś•≠„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„ĀģÁźÜŤß£„āíś∑Ī„āĀ„āč„Āü„āĀ„ĀģśēôŤā≤„Éó„É≠„āį„É©„Ɇ„āĄŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™ŚĮĺÁ≠Ė„āíŚįéŚÖ•„Āô„āč„Āü„āĀ„ĀģśäÄŤ°ďÁöĄ„Ā™śĒĮśŹī„ĀĆśŹźšĺõ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀŚćė„Ā™„āč„Äƌ䙌äõÁõģś®ô„Äć„ĀßÁĶā„āŹ„āČ„Āõ„āč„Āď„Ā®„Ā™„ĀŹ„ÄĀŚģüŚäĻśÄß„Āģ„Āā„āčŚĮĺÁ≠Ė„Āł„Ā®ÁĻč„Āí„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā „Āē„āČ„Āę„ÄĀÁĶĆśłąÁĒ£ś•≠ÁúĀ„ĀĮ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ŚÖ®šĹď„Āģ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„āíŚģĘŤ¶≥ÁöĄ„ĀꌏĮŤ¶ĖŚĆĖ„ÉĽŤ©ēšĺ°„Āô„āč„Āü„āĀ„ĀģśĖį„Āü„Ā™Śą∂Śļ¶Ť®≠Ť®ą„āíťÄ≤„āĀ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ2026ŚĻīŚļ¶šł≠„ĀģŚą∂Śļ¶ťĖčŚßč„āíÁõģśĆá„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģŚą∂Śļ¶„ĀĆŚįéŚÖ•„Āē„āĆ„āĆ„Āį„ÄĀOEM„ĀĮŚŹĖŚľēŚÖą„Āģ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠ĖÁä∂ś≥Ā„āíŚģöťáŹÁöĄ„Āęśä䜏°„Āó„ÄĀ„É™„āĻ„āĮ„Āģťęė„ĀĄšľĀś•≠„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶śĒĻŚĖĄ„āíšŅÉ„Āô„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āü„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥Áģ°ÁźÜ„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀUN-R155„ĀßśĪā„āĀ„āČ„āĆ„āč„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„ĀģÁģ°ÁźÜŤ≤¨šĽĽ„āíśěú„Āü„Āôšłä„Āß„āāťá捶Ā„Ā™šĽēÁĶĄ„ĀŅ„Ā®„Ā™„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā [‚Ķ]
2024ŚĻī8śúą19śó•
2024ŚĻī8śúą19śó•
śė®šĽä„ÄĀŚ§ö„ĀŹ„Āģ„É°„Éá„ā£„āĘ„ĀĆŚźĄŚõĹ„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼ʜäÄŤ°ďšļčśÉÖ„ā팏Ė„āäšłä„Āí„Ā¶„ĀĄ„āč„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„Āģ‚Ä̍ᙌčēťĀ荼ʂÄĚ„ĀĮŤá™ŚčēŤĽä„Āęśź≠ŤľČ„Āē„āĆ„āčECUÔľąťõĽŚ≠źŚą∂Śĺ°Ť£ÖÁĹģ„ĀģÁ∑ŹÁßį„ÄāElectronic Control Unit„Āģť†≠śĖáŚ≠ó„Ā®ŚŹĖ„āčԾȄāĄśßė„ÄÖ„Ā™„āĽ„É≥„āĶ„Éľ„ĀĆŤ§áťõĎ„Ā™ťĀďŤ∑ĮÁä∂ś≥Ā„āíťĀ©ś†ľŚą§śĖ≠„Āô„āč„ÄĀŤ®Ä„āŹ„Āį‚ÄĚÁĄ°šļļ‚ÄĚťĀ荼ʄāíśĆá„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Éą„É®„āŅŤá™ŚčēŤĽäś†™ŚľŹšľöÁ§ĺ„ĀĆśé≤„Āí„Ā¶„ĀĄ„āč‚ÄĚ„Āô„ĀĻ„Ā¶„Āģšļļ„ĀęÁ߼Śčē„ĀģŚĖú„Ā≥„āí‚ÄĚ„ā팏∂„Āą„Ā¶„ĀŹ„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„Āģ„Āā„āčśäÄŤ°ď„Āß„Āô„Äā šłÄśĖĻ„ÄĀšĽäŚõ썮ėŤľČ„Āô„āčťĀ†ťöĒŚěčŤá™ŚčēťĀ荼ʄĀĮ„ÄĀ1„Ā§„ĀģŤĽäšł°„Ā®„Āó„Ā¶Ť¶č„āč„Ā®‚ÄĚÁĄ°šļļ‚ÄĚťĀ荼ʄĀß„Āā„āč„Āď„Ā®„ĀĮŚČćŤŅį„Āģ‚Ä̍ᙌčēťĀ荼ʂÄĚ„Ā®Ś§Č„āŹ„āä„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„ĀĆ„ÄĀŚą∂Śĺ°„ĀģšłĽŚĹĻ„ĀĮ‚ÄĚšļļ‚ÄĚ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äāšĺč„Āą„ĀįŚą∂Śĺ°„āĽ„É≥„āŅ„Éľ„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ťĀ†ťöĒ„ĀģŚ†īśČÄ„ĀęťĀ荼ʍÄÖ„ĀĆ„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŤĽä„āíśďćšĹú„Āó„Ā¶„ĀĄ„ā茆īŚźą„ĀĆ‚ÄĚťĀ†ťöĒŚěč‚Ä̍ᙌčēťĀ荼ʄĀę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāŚźĆ„Āė‚ÄĚÁĄ°šļļ‚ÄĚ„Āß„āā„ÄĀŤá™ŚčēťĀ荼ʄĀ®ťĀ†ťöĒŚěčŤá™ŚčēťĀ荼ʄĀĮÁõģÁöĄ„āĄÁĒ®ťÄĒ„ĀĆÁēį„Ā™„āä„ÄĀ„Āĺ„ĀüŚŅÖŤ¶Ā„Ā™śäÄŤ°ď„Āę„āā„ĀĚ„āĆ„Āě„āĆ„ĀģŤČ≤„ĀĆŚáļ„Ā¶„Āć„Āĺ„Āô„ÄāšĽäŚõě„ĀĮ„ÄĀťĀ†ťöĒŚěčŤá™ŚčēťĀ荼ʄĀę„Éē„ā©„Éľ„āę„āĻ„āíŚĹď„Ā¶„ÄĀ„ĀĚ„ĀģśäÄŤ°ď„āĄ„É°„É™„ÉÉ„Éą„Āä„āą„Ā≥ŚõĹŚÜÖšļčšĺč„ā퍮ėŤľČ„Āó„Āü„ĀĄ„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā ŚľäÁ§ĺ„ĀģśäÄŤ°ď„āíťĀ©ÁĒ®„Āó„ĀüťĀ†ťöĒŚěčŤá™ŚčēťĀ荼ʄā∑„āĻ„É܄Ɇ„āíťĖčÁôļ„ÉĽśŹźšĺõ„Āó„Ā¶„Āä„āä„Āĺ„Āô„Äā„ā™„Éö„ɨ„Éľ„āŅ„Éľ„ĀĆÁõīśé•„Āꍼ䚳°„ā팹∂Śĺ°„Āô„āčśĖĻś≥ē„Āä„āą„Ā≥Áä∂ś≥Ā„Āꌟą„Ā܍ᙌčēťĀ荼ʄĀģ„Éę„Éľ„Éę„ā휏źšĺõ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀßťĖďśé•ÁöĄ„ĀęťĀ荼ʄāí„āĶ„ÉĚ„Éľ„Éą„Āô„āčśĖĻś≥ē„ā휏źšĺõ„Āó„ÄĀŚģČŚÖ®„Ā™ťĀ†ťöĒŚěčŤá™ŚčēťĀ荼ʄāí„āĶ„ÉĚ„Éľ„Éą„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŤ©≥„Āó„ĀŹ„ĀĮ„Āď„Ā°„āČ„āí„ĀĒŤ¶ß„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā ťĀ†ťöĒŚěčŤá™ŚčēťĀ荼ĘÔľąťĀ†ťöĒśďćšĹúԾȄĀĆÁôĽŚ†ī„Āó„ĀüŤÉĆśôĮ„Ā®ŚŅÖŤ¶ĀśÄß ÁôĽŚ†īŤÉĆśôĮ„ĀĮŤá™ÁĄ∂ÁĀĹŚģ≥„Ā™„Ā©„ĀģśúČšļč„Āģťöõ„ĀģŚĮĺŚŅú„āíśó©„ĀŹ„Āó„Āü„ĀĄ„Āď„Ā®„ĀĆśĆô„Āí„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāÁĀĹŚģ≥„ĀģŚ§ö„ĀŹ„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀŤá™Ť°õťöä„Ā™„Ā©„Āģ„Éó„É≠„Éē„āß„ÉÉ„ā∑„Éß„Éä„Éę„ĀĮŚć≥śó•ÁŹĺŚ†ī„ĀłŤ°Ć„Āć„ÄĀťĀ©Śąá„Ā™śĒĮśŹī„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„āĆšĽ•Ś§Ė„Āģ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©„ĀģśĖĻ„ĀĮÁęč„Ā°ŚÖ•„āä„āíÁ¶Āś≠Ę„Āē„āĆ„ÄĀśĒĮśŹī„ĀꌟτĀč„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆŚõįťõ£„Āß„Āô„Äā„ĀĚ„ĀģÁźÜÁĒĪ„ĀĮšĹôťúá„Ā™„Ā©„Āęšľī„ĀÜšļĆś¨°ŤĘęŚģ≥„ĀģśäĎŚą∂„Āß„Āô„Äā „ĀĚ„Āď„Āßś≥®Áõģ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„ĀĆťĀ†ťöĒŚěčŤá™ŚčēťĀ荼ʄĀß„Āô„Äā‚ÄĚÁĄ°šļļ‚ÄĚ„Āß„Āā„ā茹©ÁāĻ„āíśúÄŚ§ßťôźśīĽÁĒ®„Āó„ÄĀŤŅÖťÄü„Ā™śĒĮśŹī„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāťÄöŚłł„Āß„ĀĮśĒĮśŹī„Āô„āčŚĀī„ĀĆťÄÜ„ĀęśĒĮśŹī„Āē„āĆ„āčŚĀī„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„Āó„Āĺ„āŹ„Ā™„ĀĄ„āą„ĀÜ„ÄĀŤĘęÁĀĹŚúį„Āĺ„Āß„ĀģŤĘęŚģ≥Áä∂ś≥ĀÔľąťĀďšł≠„Āģšļ§ťÄöÁä∂ś≥Ā„āĄ„ā§„É≥„Éē„É©Áä∂ś≥Ā„Ā™„Ā©ÔľČ„āíÁĘļŤ™ć„Āó„Āüšłä„ĀßśĒĮśŹī„āíťĖčŚßč„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó‚ÄĚÁĄ°šļļ‚ÄĚ„Āß„Āā„āĆ„Āį„ÄĀÁĘļŤ™ćšļ蝆քāā„āą„āäŚįĎ„Ā™„ĀŹśäĎ„Āą„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„ÄĀśĒĮśŹīťĖčŚßč„Āĺ„Āß„Āģśó•śēį„ĀĆŚźĄśģĶ„Āęśó©„ĀŹ„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā šĽ•šłä„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™Ťá™ÁĄ∂ÁĀĹŚģ≥„ĀģśĒĮśŹī„Āꚼ£Ť°®„Āē„āĆ„āč„āą„ĀÜ„Āę„ÄĀťĀ†ťöĒŚěčŤá™ŚčēťĀ荼ʄĀģŚŅÖŤ¶ĀśÄß„ĀĮśäÄŤ°ď„ĀģťÄ≤ś≠©„Ā®ŚÖĪ„Āę„ÄĀŚĻī„ÄÖŚĘóŚä†„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā ťĀ†ťöĒŚěčŤá™ŚčēťĀ荼ʄĀģśäÄŤ°ďŤ¶ĀšĽ∂ Ť§áťõĎ„Āę„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀĆÁĶ°„ĀŅŚźą„ĀÜÁŹĺŚú®„ĀģŤá™ŚčēŤĽä„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀťĀ†ťöĒśďćšĹú„āíŚģČŚÖ®„ĀęÁĘļŚģü„ĀęŚģüśĖĹ„Āô„āč„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀŚ§ö„ĀŹ„ĀģśäÄŤ°ďŤ¶ĀšĽ∂„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāšĽäŚõě„ĀĮ‚φťĀ†ťöĒ„Āč„āČÁĘļŚģü„Āč„Ā§„āŅ„ā§„Ɇ„É™„Éľ„ĀęśÉÖŚ†Ī„Ā®ŚĪä„ĀĎ„āčťÄöšŅ°śäÄŤ°ď„Ā®‚Ď°ťĀ†ťöĒ„Āč„āČ„ĀģśďćšĹú„Āę„Ā™„ĀŹ„Ā¶„ĀĮ„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄśė†ŚÉŹśäÄŤ°ď„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶Ť®ėŤŅį„Āó„Āĺ„Āô„Äā „Āĺ„Āö„ĀĮ„ÄĀťÄöšŅ°śäÄŤ°ď„Āß„Āô„ÄāšĽ£Ť°®„Āē„āĆ„āč„āā„Āģ„ĀĆ‚ÄĚV2XÔľąVehicle to XԾȂÄĚ„Āß„ÄĀŤĽäšł°„Ā®śßė„ÄÖ„Ā™„āā„Āģ„Ā®„ĀģťĖď„ĀģťÄöšŅ°„āĄťÄ£śźļ„ā퍰ƄĀÜśäÄŤ°ď„Āģ„Āď„Ā®„āíśĆá„Āó„Āĺ„Āô„ÄāŤĽä„Āęśßė„ÄÖ„Ā™ś©üŚô®„āĄťÉ®ŚďĀ„āíśź≠ŤľČ„Āó„ÄĀŚłłśôā„ā≥„É≥„ÉĒ„É•„Éľ„āŅ„Éć„ÉÉ„Éą„ÉĮ„Éľ„āĮ„Āęśé•Á∂ö„Āē„Āõ„āč„Āď„Ā®„Āę„āą„āä„ÄĀťĀ荼ʄĀęťĖĘ„Āô„ā茹©šĺŅśÄß„ā팟Ϛłä„Āē„Āõ„Āĺ„Āô„Äā V2X„Āę„ĀĮŚ§ß„Āć„ĀŹ4Á®ģť°ě„Āģ„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā „ÉĽV2V„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆVehicle to Vehicle„Äć„ĀģÁē•„Āß„ÄĀŤĽäšł°ŚźĆŚ£ę„ĀĆťÄöšŅ°„ā퍰ƄĀÜ„Āď„Ā®„āíśĆá„Āó„Āĺ„Āô„Äā „ÉĽV2I„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆVehicle to Infrastructure„Äć„ĀģÁē•„Āß„ÄĀŤĽäšł°„Ā®ťĀďŤ∑ĮŚĎ®Ťĺļ„Āģ„ā§„É≥„Éē„É©ś©üŚô®„Ā®„ĀģťÄöšŅ°„ā퍰ƄĀÜśäÄŤ°ď„Āß„Āô„Äā „ÉĽV2P„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆVehicle to Pedestrian„Äć„ĀģÁē•„Āß„ÄĀŤĽäšł°„Ā®ś≠©Ť°ĆŤÄÖ„Ā®„ĀģťÄöšŅ°„ā퍰ƄĀÜśäÄŤ°ď„Āß„Āô„Äā [‚Ķ]
2024ŚĻī7śúą31śó•
2024ŚĻī7śúą31śó•
ÁŹĺšĽ£„ĀģŤá™ŚčēŤĽäśäÄŤ°ď„ĀģťÄ≤ŚĆĖ„Āęšľī„ĀĄ„ÄĀ„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„Éąśé•Á∂öś©üŤÉĹ„āí„āā„Ā§„ā≥„Éć„āĮ„ÉÜ„ÉÉ„ÉČ„āę„Éľ„ĀƜĕťÄü„ĀęśôģŚŹä„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀ„ÉČ„É©„ā§„Éď„É≥„āį„ĀģŚą©šĺŅśÄß„ĀĆŚźĎšłä„Āô„āč„Ā®ŚźĆśôā„Āę„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„É™„āĻ„āĮ„āāŚĘóŚ§ß„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀ2015ŚĻī„ĀęÁôļÁĒü„Āó„Āü„āł„Éľ„Éó„ÉĽ„ÉĀ„āß„É≠„ā≠„Éľ„Āģ„É™„ÉĘ„Éľ„Éą„ÉŹ„ÉÉ„ā≠„É≥„āįšļ蚼∂„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ÉŹ„ÉÉ„āę„Éľ„ĀĆťĀ†ťöĒśďćšĹú„ĀߍĽäšł°„ĀģŚą∂Śĺ°„ā팕™„ĀÜ„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ°ĚśíÉÁöĄ„Ā™šļčšĺč„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā „Āď„ĀÜ„Āó„ĀüŤÉĆśôĮ„āā„Āā„āä„ÄĀŤá™ŚčēŤĽä„Āģ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„ĀƜĕŚčô„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„ĀĆśėéÁĘļ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„Āď„Āß„ÄĀŚě茾ŹŤ™ćŤ®ľÔľąVTAÔľöVehicle Type ApprovalԾȄĀģśĚ°šĽ∂„Āę„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„ĀĆŤŅŌ䆄Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äāśú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀŤá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„Āģťá捶ĀśÄß„Ā®„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀęŚĮÜśé•„ĀęťĖĘťÄ£„Āô„āčŚě茾ŹŤ™ćŤ®ľÔľąVTAԾȄĀģšĽēÁĶĄ„ĀŅ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶ŚąÜ„Āč„āä„āĄ„Āô„ĀŹŤ™¨śėé„Āó„Āĺ„Āô„Äā ŚľäÁ§ĺ„ĀĮśäÄŤ°ďś©üťĖĘ„Ā®„Āó„Ā¶śĆáŚģö„Āē„āĆ„ÄĀVTAÔľąŤĽäšł°Śě茾ŹŤ™ćŤ®ľÔľČŚą∂Śļ¶„ĀęŚüļ„Ā•„Āć„ÄĀšł≠Áęč„Ā™Áę茆ī„Āß„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚĮ©śüĽ„ā퍰ƄĀ£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŤ©≥„Āó„ĀŹ„ĀĮ„Āď„Ā°„āČ„āí„ĀĒŤ¶ß„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā Śě茾ŹŤ™ćŤ®ľÔľąVTAԾȄĀ®„ĀĮšĹē„Āč Śě茾ŹŤ™ćŤ®ľÔľąVTAÔľöVehicle Type ApprovalԾȄĀ®„ĀĮ„ÄĀŤ£ĹťÄ†„Āē„āĆ„ĀüśĖįŚě荼䚳°„ĀĆŚźĄŚõĹ„Āģś≥ēÁöĄŚüļśļĖ„āíśļÄ„Āü„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„ā퍮ľśėé„Āô„āč„Āü„āĀ„ĀģŚą∂Śļ¶„Āß„Āô„Äā„Āď„ĀģŤ™ćŤ®ľ„ā팏ó„ĀĎ„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŤĽäšł°„ĀĮŚźąś≥ēÁöĄ„ĀꌳāŚ†ī„Āę„É™„É™„Éľ„āĻ„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāVTA„ĀģšłĽ„Ā™ŚĹĻŚČ≤„ĀĮ„ÄĀŤĽäšł°„ĀģŚģČŚÖ®śÄß„ÄĀÁíįŚĘÉśÄߍÉĹ„ÄĀ„Āä„āą„Ā≥„ĀĚ„ĀģšĽĖ„Āģś≥ēÁöĄŤ¶ĀšĽ∂„āíÁĘļŤ™ć„Āó„ÄĀś∂ąŤ≤ĽŤÄÖ„ĀęŚģČŚŅÉ„Āó„Ā¶Śą©ÁĒ®„Āó„Ā¶„āā„āČ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„Āô„ÄāVTA„ĀģŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āčŤá™ŚčēŤĽä„ĀĮ„ÄĀšĻóÁĒ®ŤĽä„ÄĀŚēÜÁĒ®ŤĽä„ÄĀšļĆŤľ™ŤĽä„ÄĀ„Éą„É©„ÉÉ„āĮ„ÄĀ„Éź„āĻ„Ā™„Ā©Ś§öŚ≤ź„Āę„āŹ„Āü„āä„Āĺ„Āô„ÄāŚźĄŚõĹ„ĀģŤ¶ŹŚą∂„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶„ÄĀ„Āď„āĆ„āČ„ĀģŤĽäšł°„ĀĆŚłāŚ†ī„ĀęśäēŚÖ•„Āē„āĆ„āčŚČć„Āę„ÄĀŚŅÖŤ¶Ā„Ā™Ť™ćŤ®ľ„ā팏ĖŚĺó„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā VTAŚŹĖŚĺó„Āģ„Éó„É≠„āĽ„āĻ VTA„ĀģŚŹĖŚĺó„Éó„É≠„āĽ„āĻ„Āę„ĀĮ„ĀĄ„ĀŹ„Ā§„Āč„Āģ„āĻ„ÉÜ„ÉÉ„Éó„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āö„ÄĀŤ£ĹťÄ†ŤÄÖ„ĀĮŤĽäšł°„ĀĆŤ¶ŹŚą∂ŚüļśļĖ„āíśļÄ„Āü„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„āíÁĘļŤ™ć„Āô„āč„Āü„āĀ„ĀęŚŅÖŤ¶Ā„Ā™śõłť°ě„āĄŤ©¶ť®ď„Éá„Éľ„āŅ„āíśļĖŚāô„Āó„Āĺ„Āô„Äāś¨°„Āę„ÄĀŤ™ćŚģö„Āē„āĆ„ĀüśäÄŤ°ďś©üťĖĘ„ĀĆśŹźŚáļ„Āē„āĆ„Āüśõłť°ě„āĄŤ©¶ť®ď„Éá„Éľ„āŅ„āíŚĮ©śüĽ„Āó„ÄĀŚŅÖŤ¶Ā„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶ŤĽäšł°„ĀģŚģüÁČ©Ť©¶ť®ď„ā퍰ƄĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āô„ĀĻ„Ā¶„ĀģŚüļśļĖ„āíśļÄ„Āü„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®ÁĘļŤ™ć„Āē„āĆ„āĆ„Āį„ÄĀŚě茾ŹŤ™ćŤ®ľ„ĀĆÁôļŤ°Ć„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā CSMS„Ā®SUMS„Āģťá捶ĀśÄß VTAŚŹĖŚĺó„Āę„ĀĮ„ÄĀCSMSÔľąCyber Security Management SystemԾȄĀ®SUMSÔľąSoftware Update Management SystemԾȄĀģŚįéŚÖ•„ĀĆŚŅÖť†ą„Āß„Āô„Äā „Āď„āĆ„āČ„Āģ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Āģś≥ēÁöĄś†Ļśč†„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀ2019ŚĻī„ĀęśĖĹŤ°Ć„Āē„āĆ„ĀüUNECE„ĀģśĖįŤ¶ŹŚČá„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģŤ¶ŹŚČá„Āę„āą„āä„ÄĀŤĽäšł°„É°„Éľ„āę„Éľ„ĀĮ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„É™„āĻ„āĮ„ā퍩ēšĺ°„Āó„ÄĀťĀ©Śąá„Ā™ŚĮĺÁ≠Ė„ā퍨õ„Āė„āč„Āď„Ā®„ĀĆÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā CSMS„ĀģŤ™ćŤ®ľ„ā팏ó„ĀĎ„āč„Āü„āĀ„ĀęŚŅÖŤ¶Ā„Ā™„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ CSMS„Āę„ĀĮ„ÄĀŤĽäšł°„ĀģŤ®≠Ť®ą„Āč„āČťĀčÁĒ®„Āĺ„Āß„Āģ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„É™„āĻ„āĮ„āíÁģ°ÁźÜ„Āô„āč„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Āß„Āô„ÄāšĽ•šłč„ĀģŤ¶ĀÁī†„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā 1.¬†¬†¬† [‚Ķ]
2024ŚĻī6śúą25śó•
2024ŚĻī6śúą25śó•
ś¨°šłĖšĽ£„Āģ„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£Á§ĺšľö„ĀģŚģüÁŹĺ„ĀꌟτĀĎ„ĀüŤá™ŚčēťĀ荼ʄāĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚŹä„Ā≥MaaS„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥„āíśČčśéõ„ĀĎ„āč„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éąś†™ŚľŹšľöÁ§ĺÔľąAUTOCRYPT Co., Ltd.„ÄĀhttps://www.autocrypt.jp„ÄĀśú¨Á§ĺÔľöťüďŚõĹ„āĹ„ā¶„Éę„ÄĀšĽ£Ť°®ŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ ťáĎ„ÉĽÁĺ©ťĆę„ÄĀšĽ•šłč„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„ɹԾȄĀĮEUŚźĎ„ĀύᙌčēŤĽäŚě茾ŹŤ™ćŤ®ľ„Āä„āą„Ā≥ÁôĽťĆ≤„āíśčÖŚĹď„Āô„āč„ā™„É©„É≥„ÉÄ„ĀģťĀďŤ∑Įšļ§ťÄöŚĪÄÔľąRijksdienst voor het Wegverkeer„ÄĀšĽ•šłčRDW ԾȄĀč„āČ„āĘ„āł„āĘ„ÉĽ„ÉĎ„ā∑„Éē„ā£„ÉÉ„āĮŚúįŚüü„ĀߌąĚ„āĀ„Ā¶„ÄƍᙌčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť™ćŤ®ľ„Āģ„ÉÜ„āĮ„Éč„āę„Éę„āĶ„Éľ„Éď„āĻś©üťĖĘ„Äć„ĀģŤ≥ᜆľ„āíÁć≤Śĺó„Āó„Āü„Āď„Ā®„āí„ĀäÁü•„āČ„Āõ„Āó„Āĺ„Āô„Äā¬† „āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘŚģöÁĺ©ŚěčŤá™ŚčēŤĽäÔľą„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„ÉĽ„Éá„ā£„Éē„ā°„ā§„É≥„ÉČ„ÉĽ„Éď„Éľ„āĮ„ÉęԾȄāĄ„ā≥„Éć„āĮ„ÉÜ„ÉÉ„ÉČ„āę„Éľ„āí„ĀĮ„Āė„āĀ„Ā®„Āô„āčŤá™ŚčēŤĽäťĖĘťÄ£„ĀģśäÄŤ°ď„ĀģťęėŚļ¶ŚĆĖ„Āę„Ā§„āĆ„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„Āģťá捶ĀśÄß„ĀĆťęė„Āĺ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāEU„Āß„ĀĮ„ÄĀ2024ŚĻī7śúą„Āč„āČÁĒüÁĒ£„Āē„āĆ„āčśĖįŚě荼䚳°„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶Śě茾ŹŤ™ćŤ®ľ„Āę„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀęťĖĘ„Āô„ā荶ĀšĽ∂ÔľąUN-R155„ÄĀUN-R156ԾȄĀģŚģüŤ£Ö„ĀĆÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„ÄĀ2026ŚĻī„Āč„āČ„ĀĮśóĘŚ≠ė„ĀģŤĽäšł°„Āę„āāŚźĆŤ¶ŹŚČá„Āł„ĀģťĀ©Śźą„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀŤá™ŚčēŤĽä„É°„Éľ„āę„Éľ„āĄťĖĘťÄ£šľĀś•≠„ĀĮ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„Āģťá捶ĀśÄß„āíŚÜ捙ćŤ≠ė„Āó„ÄĀťĀ©Śąá„Ā™ŚĮĺÁ≠Ė„ā퍨õ„Āė„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā¬†¬†¬†¬† „Āď„Āģ„Āü„Ā≥„ÄĀ„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éą„ĀĮ„ā™„É©„É≥„ÉÄ„ĀģťĀďŤ∑Įšļ§ťÄöŚĪÄÔľąRDWԾȄĀč„āČ„ÄƍᙌčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť™ćŤ®ľ„Āģ„ÉÜ„āĮ„Éč„āę„Éę„āĶ„Éľ„Éď„āĻś©üťĖĘ„Äć„ĀģŤ≥ᜆľ„āíÁć≤Śĺó„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā„āĘ„āł„āĘ„ÉĽ„ÉĎ„ā∑„Éē„ā£„ÉÉ„āĮŚúįŚüü„ĀߍᙌčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£šľĀś•≠„Āģšł≠„Āß„ĀĮŚąĚ„āĀ„Ā¶„ÉÜ„āĮ„Éč„āę„Éę„āĶ„Éľ„Éď„āĻś©üťĖĘ„ĀęśĆáŚģö„Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āď„ĀģŤ≥ᜆľŚŹĖŚĺó„Āę„āą„āä„ÄĀ„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éą„ĀĮ„ÄĆŚõĹťÄ£„ĀģŤĽäšł°Á≠Č„ĀģŚě茾ŹŤ™ćŚģöÁõłšļíśČŅŤ™ćŚćĒŚģö„Äć„ĀęŚä†Áõü„Āó„Ā¶„ĀĄ„āčśó•śú¨„ā팟ę„āÄ68ÁģáŚõĹ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀģśßčÁĮČ„Āč„āČŚě茾ŹŤ™ćŤ®ľ„āĶ„ÉĚ„Éľ„Éą„Āĺ„Āß„ÄĀšłÄŤ≤ę„Āó„Āü„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„ā휏źšĺõ„Āß„Āć„āčšľĀś•≠„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éą„ĀĮŚäĻÁéáÁöĄ„Ā™Śě茾ŹŤ™ćŤ®ľŚźĎ„ĀĎ„ÉÜ„āĮ„Éč„āę„Éę„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„ā휏źšĺõ„Āô„āč„Āü„āĀ„Āę„ÄĀśĚ•„āč7śúą„Āę„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ÉÜ„āĻ„Éą„āĽ„É≥„āŅ„Éľ„āíťĖčśČÄ„Āó„ÄĀŚąĚśúüŚĮ©śüĽ„Āč„āČŚģöśúüÁöĄ„Ā™ťĀ©ŚźąśÄßÁĘļŤ™ć„Āĺ„Āß„āĶ„ÉĚ„Éľ„Éą„Āô„āč„ÄĆAutoCrypt TS„Äć„ā휏źšĺõ„Āô„āčšļąŚģö„Āß„Āô„Äā¬†¬†¬†¬† „āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„ÉąšĽ£Ť°®ŚŹĖÁ∑†ŚĹĻÁ§ĺťē∑„ĀģťáĎ„ĀĮś¨°„Āģ„āą„ĀÜ„ĀęŤŅį„ĀĻ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ÄƍᙌčēŤĽäÁĒ£ś•≠„ā팏Ė„āäŚ∑Ľ„ĀŹ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„É™„āĻ„āĮ„ĀĮś∑ĪŚąĽŚĆĖ„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀĮŚŅÖŤ¶ĀšłćŚŹĮś¨†„Ā™„āā„Āģ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĚ„Āģťá捶ĀśÄß„ĀĆ„Āĺ„Āô„Āĺ„Āôťęė„Āĺ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚľäÁ§ĺ„ĀƍᙌčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť™ćŤ®ľ„Āģ„ÉÜ„āĮ„Éč„āę„Éę„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„ā휏źšĺõ„Āô„āčś©üťĖĘ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģŤ≥ᜆľ„ā팏ĖŚĺó„Āó„Āü„Ā†„ĀĎ„Āęśó•śú¨„ĀģŤá™ŚčēŤĽä„É°„Éľ„āę„Éľ„ĀģEU„Āł„ĀģťÄ≤Śáļ„āíÁ©ćś•ĶÁöĄ„Āę„āĶ„ÉĚ„Éľ„Éą„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āć„Āü„ĀĄ„Ā®ŤÄÉ„Āą„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Ä欆
2024ŚĻī4śúą29śó•
2024ŚĻī4śúą29śó•
100ŚĻī„ĀꚳČļ¶„ĀģŚ§ßŚ§ČťĚ©śúü„āíŤŅé„Āą„Ā¶„ĀĄ„āčŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀśäÄŤ°ď„ĀģťÄ≤ś≠©„ĀĮÁõģ„Āĺ„Āź„āč„Āó„ĀĄÁä∂ś≥Ā„ĀĆÁ∂ö„ĀĄ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāACC(„ā™„Éľ„Éą„ÉĽ„āĮ„Éę„Éľ„āļ„ÉĽ„ā≥„É≥„Éą„É≠„Éľ„Éę)„āĄAHB(„ā™„Éľ„Éą„ÉĽ„ÉŹ„ā§„Éď„Éľ„Ɇ„ÉĽ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ)/AHS(„āĘ„ÉÄ„Éó„ÉÜ„ā£„ÉĖ„ÉĽ„ÉŹ„ā§„Éď„Éľ„Ɇ„ÉĽ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ)„Ā™„Ā©„ÄĀ„Āā„ĀŹ„Āĺ„ĀßťĀ荼ʄĀęŚĮĺ„Āô„ā茹©šĺŅśÄß„āĄŚģČŚÖ®śÄß„ĀģŚźĎšłä„āíÁõģÁöĄ„Ā®„Āó„ĀüŤĽäŚÜÖ„āĮ„É≠„Éľ„āļ„ÉČ„Āģś©üŤÉĹ„ĀĆ„Ā©„ĀģŤĽäšł°„Āę„āāś®ôśļĖÁöĄ„Āęśź≠ŤľČ„Āē„āĆ„Āü„Āč„Ā®śÄĚ„Āą„Āį„ÄĀÁŹĺŚú®„Āß„ĀĮ„ÄĀ„āĻ„Éě„Éõ„āíšĹŅÁĒ®„Āó„ĀüŤĽäšł°„ĀģťĖčťĆ†/śĖŝƆ„ÄĀ„ĀĚ„āĆšĽ•Ś§Ė„Āę„āā„É™„ÉĘ„Éľ„Éą„ā≥„É≥„Éą„É≠„Éľ„Éę„Ā®ŚĎľ„Āį„āĆ„āčťĀ†ťöĒ„ĀߍĽäšł°„āíŚčē„Āč„Āôś©üŤÉĹ„Āĺ„ĀߌĹď„Āü„āäŚČć„Āę„Ā™„āć„ĀÜ„Ā®„Āó„Ā¶„Āć„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā „Āó„Āč„Āó„ÄĀśäÄŤ°ď„ĀĆťÄ≤ś≠©„Āô„ā蚳ĜĖĻ„Āß„ÄĀśā™„ĀĄŚĀīťĚĘ„āāŚáļ„Ā¶„Āć„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĮśäÄŤ°ď„ĀģÁ©ī„āí„Ā§„ĀĄ„Āü„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„Āß„Āô„Äāśė®šĽä„Éč„É•„Éľ„āĻ„Ā™„Ā©„Āģ„É°„Éá„ā£„āĘ„ĀߌŹĖ„āäšłä„Āí„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āčÁĒüÁĒ£ŚĀúś≠Ę„āĄť°ßŚģĘśÉÖŚ†Ī„ĀģśĶĀŚáļ„Ā™„Ā©„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„Āę„āą„āč„ā§„É≥„ā∑„Éá„É≥„Éą„ĀĆśó•„ÄÖÁôļÁĒü„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„ĀĮŤĽäšł°„ĀģŚĹĪťüŅ„ĀęÁēô„Āĺ„āČ„Āö„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„ā팟ę„āčᙌčēŤĽäś•≠ÁēĆ„āíŚ∑Ľ„ĀćŤĺľ„āÄšļčśÖč„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®Ť®Ä„Āą„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āč„āČ„ĀģŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆ„ĀĮ„ÄĀśäÄŤ°ď„ĀģťÄ≤ś≠©„ĀęŚä†„Āą„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„Āę„Ā©„ĀÜŚĮĺŚŅú„Āó„ÄĀ„ĀĄ„Āč„Āę„Āó„Ā¶„É™„āĻ„āĮ„āíśłõ„āČ„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āč„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āď„Āߌą∂Śģö„Āē„āĆ„Āü„Āģ„ĀĆ„ÄĀŤá™Ś∑•šľöÔľŹťÉ®Ś∑•šľö„ÉĽ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„Āß„Āô„ÄāšĽäŚõě„ĀģŤ®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀŤá™Ś∑•šľö/ťÉ®Ś∑•šľö„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„ĀęťĖĘ„Āô„ā茹∂Śģö„ĀģŤÉĆśôĮ„ÄĀ„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„ĀģÁõģÁöĄ„ÄĀŚĮĺŤĪ°„Āę„Ā™„āčÁĒ£ś•≠„āĄšľĀś•≠„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶Ť™¨śėé„Āó„Āĺ„Āô„Äā „ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥Śą∂Śģö„ĀģŤÉĆśôĮ„Ā®ÁõģÁöĄ „āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ„Āģ„É™„āĻ„āĮ„āíśĆô„Āí„āč„Ā® „ÉĽ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„ā팾∑ŚĆĖšł≠„ĀģťĖĘšŅāšľĀś•≠„āĄŚŹĖŚľēŚÖąÁ≠Č„Āģ„Éć„ÉÉ„Éą„ÉĮ„Éľ„āĮ„Āł„Āģšłćś≠£šĺĶŚÖ• „ÉĽšľĀś•≠ťĖď„Éć„ÉÉ„Éą„ÉĮ„Éľ„āĮ„āíÁĶĆÁĒĪ„Āó„ĀüśĒĽśíÉ „ÉĽś®ôÁöĄšľĀś•≠„ĀĆŚą©ÁĒ®„Āô„āč„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„āĄŤ£ĹŚďĀ„Āł„Āģšłćś≠£„Ā™„Éó„É≠„āį„É©„Ɇ„ĀģŚüč„āĀŤĺľ„ĀŅÁ≠Č„Āģ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„āíÁčô„Ā£„Āü„āĶ„ā§„Éź„ÉľśĒĽśíÉ „Ā™„Ā©„ÄĀśēįŚ§ö„ĀŹ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāŤá™ŚčēŤĽä„É°„Éľ„āę„Éľ„āĄ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„āíśßčśąź„Āô„ā茟ĄÁ§ĺ„ĀęśĪā„āĀ„āČ„āĆ„āčŤá™ŚčēŤĽäÁĒ£ś•≠ŚõļśúČ„Āģ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„É™„āĻ„āĮ„āíŤÄÉśÖģ„Āó„Āü„ÄĀŚźĎ„Āď„ĀÜ3ŚĻī„ĀģŚĮĺÁ≠Ė„Éē„ɨ„Éľ„Ɇ„ÉĮ„Éľ„āĮ„āĄś•≠ÁēĆŚÖĪťÄö„ĀģŤá™Ś∑ĪŤ©ēšĺ°ŚüļśļĖ„āíśėéÁ§ļ„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆŚÖ®šĹď„Āģ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„Āģ„ɨ„Éô„Éę„āĘ„ÉÉ„Éó„āĄŚĮĺÁ≠Ė„ɨ„Éô„Éę„ĀģŚäĻÁéáÁöĄ„Ā™ÁāĻś§ú„āíśé®ťÄ≤„Āô„āč„Āď„Ā®„āíÁõģÁöĄ„Āę„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„ĀĆŚą∂Śģö„Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā „ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„ĀģŚĮĺŤĪ° „ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„ĀģŚĮĺŤĪ°„ĀĮšłčŤ®ė„Ā®ŚģöÁĺ©„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā „ÉĽŤá™ŚčēŤĽäÁĒ£ś•≠„ĀęťĖĘšŅā„Āô„āčŚÖ®„Ā¶„ĀģšľöÁ§ĺÔľąÁČĻ„Āę„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ś•≠Śčô„ĀęťĖĘšłé„Āó„Ā¶„ĀĄ„āčÔľČ „Éľ CISO ÔľąśúÄťęėśÉÖŚ†Ī„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť≤¨šĽĽŤÄÖÔľČ „Éľ „É™„āĻ„āĮÁģ°ÁźÜťÉ®ťĖÄ „Éľ Áõ£śüĽťÉ®ťĖÄ „Éľ „āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺŚŅúťÉ®ťĖÄ „Éľ śÉÖŚ†Ī„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀģťĖčÁôļ/ťĀčÁĒ®ťÉ®ťĖÄ „Éľ „Éá„Éľ„āŅ„Éě„Éć„āł„É°„É≥„ÉąťÉ®ťĖÄ [‚Ķ]
2023ŚĻī10śúą6śó•
2023ŚĻī10śúą6śó•
„Āď„ĀģŚļ¶„ÄĀ„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éąś†™ŚľŹšľöÁ§ĺ„ĀĮ„ÄĀ2023ŚĻī10śúą26śó•Ôľąśú®ÔľČ„Āč„āČ11śúą5śó•Ôľąśó•ÔľČ„Āĺ„ĀßśĚĪšļ¨„Éď„ÉÉ„āį„āĶ„ā§„Éą„ĀßťĖčŚā¨„Āē„āĆ„āč„ÄĆ„āł„É£„ÉĎ„É≥„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£„ā∑„Éß„Éľ2023ÔľąJAPAN MOBILITY SHOWԾȄÄć„ĀģÁČĻŚą•šľĀÁĒĽŚĪēÁ§ļ„ÄĆStartup Future Factory„Äć„ĀęŚáļŚĪē„Āó„Āĺ„Āô„Äā „āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éą„ĀĮ„ÄĀ10śúą31śó•ÔľąÁĀęԾȄÄĀ11śúą1śó•ÔľąśįīԾȚł°śó•„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶„ÄĀťė≤ÁĀĹ„āí„ÉÜ„Éľ„Éě„Āę„Āó„ĀüÁČĻŤ®≠„ÉĖ„Éľ„āĻ„Āß„ÄĀWP29 UN‚ÄźR155ŚŹä„Ā≥ISO/SAE21434„ĀęśļĖśč†„Āó„ĀüCSMSÔľą„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Áģ°ÁźÜ„ā∑„āĻ„É܄ɆԾȄĀģÁĘļÁę茏ä„Ā≥ťĀčÁĒ®śą¶Áē•„ā휏źś°ą„Āē„Āõ„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā†„Āć„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŤĽäŤľČ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„ĀģOSSŚąÜśěź„ÉĄ„Éľ„Éę„ÄĆAutocrypt Security Analyzer„Äć„ÄĀŤĽäŤľČŚįāÁĒ®„Āģ„Éē„ā°„āł„É≥„āį„ÉÜ„āĻ„ÉÜ„ā£„É≥„āį„ÉĄ„Éľ„Éę„ÄĆAutoCrypt Security Fuzzer„Äć„ÄĀŤĽäŤľČ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥„ÄĆAutoCrypt IVS„Äć„Āĺ„Āß„ÄĀŤá™ŚčēŤĽäťĖčÁôļ„Éó„É≠„āĽ„āĻ„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚēŹť°Ć„Āģśó©śúüÁôļŤ¶č„Ā®ŚąÜśěź„ÄĀŚēŹť°Ć„ĀęťĀ©„Āó„ĀüŤß£śĪļÁ≠Ė„Āĺ„Āß„ĀģšłÄťÄ£„ĀģśĶĀ„āĆ„āí„āę„Éź„Éľ„Āß„Āć„āčśßė„ÄÖ„Ā™„É©„ā§„É≥„Éä„ÉÉ„Éó„āíŚĪēÁ§ļ„Āó„Āĺ„Āô„Äā śúÄśĖį„ĀģŤá™ŚčēťĀ荼ʜäÄŤ°ďŚŹä„Ā≥Ťá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀꍹąŚĎ≥„Āģ„Āā„āčśĖĻ„ĀĮ„ÄĀŚĹďÁ§ĺ„ÉĖ„Éľ„āĻ„Āę„Āú„Ā≤Ť∂≥„āíťĀč„āď„Āß„ĀĄ„Āü„Ā†„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā ‚Ė†„ā§„Éô„É≥„Éąś¶āŤ¶Ā¬†¬† ‚óÜŚźćÁßįÔľö„āł„É£„ÉĎ„É≥„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£„ā∑„Éß„Éľ2023ÔľąJAPAN MOBILITY SHOWÔľČ ‚óÜšľöśúüÔľö2023ŚĻī10śúą26śó•(śú®)ÔĹě11śúą5śó•(śó•) ÔľąšłÄŤą¨ŚÖ¨ťĖčśó•„ĀĮ„ÄĀ10śúą28śó•ÔľąŚúüÔľČÔĹě11śúą5śó•Ôľąśó•ÔľČ„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāÔľČ ‚óÜšłĽŚā¨ÔľöšłÄŤą¨Á§ĺŚõ£ś≥ēšļļ śó•śú¨Ťá™ŚčēŤĽäŚ∑•ś•≠šľö ‚óÜšľöŚ†īÔľöśĚĪšļ¨„Éď„ÉÉ„āį„āĶ„ā§„Éą ŚÖ¨ŚľŹHPÔľöhttps://www.japan-mobility-show.com/ ‚Ė†ŚĹďÁ§ĺŚáļŚĪēśÉÖŚ†Ī ‚óÜšľöśúüÔľö2023ŚĻī10śúąÔľďԾϜó•(ÁĀę)ÔĹě11śúąÔľĎśó•(śįī)„ÄÄ09:00ÔĹě19:00 ‚óÜŚáļŚĪē„ÉĖ„Éľ„āĻšĹćÁĹģÔľö [‚Ķ]
2023ŚĻī8śúą24śó•
2023ŚĻī8śúą24śó•
„Āď„ĀģŚļ¶„ÄĀ„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éąś†™ŚľŹšľöÁ§ĺ„ĀĮ„ÄĀ2023ŚĻī9śúąÔľēśó•ÔľąÁĀęԾȄĀč„āČÔľĖśó•ÔľąśįīԾȄĀęťĖčŚā¨„Āē„āĆ„āč„ÄĆťüďŚõĹś¨°šłĖšĽ£„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£śäÄŤ°ďŚĪē2023„Äć„ĀęŚáļŚĪē„ĀĄ„Āü„Āó„Āĺ„Āô„Āģ„Āß„ĀäÁü•„āČ„Āõ„Āó„Āĺ„Āô„Äāśė®ŚĻī„ĀęÁ∂ö„Āć„ÄĀÔľíŚĻīťÄ£Á∂ö„ĀģŚáļŚĪē„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā śó•śú¨„Āģ„ĀŅ„Ā™„āČ„ĀöśĶ∑Ś§Ė„Āß„āāÁ∂ö„ÄÖ„Ā®ťõĽŚčēŚĆĖ„āĄEVŚĆĖ„ĀƜ鮄ĀóťÄ≤„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„Āģťá捶ĀŚļ¶„ĀĮ„Āĺ„Āô„Āĺ„Āôťęė„Āĺ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŤá™ŚčēŤĽä„É°„Éľ„āę„Éľ„āĄ„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„ÉľšľĀś•≠„Āę„āāWP29„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ś≥ēŤ¶Ź„ĀęŚüļ„Ā•„ĀŹCSMSśßčÁĮČ„ĀģŚĮĺŚŅú„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„āčšł≠„ÄĀŚÖ∑šĹďÁöĄ„Āę„Ā©„ĀÜŚĮĺŚŅú„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āč„ĀĆŤ™≤ť°Ć„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā šĽäŚõě„ĀģŚáļŚĪē„Āß„ĀĮ„ÄĀWP29ś≥ēŤ¶Ź„ĀģŚŹāÁÖߌֹ„Āß„Āā„āčISO/SAE21434„ĀęŚüļ„Ā•„ĀŹ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚģüŤ£Ö„ĀģťÄ≤„āĀśĖĻ„Ā®„Āó„Ā¶ŚĹďÁ§ĺ„ĀĆśŹźś°ą„Āô„āč„ā≥„É≥„āĶ„Éę„ÉÜ„ā£„É≥„āįŚĮĺÁ≠Ė„āí„ĀĒÁīĻšĽč„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀÁĶĪŚźąŚěč„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥„ÄĆAutoCrypt IVS„Äć„Āč„āČ„ÄĀŤĽäŤľČ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘŚįāÁĒ®„Éē„ā°„āł„É≥„āį„ÉÜ„āĻ„Éą„ÉĄ„Éľ„Éę„ÄĆAutoCrypt Security Fuzzer„Äć„āĄŤĽäŤľČOSSŤĄÜŚľĪśÄߍ®ļśĖ≠„ÉĽŤá™ŚčēŚąÜśěź„ÉĄ„Éľ„Éę„ÄĆAutoCrypt Security Analyzer„Äć„Āĺ„Āß„ÄĀŤá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚįāťĖÄšľĀś•≠„Ā™„āČ„Āß„ĀĮ„ĀģŤ£ĹŚďĀ„É©„ā§„É≥„Éä„ÉÉ„Éó„āíŚĪēÁ§ļ„Āó„Āĺ„Āô„Äā ŚĹďÁ§ĺ„ĀĮ„ÄĀ15ŚĻīšĽ•šłäŚüĻ„Ā£„Ā¶„Āć„ĀüŤá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£śäÄŤ°ď„Éé„ā¶„ÉŹ„ā¶„Ā®ŚõĹŚÜÖŚ§Ė„Āß„ĀģŚģüŤ£ÖÁĶĆť®ď„āíśīĽ„Āč„Āó„ÄĀšĽäŚĺĆ„āā„ÄĀ„ĀäŚģĘśßė„Āģ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť™≤ť°ĆŤß£śĪļ„ĀꌟτĀĎ„Ā¶ŚŹĖ„āäÁĶĄ„āď„Āß„Āĺ„ĀĄ„āä„Āĺ„Āô„Äā ‚Ė†„ā§„Éô„É≥„Éąś¶āŤ¶Ā¬†¬† ‚óÜŚźćÁßįÔľöťüďŚõĹś¨°šłĖšĽ£„ÉĘ„Éď„É™„ÉÜ„ā£śäÄŤ°ďŚĪē2023 ‚óÜšľöśúüÔľö2023ŚĻī9śúą5śó•(ÁĀę)ÔĹě9śúą6śó•(śįī)ÔľĆ10:00~17:00 ‚óÜšłĽŚā¨ÔľöKOTRAÔľąťüďŚõĹŤ≤Ņśėď„āĽ„É≥„āŅ„ÉľŚźćŚŹ§ŚĪčÔľČ ‚óÜšľöŚ†īÔľö„ÉĚ„Éľ„Éą„É°„ÉÉ„āĽ„Ā™„ĀĒ„āĄ„ÄÄ„ā≥„É≥„Éô„É≥„ā∑„Éß„É≥„āĽ„É≥„āŅ„Éľ ‚óÜťĖčŚā¨ŚĹĘŚľŹÔľöšľöŚ†īťĖčŚā¨ÔľąŚŹāŚä†ÁĄ°śĖô„ÉĽšļčŚČćÁôĽťĆ≤Śą∂ÔľČ ŚÖ¨ŚľŹHPÔľöhttps://kor-mobitech.com/¬† ‚Ė†ŚáļŚĪēŤ£ĹŚďĀ„ĀģŤ©≥Áīį„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶¬† AutoCrypt IVSÔľöhttps://www.autocrypt.jp/in-vehicle-system-security/ AutoCrypt Security FuzzerÔľöhttps://www.autocrypt.jp/security-fuzzer/ AutoCrypt AnalyzerÔľöhttps://www.autocrypt.jp/security-analyzer/
2023ŚĻī8śúą8śó•
2023ŚĻī8śúą8śó•
Ťá™ŚčēťĀ荼ʄāĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚŹä„Ā≥MaaS„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥„āíśČčśéõ„ĀĎ„āč„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éąś†™ŚľŹšľöÁ§ĺÔľąAUTOCRYPT Co., Ltd.„ÄĀśú¨Á§ĺÔľöťüďŚõĹ„āĹ„ā¶„Éę„ÄĀšĽ£Ť°®ŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ ťáĎ„ÉĽÁĺ©ťĆę„ÄĀšĽ•šłč„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„ɹԾȄĀĮ„ÄĀ8śúą22śó•ÔľąÁĀęÔľČ14śôāZoom„Āę„Ā¶„ÄĆWP29„ĀĆśĪā„āĀ„Ā¶„ĀĄ„āčŤá™ŚčēŤĽäŚźĎ„ĀĎ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÉÜ„Éľ„Éě„Āģ„ā¶„āß„Éď„Éä„Éľ„āíťĖčŚā¨„Āó„Āĺ„Āô„Äā ¬† Ť©≥ÁīįŚŹä„Ā≥ÁĒ≥Ťĺľ„ĀŅ„ĀĮ„Āď„Ā°„āČÔľąÁĄ°śĖô/šļčŚČćÁôĽťĆ≤Śą∂ÔľČ ÁĶāšļÜ„ĀĄ„Āü„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ĀĒŚŹāŚä†„Āā„āä„ĀĆ„Ā®„ĀÜ„ĀĒ„ĀĖ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā „ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„Āó„Ā¶„Āä„āä„Āĺ„Āô„Āģ„Āß„ÄĀ„ā¶„āß„Éď„Éä„Éľ„Éö„Éľ„āł„Āę„Ā¶„ĀäÁĒ≥„ĀóŤĺľ„ĀŅ„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā <„ā¶„āß„Éď„Éä„Éľś¶āŤ¶Ā> 2022ŚĻī7śúą„āą„āä„ÄĀWP29„Āßśé°śäě„Āē„āĆ„ĀüŤá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£śßčÁĮČÔľąCSMSԾȄĀęťĖĘ„Āô„ā荶ŹŚą∂„ĀĆťĖčŚßč„Āē„āĆ„ÄĀŤá™ŚčēŤĽäś•≠ÁēĆ„ĀߌĮĺŚŅú„ĀĆśú¨ś†ľŚĆĖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£śßčÁĮČ„ĀęśÖ£„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄšľĀś•≠„ÄĀś≥ēŤ¶ŹŤß£ťáą„āĄŚĮĺÁ≠ĖśßčÁĮČ„Āęśā©„āď„Āß„ĀĄ„āčšľĀś•≠„āāŚ§ö„ĀĄ„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Āč„Äā„ĀĚ„Āď„Āß„ÄĀŚľäÁ§ĺ„ĀĮOEM„āĄ„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„ĀęśĪā„āĀ„āČ„āĆ„āčWP29ś≥ēŤ¶ŹŤß£ťáą„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£śßčÁĮČ„ĀęťĖĘ„Āô„āč„āĪ„Éľ„āĻ„āĻ„āŅ„Éá„ā£„Éľ„ÄĀŚŅÖŤ¶Ā„Ā™„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥„Ā™„Ā©„ā팹܄Āč„āä„āĄ„Āô„ĀŹŤ™¨śėé„Āô„āčÁĄ°śĖô„ā¶„āß„Éď„Éä„Éľ„āíťĖčŚā¨„Āó„Āĺ„Āô„Āģ„Āß„ÄĀśėĮťĚě„ĀĒŚŹāŚä†„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā ÔľúťĖčŚā¨ś¶āŤ¶ĀÔľě „ÉÜ„Éľ„ÉěÔľöWP29„ĀĆśĪā„āĀ„Ā¶„ĀĄ„āčŤá™ŚčēŤĽäŚźĎ„ĀĎ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„Ā®„ĀĮÔľü ťĖčŚā¨śó•śôāÔľö2023ŚĻī8śúą22śó•ÔľąÁĀęÔľČ 14:00~15:00 ťĖčŚā¨Ś†īśČÄ„ÉĽŤ≤ĽÁĒ®Ôľö„ā™„É≥„É©„ā§„É≥ÔľąZoomԾȄÄĀÁĄ°śĖô ÁôĽŚ£áŤÄÖÔľö„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éąś†™ŚľŹšľöÁ§ĺ „ā≥„Éć„āĮ„ÉÜ„ÉÉ„ÉČ„āę„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£šļčś•≠ťÉ® ŚīĒ„ÄÄÁŹćŤĪ™(„ÉĀ„āß„ÉĽ„āł„É≥„Éõ) „ĀäÁĒ≥„ĀóŤĺľ„ĀŅÔľöÁĶāšļÜ„ĀĄ„Āü„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„Āó„Ā¶„Āä„āä„Āĺ„Āô„Āģ„Āß„ÄĀ„ā¶„āß„Éď„Éä„Éľ„Éö„Éľ„āł„Āę„Ā¶„ĀäÁĒ≥„ĀóŤĺľ„ĀŅ„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā Ôľú„Āď„āď„Ā™śĖĻ„Āę„Āä„Āô„Āô„āĀÔľě Ťá™ŚčēťĀ荼ʍĽä„ĀģťĖčÁôļ„Āęśźļ„āŹ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āčśĖĻ OEM„āĄ„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„Āģ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£śßčÁĮČ„ĀꌏĖ„āäÁĶĄ„Āĺ„āĆ„āčśĖĻ Ťá™ŚčēťĀ荼ʍĽä„Āģ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ĀꍹąŚĎ≥„ĀĆ„Āā„āčśĖĻ
2023ŚĻī4śúą25śó•
2023ŚĻī4śúą25śó•
Ťá™ŚčēťĀ荼ʄāĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚŹä„Ā≥MaaS„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥„āíśČčśéõ„ĀĎ„āč„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éąś†™ŚľŹšľöÁ§ĺÔľąAUTOCRYPT Co., Ltd.„ÄĀśú¨Á§ĺÔľöťüďŚõĹ„āĹ„ā¶„Éę„ÄĀšĽ£Ť°®ŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ ťáĎ„ÉĽÁĺ©ťĆę„ÄĀšĽ•šłč„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„ɹԾȄĀĆś†™ŚľŹšľöÁ§ĺ„ÉĚ„ÉÉ„Éó„ā≥„Éľ„É≥„ā∂„Éľ„ÉĽ„āł„É£„ÉĎ„É≥Ôľą PopcornSAR Co., Ltd.„ÄĀšĽ£Ť°®ŤÄÖÔľö„ÉĀ„āß„ÉĽ„āĻ„É≥„É®„Éó„ÄĀšĽ•šłč„ÉĚ„ÉÉ„Éó„ā≥„Éľ„É≥„ā∂„ɾԾȄĀ®„ÄĀ2023ŚĻī5śúą24śó•ÔľąśįīÔľČ~26śó•ÔľąťáĎԾȄĀęťĖčŚā¨„Āē„āĆ„āč„ÄĆšļļ„Ā®„ĀŹ„āč„Āĺ„Āģ„ÉÜ„āĮ„Éé„É≠„āł„ÉľŚĪē2023 YOKOHAMA„Äć„ĀęŚÖĪŚźĆŚáļŚĪē„Āó„Āĺ„Āô„Äā SDVťĖčÁôļ„ĀģŚä†ťÄüŚĆĖ„Āę„āą„āä„ÄĀ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„Ā®„ā≥„Éć„āĮ„ÉÜ„ÉÉ„ÉČśäÄŤ°ď„Āģťá捶ĀŚļ¶„ĀĆ„Āĺ„Āô„Āĺ„Āôťęė„Āĺ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āčšł≠„Āß„ÄĀšĽäŚõě„ĀĮŤá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚąÜťáé„Āꌾ∑„ĀŅ„āíśĆĀ„Ā§„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éą„Ā®„ÄĀ„āĻ„āŅ„Éľ„Éą„āĘ„ÉÉ„ÉóšľĀś•≠„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮšłĖÁēĆŚąĚ„ĀßAUTOSARś®ôśļĖśäÄŤ°ď„āíšŅĚśúČ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ÉĚ„ÉÉ„Éó„ā≥„Éľ„É≥„ā∂„Éľ„ĀĆŚÖĪŚźĆŚáļŚĪē„Āó„ÄĀSDV„ĀģťęėŚļ¶ŚĆĖŚŹä„Ā≥ŚģüÁĒ®ŚĆĖ„ĀꌟτĀĎ„Āü„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„āĹ„É™„É•„Éľ„ā∑„Éß„É≥„Ā®AUTOSARŚüļÁõ§„āíśīĽÁĒ®„Āó„ĀüSW„āĘ„Éľ„ā≠„ÉÜ„āĮ„ÉĀ„É£„āíŚĪēÁ§ļ„Āó„Āĺ„Āô„Äā „ÉĖ„Éľ„āĻ„Āß„ĀĮ„ÄĀ„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éą„Āģ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£śäÄŤ°ď„Ā®„ÉĚ„ÉÉ„Éó„ā≥„Éľ„É≥„ā∂„Éľ„ĀģAdaptive AUTOSARÔľąR20-11ԾȄāíťĀ©ÁĒ®„Āó„ĀüADAS/Ťá™ŚčēťĀ荼ʄĀģťĖčÁôļ„ÄĀ„ÉÜ„āĻ„Éą„ÄĀŤ©ēšĺ°„ā∑„Éä„É™„ā™„ĀģśŹźšĺõ„āí„Éá„āł„āŅ„Éę„ÉĄ„ā§„É≥šłä„Āß„ā∑„Éü„É•„ɨ„Éľ„ā∑„Éß„É≥„Āô„āč„ā≥„É©„Éú„Éá„ÉĘ„āāŤ°Ć„ĀÜšļąŚģö„Āß„Āô„Äā ¬† „ÄĆšļļ„Ā®„ĀŹ„āč„Āĺ„Āģ„ÉÜ„āĮ„Éé„É≠„āł„ÉľŚĪē2023 YOKOHAMA„ÄćŚĪēÁ§ļšľöś¶āŤ¶Ā„Äź„É™„āĘ„ÉęŚĪēÁ§ļšľö„ÄĎ ¬† šľöśúüÔľö2023ŚĻī 5śúą24śó•ÔľąśįīÔľČÔĹě5śúą26śó•ÔľąťáĎԾȚľöŚ†īÔľö„ÉĎ„ā∑„Éē„ā£„ā≥ś®™śĶúťĖčŚā¨śôāťĖďÔľö10:00ÔĹě18:00ÔľąśúÄÁĶāśó•„ĀĮ17:00„Āĺ„ĀßԾȌŹāŚä†śĖĻś≥ēÔľöŚŹāŚä†ÁĄ°śĖôÔľąšļčŚČćÁôĽťĆ≤Śą∂ԾȄÉĖ„Éľ„āĻÁē™ŚŹ∑Ôľö240šļčŚČćÁôĽťĆ≤URLÔľöhttps://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/registinfo/ „Äź„ā™„É≥„É©„ā§„É≥ŚĪēÁ§ļšľö„ÄĎ ¬†šľöśúüÔľö2023ŚĻī5śúą17śó•ÔľąśįīÔľČÔĹě6śúą7śó•ÔľąśįīԾȚľöŚ†īÔľöhttps://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/ ¬† ‚Ė†„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éą x „ÉĚ„ÉÉ„Éó„ā≥„Éľ„É≥„ā∂„ÉľŚáļŚĪēŚÜÖŚģĻ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶ ¬† 1ÔľéUNECE WP29ś≥ēŤ¶ŹŚĮĺŚŅú„ā≥„É≥„āĶ„Éę„ÉÜ„ā£„É≥„āį„āĶ„Éľ„Éď„āĻ¬†„āĘ„ā¶„Éą„āĮ„É™„Éó„Éą„Āß„ĀĮ„ÄĀŤá™ŚčēŤĽä„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Ť™ćŤ®ľ„ĀęťĖĘ„āŹ„āčCSMSśßčÁĮČŚŹä„Ā≥ŤĽäšł°Śě茾ŹŤ™ćŤ®ľ„ĀģŚŹĖŚĺó„āíśĒĮśŹī„Āô„āčŚĆÖśč¨ÁöĄ„Ā™„ā≥„É≥„āĶ„Éę„ÉÜ„ā£„É≥„āį„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„āíÁīĻšĽč„Āó„Āĺ„Āô„Äāť°ßŚģĘ„ĀĆWP29 [‚Ķ]